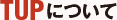機密文書が裏付ける侵攻前の米国の石油戦略、立ち上がったイラク市民社会
2003年の米国のイラク侵攻からまもなく10年です。侵攻と占領はイラク市民に膨大な数の死者を出し、ファッルージャでは劣化ウランが胎児を蝕み続けています。人間性を奪われた米軍兵士もPTSDに苦しみ、自殺する人が後を絶ちません。イギリスのジャーナリスト・活動家のグレッグ・マティットは、Fuel on the Fire: Oil and Politics in Occupied Iraq (火に油を注ぐ――占領下イラクの石油と政策)(2011年)の著者で、情報公開請求で得られた資料に基づいて、イラク侵攻前の米国防総省内で石油権益の確保が議論されていたことを明るみに出し、米国によるイラク侵攻と占領の動機の中心に石油があったことを裏付けました。一方で、イラクの市民社会は、米国の押し付ける石油法に反対の声を上げ、議会を動かして、成立を阻みました。本記事はマティットの著書のごく一部をまとめたものです。石油メジャーに続いて、日本企業も、2009年に石油資源開発株式会社(JAPEX)がガラフ油田の開発・生産権を取得し、今年2012年11月7日には国際石油開発帝石(INPEX)がイラク南部の石油開発権の契約を締結したばかりです。また三菱商事は、イラク石油省、ロイヤル・ダッチ・シェルと共同で、天然ガス回収・LNG精製施設を建設しています。米国と巨大石油企業によるイラクの石油の支配を許さないために、日本の私たちもイラク市民社会と連携したいと思います。(翻訳:荒井雅子/TUP)
イラク――石油メジャーの「任務は完了」か?
米国がもたらした災厄がいかに石油メジャーの興隆――と没落の可能性――につながったか
グレッグ・マティット
2011年、9年近い戦争と占領の末、米軍はようやくイラクから撤退した。現在、米軍に代わって力をもっているのは石油メジャーであり、数十年間ダメージを受けてきたイラクの石油生産は再び増加に転じた。ここへきてイラクは、石油制裁を受けているイランを抜いて、OPEC(石油輸出国機構)で第二位の地位を取り戻した。今や、世界的な石油の過剰供給が再び取りざたされるようになった。ということは、ようやく「任務が完了した」ということなのだろうか。
そうとも言えない。実は、イラクで石油企業がいかなる勝利を収めたとしても、それは2003年のジョージ・W・ブッシュの勝利のように一時的なものとなる可能性が高い。その主な理由は、これも主流メディアがあまりページを割こうとしない話の一つだが、イラク市民社会の役割にある。だがその話をする前に、今日イラクの石油に何が起きているのか、世界各地で「石油のために血を流すな」と抗議が行われた2003年から現在までの経過を見ておこう。
まず初めに、2年半前に石油メジャーがイラクに入って以来何が起きたか、その「実績」を見ておこう。政治的腐敗が激増した。欧米石油企業2社が、贈賄または収賄で捜査を受けている。イラク政府は、石油企業が実際に掘削した出来高には無頓着に、彼らが設定したまったく非現実的な生産目標どおりの掘削費を支払っている。請負会社は油井掘削費を大幅に水増ししているが、勘定を払うのはイラク政府であり、石油企業は一向に気にしていない。
さらに、石油巨大企業を異議申し立てや抗議から守るため、労働組合の事務所が急襲捜索を受け、コンピューターが押収され、設備が打ち壊され、リーダーが逮捕、迫害されている。そしてこうしたことは、まさに石油の豊富なイラク南部で起きている。
北部のクルド地域では、自治政府が管轄区域外の土地に関して契約を承認している。こうした契約で自治政府は、石油プロジェクトの権益を25%まで、お気に入りの私企業に移転できるようになる。1日にタンカー数百隻分の燃料が国境を越えて密輸されている。
クルド地域では、少なくともこのようなやり方は意図的にとられている。地域を支配する2つの氏族、バルザニ家とタラバニ家は、指揮下のペシャメルガ民兵が地域を支配しているために、自分たちが何でも思い通りにできることを知っているのだ。これに対してマリキ首相のイラク連邦政府は、何に対してもほとんど支配力がない。その結果、クルド地域以外のイラクでは、石油産業はほとんどまったく監視も規制もなく、早い者勝ちの野放し状態だ。
2つのイラクのどちらで操業したいかは石油企業によって分かれる。BP、シェル両社は、黒い黄金めがけてイラク南部の超巨大油田に向かうことを選んだ。エクソン社は両方の選択肢に投資し、リスクをヘッジしている。今夏、シェブロン社とフランスの石油企業トタル社は、油田の規模こそイラク南部より小さいが、条件がよりよく、治安もいくらかましな、クルドのほうを選んだ。
イラク政府の無能は、石油産業に限ったことではないというのを忘れてはいけない。ありとあらゆる機関がことごとく停滞している。イラクでは依然として一日平均5時間しか電気が来ず、50℃を超える暑さの中では何かにつけて一触即発の情勢につながる。国内の2本の大河、5000年前には文明の揺籃の地を潤したチグリス、ユーフラテス川は、現在は枯渇しつつある。これは、上流にダムを建設するトルコに歯止めをかけるような有効な域内外交を打ち出せない、イラク政府の無策によるところが大きい。
2010年の選挙の後、イラクのトップ政治家たちは、どうやって政権を作るかで合意することすらできず、最高裁に尻を叩かれる始末だった。こうした無能の数々、猛威を振るう腐敗、大規模な弾圧、宗派主義の復活はすべて、占領時代の米国の決定に根源がある。悲劇的なことに、こうした抜きがたい害悪は、最近の車両爆破その他による流血のテロとなって現れている。
米政府がもつ石油への強い欲望
侵攻前も侵攻の頃も、ブッシュ政権はイラクの石油に言及することはほとんどなく、ただ恭しくイラクの「国家財産」だと言うだけだった。戦争をする理由については、ブッシュ政権は、世界の石油埋蔵量の十分の一がイラクにあることなどほとんど念頭になかったと主張していた。だが、私は近著で私の手に入った文書を公開したが、「機密/外国人閲覧禁止」という印が付けられたその文書によって、ネオコンの領袖ダグラス・フェイスのエネルギー・インフラ計画グループ(EIPG)が国防総省内部で温めた、戦争前の石油戦略が初めて明らかにされた。
イラク侵攻の4カ月前の2002年11月、EIPGは新たな構想を練り上げた。そこでは、米国のいかなる占領当局も、戦争によるイラクの石油インフラへの損害の補修を行わないことが提案されていた。補修をすれば「民間部門の参画に水を差しかねない」からだという。言い換えれば、石油メジャー参入の余地ができるよう、イラクの自前の石油産業は一掃されるべきと示唆したわけだ。
これでは石油市場が動揺しかねないとブッシュ政権が懸念すると、EIPGは、新たな戦略をひねり出し、当初の補修をハリバートンの子会社KBRが行うとした。その後、米占領当局の承認の下、多国籍企業各社との長期契約が結ばれる。EIPGの文書は国際法などお構いなしに、こうした方法が「[石油]価格に長期的な下落圧力」をかけ、「イラクとOPECとの将来的関係に関する問いかけ」を迫るだろうと上機嫌で記している。
同時にEIPGは、この政策が「イラクによる自国の石油開発政策に関する将来的決定を縛るものではない」と表明するよう米政府に勧告していた。以後数年間ブッシュ政権と占領当局が採用するアプローチが、このように文書になっていたのだ。すなわち、国民には嘘をつきながら、イラクを石油メジャーに明け渡す計画を陰で練る、というわけだ。
しかしこの計画に小さな狂いが生じることになった。国際法廷で持ちこたえられず違法を宣告されることになるのを恐れた石油企業が米国の認めた契約を拒んだのだ。企業側は、まずイラクに選挙で選ばれた、暫定でない政府が発足し、しかる後に同じ結果に到達することを望んだ。そうなると問題は、形式的に責任者となるイラク政府から、必要な成果を引き出すためにどうすべきかということだ。その答えは、親米政権を据えてイラクの石油産業を破壊すべし、となる。
2003年7月、米国の占領当局は、イラク統治評議会を発足させた。政府に準ずる組織で、トップに立つのは、それまで数十年間イラク国外にいた親米派のイラク人亡命者たちだ。評議会は、爆弾を防ぐコンクリート壁と機関銃つき監視塔でイラク民衆から隔離されたバグダッドの一地区、いわゆるグリーンゾーンに置かれた。政治家たちはそこで、一般の国民の苦しみなど忘れ去って意にも介さず、豪勢な生活を送った。
侵攻後最初の石油相イブラヒム・バフル・アル=ウルムは、国内育ちの石油技術への侮蔑を隠さなかった。アル=ウルムは、1970年代の国有化に続いてイラク石油産業を築き上げ、戦争と制裁の期間を乗り切って持続させてきた技術者や管理職をすぐさま解雇した。首にした技術者・管理職の代わりに、気心の知れた人間や同僚党員を任命した。元ピザ店主が任命されたのがいい例だ。
これが石油産業にもたらしたダメージは、ミサイルや戦車によるいかなる破壊をも凌ぐものだった。結果としてイラクは、――米政府が望んだとおりに――外国企業の専門技術に頼らざるを得なくなった。さらに、占領を統括する連合国暫定当局(CPA)は、66億ドルのイラクの資金を失くしただけでなく、腐敗など懸念するには及ばないと手回しよくほのめかした。2003年12月、CPAの政策文書の勧告によれば、イラクはアゼルバイジャンに倣うべしとされている。アゼルバイジャンでは、すさまじい腐敗が蔓延する(「ガバナンスという点ではいささか見劣りする」)中、政府がきわめて実入りのいい取引を大盤振る舞いして多国籍企業を呼び込んでいた。
それから何年も経った今日、腐敗が至るところにはびこり、多国籍企業は、監視されることもなく操業を続けている。イラク石油省を運営するのが、ピザ店主と変わらない人間だからだ。
マリキ首相の下でイラクに最初の公式政府が発足したのは2006年5月だった。それに先立つ数カ月間、米英両国政府は、首相候補が最優先事項を肝に銘じるよう万策怠りなかった。最優先事項とは、七〇年代に国を追い出されていた外国多国籍企業の復帰・石油部門運営を合法化する法律を成立させることだ。
法律は数週間のうちに起草され、律儀に数日のうちに米国官僚に提示され、まもなく石油多国籍企業にも示された。しかし、イラク議会の議員が文書を目にしたのは七カ月も経ってからだった。
石油メジャーの勝利はいつまでもつか
問題は、この法律を議会で成立させることが、米政府やイラクにいる米官僚の予想よりはるかに困難だったことだ。2007年1月、しびれをきらしたブッシュ大統領は、3万人の米国部隊のイラクへの「増派」を表明した。その頃にはイラクは血なまぐさい内戦に陥っていた。従順なジャーナリストたちは、同胞相争うイラクに平和をもたらすという、デイビッド・ぺトレイアス将軍による賭けのような話を唯々諾々と受け入れた。
実のところ、こうした部隊が担っていた戦略には、それほど利他的とは言いがたい目的があった。第一に、米国寄りの諸派――イラクの政治家の中でもっとも宗派的で腐敗した面々(従って、米国の外交政策特有の逆転現象で、しばしば「穏健派」とされる人びと)――の間で新たな政治的取引を仲介すること。第二に、彼らに圧力をかけて、米政府が設定した政治目標、いわゆる「ベンチマーク」を達成させること――「ベンチマーク」と言えば、ブッシュ大統領が2週に1度マリキと行うビデオ会談でも、駐イラク米大使のほぼ毎日の会合でも、また政権の幹部官僚の頻繁な訪問でも、取り上げられていたのは石油法案の成立だけだった。
この問題に関しては、この頃には次第にイラク戦争への反対を強めてはいたものの、やはり石油メジャー寄りの民主党は、共和党政権に協力の手を差し伸べた。民主党が多数派となった議会は、戦争を終わらせることができず、特別会計支出予算案を通したが、この予算案では、もし石油法案が成立しない場合、イラクへの復興基金を削減することになっていた。将軍たちは、石油法案が通らなければ、マリキ首相を支持することは難しくなりかねないと警告したが、首相が重々承知していたようにこれは首相の座を失うという意味だった。さらに圧力を強めるために、米国は、法案成立に2007年9月という期限を設け、首相の座にとどまりたければ期限を守れと迫った。
ブッシュとその一味にとって、歯車が本当に大きく狂い始めたのは、そのときだった。2006年12月、
私はある会合に出席したが、そこでイラクの労働組合のリーダーが石油法案と戦うことを決定した。リーダーの一人は、みなの思いをこう言い表した。「われわれを中世に引き戻す盗人たちはご免被る」。組織化が始まった。パンフレットを印刷し、公開の会合や会議を開催し、抗議行動を計画した。運動への支持は高まっていった。
ほとんどのイラク人は、自国の埋蔵石油が公的部門に属すものであり、外国のエネルギー企業ではなく自分たちに恩恵をもたらすように開発されるべきだと強く感じている。このため、話はすぐに広まり、それとともに人びとの怒りも広がった。イラクの石油専門家とさまざまな市民団体が、法案を非難した。説教者も金曜日の説教で法案に異議を唱えた。バグダッドを初め各地でデモが行われ、米政府が圧力を強めるに連れ、イラク議会の中に、人びとの間で関心が高まる一方のこの主張に同調することを政治的チャンスと見る議員が出てきた。議会内の親米派の中にさえ、法案に賛成するのは政治的自殺行為だと米大使館で外交官に漏らす者たちもいた。
9月の期限が来たときには、議会の過半数が法案に反対であり――労働組合にとって素晴らしい勝利だった――法案は成立しなかった。今日もまだ成立していない。
ブッシュ政権が石油法案の成立に向けて政治的にどれほどの精力を注ぎ込んだかを考えれば、法案が成立しなかったことは、イラク人に米国の力の限界を垣間見せ、このとき以来、米政府の影響力は衰え始めた。
2009年、石油収入が喉から手が出るほどほしいマリキ政権が、石油法が存在してもいないのに、石油企業に契約を認め始め、事態は再び変わってしまった。しかしその結果、石油メジャーの勝利は一時的なものになる可能性が高い。現在の契約は違法であり、バグダッドに契約を支持する政府が存在する間しか効力がない。
契約が交わされた後、労働組合に対する政府の弾圧が強まったのはなぜか、これで説明がつくだろう。現在イラクは、多くの面で独裁体制(および同胞相食む暴力とおそらく新たな宗派対立)へと戻っていく兆候を示している。
しかしイラクにはもう一つの可能性がある。アラブの春より何年も前に、イラクの市民社会が組織化によって何を達成できるか、私は目にした。世界で唯一の超大国が主要目的を達成するのを阻み、イラクをもっと好ましい道へと舵取りしたのだ。
2003年以来何度も、イラク人はイラクを民主的な方向へ動かしてきた。その年のうちに労働組合を結成し、2004年にシーア派・スンニ派の結びつきを築き、2007年と2008年には反宗派主義の政治家を擁立し、2009年に彼らに投票した。悲しいことに、その度ごとに米政府は、イラクを宗派主義へと押し戻した。そうした雰囲気の中では親米派が優勢になれるのだ。現在、主流メディアの評論家たちは、最近イラクで暴力がエスカレートしているのは米軍が撤退したからだと非難するのが常だが、本当の理由は、米軍の撤退があまりにも遅すぎたからだというほうが正確だろう。
米軍が撤退し基地が閉鎖された今日[*]、米政府の政治的影響力の多くは消滅した。イラクが独裁制、宗派主義へと向かうのか、それとも民主制へと向かうのかは、まだ判然としないが、もしイラク人が再び民主的な未来を築き始めるなら、それを妨げる米国はもはやイラクにはいない。そして、もし新しい政治が本当に生まれてくるとすれば、石油メジャーは、結局のところ、「任務は完了」していなかったと悟ることになるかもしれない。
[*]ただし、100人あまりの米軍人が駐留してイラク軍への関与を続ける他、武器の供与も継続する。また要塞と化した米大使館の警備に5000人を超える民間軍事企業要員も配置されるという。
原文
Mission Accomplished for Big Oil?
How an American Disaster Paved the Way for Big Oil’s Rise — and Possible Fall — in Iraq
By Greg Muttitt
関連速報、書籍も合わせてご覧ください。
○ファッルージャでの劣化ウランの被害については 速報955 ドナより ピンクの服を身にまとった女性 をはじめ、ドナ・マルハーンの報告シリーズがあります。TUPサイト右欄「配信記事の分類」の「ドナからのメッセージ」からお入りください。
○米軍帰還兵による戦争と米軍の実態についての証言シリーズは、TUPサイト右欄「配信記事の分類」の「冬の兵士」からお入りください。証言集『冬の兵士――イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実』(岩波書店)もぜひご覧ください。