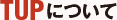注[*]: 著者の名前の表記につき、米語の発音的には、「アナン・ゴーパル」のように聞こえることが多いのではと思われます。
ゴパルの当記事にて、中心的語り手となるのが、農村に住むパシュトゥーン人の女性シャキーラです。40代前半で、20歳の長女を筆頭に8人の子がいます。彼女の夫はケシの仲買人[†]です。
シャキーラの村は、パシュトゥーン人の地方にあります。パシュトゥーン人は、アフガニスタンの人口4000万人の中で42%を占める最大部族です(人口分布のソース)。現在アフガニスタン政権についているターリバーンは、基本的にパシュトゥーン人、それも地方出身者が中心となっているとされます。ちなみに、2001年に(米国の侵攻により)ターリバーンが政権から追われた後の初代大統領カルザイおよびこの8月にカーブルを退去した2代目大統領ガニもパシュトゥーン人です。
現在までアフガニスタンは世界最貧国の一つです。しかし、女性が制度上そして慣習的に抑圧されているアフガニスタンの農村にあっても、シャキーラは男性に対する批判的姿勢やユーモアを忘れていません。
90年代、[当時実権を握っていた]ターリバーンが村に電気をひこうと提案した。村の長老の男たちは、当初、それを拒否した。黒魔術だと恐れたからだ。「もちろん私たち女は、電気は何も問題ないと知っていましたけどね」とシャキーラは笑う。
40代のシャキーラは、生まれてこの方、平和な世界をほとんど見たことがない様子です。母から昔の平和だった時代の話を聞いたことがある程度です。アフガニスタンでは、過去40年以上、多かれ少なかれ内戦が続いていたからです。冷戦中は当時の両巨頭である米ソ双方が軍事的に介入していて恒常的に内戦状態で、冷戦終結後も2001年に米国が侵攻して当時のターリバーン政権を転覆させて駐留し始めた後、反政府ゲリラがずっと活動しています。
シャキーラはこの8月、村が戦場になるとの警告をターリバーンから受けて自宅を離れることを余儀なくされました。ゴパルが話を訊いたのは、シャキーラが一時身を寄せていた先でした。シャキーラの家は、撤退直前の米軍に爆破されて半壊しています。
シャキーラがゴパルに会った時の様子が象徴的です。
シャキーラははにかんで言った。 「外国人に会うのなんて生まれて初めてです——銃を持っていない外国人という意味ですけど」
筆者注[†]:
アフガニスタンは、過去長らくケシの世界最大の産地であり麻薬の最大の輸出国。2019年統計では、ケシの作付面積にして、アフガニスタン一国で世界の全シェアの約6割を占めている。実は、2000年7月、当時のアフガニスタンの大半を支配していたターリバーンは(自分たちの支配が及ぶ範囲)全土でケシ栽培を全面禁止し、その結果、輸出量が9割減った、という実績がある。しかし、2001年の米国侵攻以来、ケシの栽培と麻薬取引はすぐ復活し、アフガニスタンは間髪入れず世界第1位の座に返り咲いた。筆者は実情を知らないものの、アフガニスタンの地方の国民にとってケシ栽培および流通の仕事はめずらしくないことと推測する。ゴパルによれば、シャキーラの村の若い男の多くがその関係の仕事に従事していると記述している——実際、村のあるヘルマンド地方はケシ栽培で有名らしいことと一致する(参考: 2007年のガーディアン紙記事)。ケシは農民そして仲買人にとっては現金収入源であり、為政者にとっては間接的でも税収だろう。
パシュトゥーン人地方での女性の生活
シャキーラの村では、女の子は初潮とともに大人の女となって基本的に屋内で過ごし、一人で表に出られるようになるのは、孫のいるような歳になってからです。シャキーラの場合、11歳で外出することがなくなり、それ以降、彼女の世界は基本的に家の中の三部屋と中庭に限られ、裁縫、タンドーリ窯での調理、そして牛の乳を絞るのが仕事になった、とゴパルは記します。
もし外出が不可避の場合は、ブルカ(顔を含めて体全体を覆うアフガニスタンの民族衣装でベールの繊維の網目を通して外を見る)をかぶることが慣習、事実上の義務です。身内以外の男性に会うこともありません。家の扉を誰かが叩いたときも、応対するのは家族の中の男の役割です。
シャキーラの夫は麻薬中毒でもあり、シャキーラは離婚を考えることもないわけではない、と言います。しかし、離婚しては生活が成り立たないため、離婚は非現実的選択として断念することになります。
女性は教育も禁じられています。
実は、シャキーラがごく幼なかった1980年頃には、クーデターで成立した社会主義政権(アフガニスタン民主共和国)が、ソビエト連邦(ソ連)の軍事介入に支えられながら急速な改革を進めようとした時期もありました。それには、農地改革と女児の学校教育も含まれます。
シャキーラの村でも、政府により、女児へ読み書きを教える政策が施行されました。ゴパルは書きます。
村人の話では、外部の人間が女性の権利を村に無理矢理持ち込むことで、同村の伝統的生活様式が一夜にして破壊された、ということになる。
そして、
政府が銃口でもって女児を学校に通学させ始めた時、ムジャーヒディーン[‡]を名乗る武装勢力をリーダーとする抵抗運動が蜂起した。その最初の作戦で、村のすべての学校教師が誘拐され、首をかき切られた。学校教師の多くは、女児の教育に賛同していた。その翌日、政府は村の長老と地主を、ムジャーヒディーンを支援した疑いで逮捕した。以後、彼ら長老の姿を見たものはいない。
ということになりました。
そのような事情なので、シャキーラは文字を教わったことはありません。シャキーラの家族で学校に通ったのは祖父が最後です。これはつまり、男児であっても教育機会がなかったことを意味し、ましてや女児の教育なんて、ということです。
この8月にアフガニスタン首都を制圧したターリバーン政権は、女性の権利を抑圧する政策を打ち出して、現在、国際的に強い批判にさらされています。事態は流動的ながら、本稿執筆段階において、たとえば女子の教育を禁じ、女性が男性を伴わずに外出することを禁じ、女性が外出する際にはブルカの着用を義務付けています。男女同権が原則とされている社会から見れば、それは極端な前近代的制度に見えます。
しかし、アフガニスタンの地方、少なくとも(最大部族である)パシュトゥーン人の地方を見る限り、ターリバーンだけが突出して抑圧的ではないことが見てとれます。教育や外出の禁止もそうですし、ブルカの着用は、そもそもの文化として受け入れている女性が少なくとも地方には少なくないと聞きます。たとえば、春日が地方の(パシュトゥーンではない?)部族の村を2001年以前のある時に訪ねて、村人の女性と話をした時も、女性たちはターリバーンは嫌悪する一方でブルカの着用は当然とみなしていた、と報告しています。
ゴパルが話したアフガン女性たちに共通していたのは、銃を突き付けて権利をもたらすことは決してできない、アフガニスタン社会自らが女性の状況を改善しなくてはいけない、という考えでした。外出禁止・教育禁止はアフガニスタン社会の慣習にすぎず、イスラームそのものは権利を求める闘いを支えるための力強い文化資源となると考える人々もいる、とゴパルは報告しています。
筆者注[‡]:
1980年代、ソ連の支援を受けた社会主義政府に対抗する反政府ゲリラが各地で組織され、国内のみならず国外からもイスラームを防衛する戦いという名目のもと、多くの志願兵が参戦し、ムジャーヒディーンと呼ばれる。ちなみに、(アル=カーイダの)ウサーマ・ビン・ラーディンもその一人(一勢力)。それら反政府ゲリラに対して、外国が資金や武器援助を行ってもいた。その中心の一つが、米国によるサイクロン作戦。当時のアフガニスタン政府にとってはムジャーヒディーンは反政府ゲリラであり、一方アメリカではムジャーヒディーンはしばしば「自由のための戦士」(freedom fighter)と呼ばれた。この四半世紀のアメリカでは、政府および主流マスコミの多くにおいて、その同じムジャーヒディーンが「テロリスト」と呼ばれている。
2001年の米軍侵攻以前の生活
ソ連が後ろ盾となった社会主義政権の時代、政府の女性解放政策により大学が一気に女性に開かれ女性の国会議員が何人も誕生した一方、シャキーラの村は、(複数の強力な軍閥が反政府活動を行っていたこともあり)たびたびソ連軍の攻撃にさらされました。シャキーラの祖父も避難中にソ連軍に捕らえられ、処刑された1人です。
社会主義政権が権力を失って以降は、シャキーラの村のある地方を事実上治めていたのは、土地の有力者(裕福な商人)でありムジャーヒディーン司令官となったアミル・ダド、そしてそれに対抗する第93部隊と呼ばれる武装組織でした。それぞれが住民に対し別々に課税し、時には狼藉を働き、村人からはひどく嫌われていた、とゴパルは説明します。
そして90年代のある時、当時勢力を拡大していたターリバーンがやってきて、同地方からダドと第93部隊の両方を追い出しました。いずれも国外に逃亡したのです。その時、ダドの宗教裁判所の恣意的な判決により処刑を待っていたシャキーラのおじ夫婦も解放されました。
ゴパルがシャキーラや他の村人女性に当時のターリバーン統治下がどうだったかと尋ねると、
女性たちは、普遍的な原理原則に照らして批評することには乗り気でなく、それ以前と比べてどうだったかを語るだけだった。「ターリバーンは相対的に厳しくなかった」と隣村の女性は言う。あるいは別の女性は「ターリバーンは私たちに尊厳をもって応対してましたね」と言う。端的には、ターリバーン統治下の生活はそれ以前のダドの下での生活と全く同じだった–見知らぬ男が夜に玄関の扉を蹴り破って入ってきたり、検問所で殺されたり、ということがなくなったことを除けば、と。
つまり、シャキーラの村は15年ぶりに平和を取り戻したのです。シャキーラが結婚したのもその頃です。とはいえ、強制的な徴兵を行うターリバーンを、住民がはすぐに恐れるようになりました。ターリバーンはその後、アフガニスタンの大部分を掌握します。
補足すると、アフガニスタン全域を俯瞰すれば、アフガニスタンの内戦は1990年代を通じて継続していて、特にターリバーンとそれ以外の勢力との内戦は全土に及びました。中でも、北部同盟との抗争は(9-11の米国同時多発テロが起こった)2001年までずっと続きました。その内戦中、ターリバーンによる1998年のハザラ人大虐殺では市民の犠牲も大量に出したことで有名です(Wikipedia英語記事)。アフガニスタンの中では、シャキーラの村のように一時的に(一定の)平和を取り戻した地方もあれば、悲惨な内戦が継続した地方もあった、とするのが公平な見方でしょう。
米軍の占領
米軍は、2001年にアフガニスタンに侵攻し、ターリバーンを政権から追い落としました。
この頃までには、シャキーラの夫は、職を失い、パキスタンに出稼ぎに行っていたのですが、その夫も帰ってきました。ちなみに、シャキーラの夫が職を失った理由は単純で、2000年のターリバーンによる麻薬禁止令、そして時期を同じくした2年越しの大旱魃のゆえ、とゴパルは解説します。
実際、ターリバーンによる麻薬禁止令は、前記注釈に述べたように、麻薬規制という意味で世界史に残る大成功例でした。しかし、国の対外経済の無視できない部分が麻薬取引によっていた状況では、直接の影響を受けた国民が少なくなかったことは容易に想像できますし、実際そう伝えられます。
ターリバーンが追われて麻薬生産と取引が一気に回復し、ケシ畑に一斉に花咲く頃に夫が帰ってくるという状況は、絵画的ながら世の矛盾を感じてなりません。
ちなみに、麻薬禁止令とアフガニスタンの大旱魃は当然ながら当時からよく知られている事実でした。後者については、日本語では、(故中村哲さんの)ペシャワール会の関連著作や『カブール・ノート』(山本芳幸著(当時の国連難民高等弁務官カブール事務所長))などにも詳しく、世界的にはイランの映画監督モフセン・マフマルバフ著の『アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない、恥辱のあまり崩れ落ちたのだ』(邦訳あり)は有名です。前者に関連して、『「新しい戦争」とメディア』(内藤正典編著)に当時の状況が生々しく描写されています。曰く「『禁止令により生アヘンの取引価格は〜2倍に高騰。このため禁止令は、取引価格を高騰させるのが目的だったのではないかとの疑念も出ている』(毎日新聞)」と報道される有様で、国連安保理はアフガニスタンへの制裁強化決議を、反対を受けながらも可決しました(S/RES/1333 (2000))。生産量を9割落として価格が2倍になったならばすさまじい大損なのは小学生でもすぐわかる話で、これは言いがかりもいいところでしょう。資料から、ターリバーンによるケシ栽培禁止令は、西側諸国の歓心を買ってアフガニスタンの農家が代替作物栽培に切替えるための国際援助を期待したものだったことが窺われますが、禁止令がしかれるも代替援助がなかったならば、関連産業の人々(農民や仲買人)には苛酷な状況だったと推察できます。
さて、戻ってきたのは、シャキーラの夫だけではありません。ゴパルの記述を読むと背筋が寒くなります。
ターリバーンが政権から追い落とされた後、シャキーラの住む地方に戻ってきたのが、米軍特殊部隊と友誼を結んだダドとその一族でした。ダドは
同ヘルマンド地方の情報省長官になり、兄弟の1人がサンギン県知事、別の1人がサンギン県警察の長になった。
結果、シャキーラの村は内戦時の恐怖政治に戻りました。一例として、ダドの民兵が2人の若い男に税を払うか民兵に加わるかのどちらかを選ばせようとして、男たちが断ると2人を惨殺し、遺体を木に吊るして去っていったこともありました。なお、ダドは、公的地位にあるとともに民兵も所有していて、これは民兵の仕業です。
それだけでなく、米国は、その地方でダドと並んで悪名高かった武装組織第93部隊も復活させました。第93部隊が幹線に関所を敷いて内戦時のように通行料を取り、狼藉を始めたため、シャキーラの夫の仕事も危険で困難になったといいます。
とはいえ、経済はボロボロで、いかに絞り上げても、国民はそれほど金を持っていません。だから、そんな折、
最も金になるのは、米軍提供の[ターリバーンの残党狩りの]懸賞金だった。
しかし問題は、事実上、活動しているターリバーンはほとんどいなかったことだった。
結果、起こったのは、全然関係ない人、あるいは自分が気に入らない人をターリバーンとして米軍に通報することでした。その端的な例として、
2003年2月、土地の権力争いをしていた第93部隊は、当地の交通局の長官(ハッジ・ビスミッラー)、すなわち通行料徴収の責任者、をテロリストとして米軍に通報した。結果、ビスミッラーは、米国のグアンタナモ収容所に送られた。長官がいなくなると、第93部隊は当地の通行料収入を独占した。
補足すると、グアンタナモ収容所は、米西戦争(1898年)以来、米国が占領しているキューバ南東部のグアンタナモ米軍基地内にあります(米国がキューバから租借していることになっているが、1959年のキューバ革命以降、キューバ政府は租借料を拒否し、返還を求めている)。近年は、アフガニスタンやイラクで米軍が捕らえた「犯罪被疑者(テロリスト容疑者)」をここに収容しています。米国内にないため、米国法の管轄外として運用されていて、人権侵害の収容施設として国際的に悪名高いものです。何年も収容され、まともな取り調べもないまま、最終的には単に無実放免される例も数多く報告されています。つまり、恣意的、あるいはごく適当に被疑者が選ばれている様子で、その点でも批判が大きいものです。このゴパルの記事でも、理由と呼べる理由なくグアンタナモ収容所に送られた例がいくつも紹介されています。たとえば、名前がたまたまターリバーンの幹部と一致していたから、という例もあります。念のため、ゴパルが報告している例は、公文書などできっちりその事実の裏を取っている様子が窺われます。
ダドはさらに大胆だったとゴパルは記録します。2003年3月、サンギン県知事(前述のダドの兄弟)との事務会議にやってきた米軍の車列が帰る時に攻撃され、米軍軍曹2人が殺される事件がありました。ダド軍は、ある男(ムッラー・ジャリル)を犯人に仕立て上げ、米軍はその男をグアンタナモ収容所に送りました。彼には、ターリバーン軍に徴兵されていた履歴がありました。しかし、ターリバーンは統治時、徴兵制をしいていた以上、徴兵がターリバーンの一員であることを意味しないことは明白でしょう。そして実際、ゴパルが入手したグアンタナモ関連の機密文書によれば、米軍の担当者は、その男が犯人とは何の関係もなく、ダド軍が「その攻撃に関与した」ことを隠蔽するために使われただけであることを知っていました。ゴパル自身、現地で、ダドの元部下から、この殺人事件へのダド軍の関与の証言を得ています。
ゴパルは続けます。
この件は、ダドと米軍特殊部隊との関係に悪影響を及ぼすことはなかった。米軍は、「対テロリスト」作戦においてダドは極めて重要で、何者にも替えがたい、と考えていた。米軍とダドとは今やともにテロリストを探索するようになった。テロリスト容疑者を求めてシャキーラの村にもやってきた。兵士らはシャキーラの家には長く滞在したわけではなかったものの、ライフルの銃口はシャキーラの脳裏から長く消えることがなかった。
シャキーラの友人や隣人は当時、復讐を恐れて行動を起こすことはなかったそうです。しかしそのうち、ダドの狼藉は国連にも知られることになりました。国連はダドの解任を訴えましたが、米国はその訴えを繰り返し退けた、とゴパルは記します。米軍海兵隊の取次を務めた人物の言によれば、ダドは
ジェファーソンのような理想とはほど遠いのは確かながら、彼の正義を追求するやり方は粗野であっても「パシュトゥーン人の抵抗勢力を抑えるために有効であることは今までの事実が証明している」
ということだったのです。
ダドと双璧の第93部隊も酷いものでした。ゴパルは、第93部隊に逮捕されたある男(アブドゥルワーヒド)が、部隊によってひどく殴打され、米軍に輸送された後、檻の中で死んだ例をあげています。そしてゴパルが入手した、この件に関する機密解除された公文書によれば、第93部隊がこのような所業を日常的に行っていたことを、米軍はよく知っていたことがわかります。
にも拘らず、米国は第93部隊を支持し続けた。これは、疑いなく人権侵害している組織に対して、職位にある米国人が支持することを禁じているリーヒー法に明確に抵触する行為だ。
2004年には、国際連合が、政府側民間軍事組織の非武装化に着手しました。しかし、ゴパルの記事では、(1例ながら)その有名無実な様子が採り上げられています。いわく、
第93部隊の司令官はその計画を聞くや、部隊の3分の1を「民間警備会社」と看板を取り替えて米国と契約することで、武装を保ったまま安泰とさせた。別の3分の1はテキサスの会社と道路工事警備の契約を結ぶことで武装を保った(カルザイ政権がその民間警備員を解任して警察にその任を与えた時、第93部隊の長は警備に就く警官の殺害計画を立てて15人を殺害し、その結果、契約を回復した)。残りの3分の1は、自分たちのかつての同僚からのゆすりの危機を感じて武器を持ってターリバーンに加わった。
そして、米軍と同盟軍の軍事行動による国民の犠牲も止まることがありません。前世紀からの変化として、軍事技術が進歩するにつれ、米軍と同盟軍によるドローン(リモコンの無人爆撃機)を使った攻撃も展開されるようになりました。米オバマ政権でドローンの軍事使用が急増したことは有名な事実でしょう。ゴパルは、アフガニスタン現地での様子を報告します。
[シャキーラには]ムハンマドという名の15歳の従兄弟がいた。ムハンマドはドローン攻撃によって殺された。友人と村内をオートバイで移動していたときに攻撃されたのだ。 [……中略……] 別のいとこ、ムハンマド・ワリも殺された。村民は、(国際)同盟軍により、軍事作戦中の3日間外出しないよう言い渡されていた。しかし、2日目までには[屋内の]飲料水が底をついてしまったため、ワリは外に出ざるを得なかった。そして撃たれた。
ゴパルの記事では、シャキーラが失ったその他の何人もの親戚について述べられています。
ゴパルが、インタビューした村人からの情報、アフガニスタンの公式死亡証明書などの情報を総合した結果、地元民が言うところの「アメリカ戦争」の期間、一家族につき平均して10〜12人の(非武装)市民の命が失われた(殺された)計算になる、と報告しています。
ここでいう「家族」とは、もちろん現代日本の核家族ではなく、親戚一同を意味しているのでしょう。しかしそれにしてもこの数は想像を絶します。太平洋戦争直後の日本でさえ、直接的大空襲を受けた都市部と広島、長崎、沖縄を除けば、ここまでの数字ではなかったことでしょう。
無論、ターリバーンとの和平交渉もなかったわけではありません。たとえば、2010年、シャキーラの地方では、
ターリバーン司令官は英軍と交渉し、地元民を支援するという条件で和平交渉が進んでいた。そして交渉も大詰めのある日、最終的な条項をまとめるためにターリバーン高官が集会を持った時、(英軍とは独立に行動していた)米軍特殊部隊がその集会を空襲し、和平交渉の責任者であった高官を殺害した。
これでは信頼醸成が行われることはとても期待できません。
シャキーラの村の一帯は、米海兵隊が2014年に撤退し、その3年後にはアフガニスタン軍(アフガン軍)も撤退、ターリバーンの支配下となりました。その際、
米国は、アフガニスタン政府軍も一緒に飛行機で輸送し、地方の多くの政府庁舎を完全破壊して去っていった。NATO(北大西洋条約機構)の公式文書でも、「瓦礫の山」だけを残し、と記されている。
誰が政権を取るにせよ、現地のインフラは必須です。こうして現地のインフラを破壊して去っていくのは、現地の復興目的とは対極です。結局、最大の被害者は住民であり国民になります。インフラは国民が再建しないとならないわけですから。
このような中で、非武装一般市民の犠牲も相次ぐことになります。シャキーラの村も例外ではありません。2019年、米国がカタールのドーハでターリバーン高官と和平交渉を持つかたわら、村はアフガン政府軍と米軍の共同作戦の標的になり、この戦争史上、村としては最悪の数の犠牲者を出した、とゴパルは記録します。村人が村から避難する中、アフメド・ヌール・ムハンマド(Ahmed Noor Mohammad)と家族は双子の息子が病気だったために家に留まっていたところ、米軍の爆撃が2発家に直撃して双子や父親をはじめ多くの家族が犠牲になりました。うち8人は子供でした。翌日に行われた葬儀は再び空襲を受け、6人が殺されました。
他にも同様の虐殺が相次ぎました。
その空襲の後、ムハンマドの兄(弟)は、カンダハールまで旅して、国連およびアフガニスタン政府に大虐殺について報告した。その後、正義が回復するようなことは何も起こる気配がないことを見た彼はターリバーンに加わった。
結局、
現地住民にとって、同盟軍とそのアフガニスタン国内シンパの統治下の生活は、災厄以外での何物でもなかった。畑の真ん中で茶を飲むことや姉妹の結婚式に出席することさえも、命の危険を冒さずにはできない博打だった。比較したら、ターリバーンが申し出たのは単純な交換条件だった。
「我々に従え。そうしたら生かしておいてやるから。」
筆者注:
ここで言う「現地住民」とは、アフガニスタンの地方(農村)、かつパシュトゥーン人の地域と解釈すべきだろう。ゴパルも後述するように都市部の状況は全く異なった。また、(人口的にアフガニスタンの最大民族である)パシュトゥーン人以外の地域では別の見方もあったかも知れないことは留意しておくべきだろう。国連報告書では、2010年のアフガニスタンの非武装市民の死の中で、反政府組織と関連付けられるものが75パーセント、政府系組織は16パーセント、と推定している。この統計には不確定性や偏りが相当程度あることだろうが、ターリバーンを主とするだろうアフガニスタン反政府組織が非難されて然るべきであることは言を俟たない。
ゴパルは、そのような大虐殺の役には従事せずにすんだアフガン軍ヘリコプターのパイロットの1人に、電話でインタビューしたことがあります。パイロット曰く
「仲間のパイロットたちにどうして殺したんだ、と訊いたんだ。すると『攻撃対象が非武装市民だということは皆知っていたよ。でも、(アフガン軍)司令官は、皆殺しにしろ、と命令をくだしたんだ』」
「皆殺しにしろ(kill them all)」とは、アクション映画で悪役が言う台詞として聞くことはあります。しかし、現実世界で人間が発する言葉としては耳を疑います。それも、同じアフガニスタン人の間で……。そして、そのアフガン軍は同盟軍から多大な支援を受けていることも念のため追記しておきます。
結局、ターリバーンは、「敵側が惨憺たる過ちを犯したために、いわば不戦勝をしたにすぎないように見える」と、ゴパルは書きます。シャキーラの村のあるような地方部では、軍閥、外国軍、アフガン軍による市民殺戮が絶え間なく続いたために、住民はいやおうなしにターリバーンに引き寄せられたということです。2011年頃までには、ただ身を守るためあるいは復讐のために息子がターリバーンに加わったという家族が増え、シャキーラの地方ではターリバーンは90年代よりもむしろ根を張っていたと、ゴパルは報じています。
米軍の占領は何だったか
ゴパルは言います。
ある意味では、こうした戦闘は、原理主義の抵抗勢力が国際的承認を得た政府に対して戦っているとも言える。またある意味では、貧乏のどん底に突き落とされた村民がかつての苛烈な領主に復讐しているとも言える。あるいは、ながらくくすぶっていた部族間抗争が同時多発的に表面化した、とも。あるいは、麻薬カルテルがライバル会社に対して攻撃を仕掛けている、とも。おそらくこれらすべてが同時に正しい表現といえるだろう。
ゴパルは続けます。
一つ確かなことは、米国は、こういった諍いを解決し、みなを包含する長期的な組織を作ろうという気はなかったことだ。米国がしたことは、内戦に干渉し、ただ一方に加担しただけだった。結果的に、米国が作り出したのは、かつてソ連が作り出したのと同様、一国内に二つのアフガニスタンだった。一つは永続的な泥沼紛争の国であり、もう一つは繁栄し希望を持つ国だった。
ここで「繁栄し希望を持つ国」とはアフガニスタンのカーブルを中心とした都市部の話です。
だからこそ、ゴパルの言葉を借りれば「[特に]都市部の女性がこの期間に得た–そして今や失った–ものを、戒律厳しいヘルマンド地方農村部の生活と比べてみれば、そのギャップは想像を絶する」。なにしろ「アフガニスタン議会の女性比率は米国議会に比肩し得るもの」で、「大学生の4分の1は女性だった」ところ、ターリバーンの首都制圧による新政策により、今やその全てが失われたわけですから。
そういう意味で、ゴパルの言葉では、
ターリバーンの権力の返り咲きにより、保守的な農村部では秩序が回復し、その一方で相対的に自由だったカーブル市街は恐怖と絶望に突き落とされた。
このことによって、過去20年間、暗黙の前提だったことが露わになった、とゴパルは言います。
米軍が農村部でターリバーンと闘っていれば、都市部の生活は花開くことができる、ということだ。これは持続可能だったかもしれない–米軍の空軍力をもってすれば、ターリバーンには都市部の掌握は不可能だったからだ。だが、これは果たして公正だっただろうか。
ゴパルは問います。
「一つの共同体が権利を持つことの条件として、別の共同体の権利が永続的に奪われる、という状況は許されるか」
ゴパルが地方の女性たちにこの質問を投げかけた時の反応は決まって、軽蔑的でした。パザロという名の女性は言います。
「連中は、カブールの女性たちに権利を与えて、ここの女性たちを殺戮している」
マルジアという名の女性は言います。
「これが正義ですか? 私たちを殺し、兄弟を殺し、父親を殺しておいて、『女性の権利』もなにもないでしょうよ。」
隣村のカリダという女性は言います。
「アメリカ人は何の権利ももたらしはしなかった。アメリカ人はやってきて、戦って、殺して、そして去っていった。それだけ。」
結び
以上、ゴパルの記事の要点を抜粋しながら、地方の女性の視点からのアフガニスタンを記述してきました。
アフガニスタンの状況は、私には絶望的に見えてしまいます。ターリバーンが女性の教育機会を禁じるのは、明白な人権侵害だと私には映ります。しかし、パシュトゥーン人の地方では、ターリバーンに従うことが高い代償を伴うとしても「殺されない」ためにはそうせざるを得ないし、また他の武装勢力よりもひどいとも言えない、というのもまた事実のようです。そして、現地基準だと、ターリバーンの方針の相当な部分が、少なからぬ住民、特に地方のパシュトゥーン人の間では一定の理解を得ているらしいこともまた事実と読み取れます。つまり、「人権侵害」とはターリバーン固有の問題ではないわけです。保守的な地元民の意識改革とセットでないと、解決に近づきそうにありません。一朝一夕に解決できる問題ではとてもなさそうです。
いずれにせよ、「女性の人権」を旗印に外国勢力が武力によって言うことを聞かせようとすることは明らかな誤りだと断言します。先方の生存権を脅かしながら人権を叫ぶのは大変な矛盾でしょう。
そもそも、武力干渉を行う際の西側諸国の「女性の人権保護」は、別の目的への言い訳に過ぎないことが事実上100%だと私自身は観察しています。ゴパル記事で解説されているアフガニスタンにおける都市部と地方の対照はその好例とも言えるでしょう。報道されやすい、目に付きやすい都市部では体裁を整える努力をしていても、そうでない地方は全く見過ごされる傾向があります。見過ごされるだけでなく、米国とダドとの癒着の例に見るように、なにか別の思惑があれば、積極的に無視されることもしばしばあります。そもそも、サウジアラビアは女性の人権抑圧で有名ですが、一貫して英米の仲間の国とみなされていて、英米から積極的な武器輸出さえ行っています。武力干渉を行う際に「女性の人権保護」が叫ばれたならば、それは表向きの言い訳以上ではないと眉に唾をつけておくべきでしょう。
結局、実際に武力で脅される、あるいは時には殺される現地民にとっては、「人権」を言い訳にした武力脅迫の偽善性は肌で感じ取れることを疑いません。ゴパルが話を訊いた女性のように。そしてそんな武力行動が、「保守的な人々の意識改革」につながるはずもなく、問題の本質的解決になることはないでしょう。
思うに、現在、アフガニスタン全土を実効支配しているのがターリバーンである以上、国際社会としてはターリバーン政権と粘り強く交渉していくことをベースラインとするしかないのではないでしょうか。
アフガニスタンでは、現在も、犯罪、端的には殺人や虐殺が横行している様子が報道されていて、由々しき事態ではあります。最新のニュースではターリバーンの中でも過激派が実権を握りつつある様子が報道され、一層懸念されます。しかし、それでも、武力介入によってアフガニスタン国民全体の事態が改善するとは極めて考えにくいです。(特に地方の)現地人をこれほど殺し、現地民にこれほど嫌悪されてきた現地民言うところの「アメリカ戦争」の後ならばなおさらです。
春日の講演では、ターリバーンも含めてアフガニスタンの人々がとても柔軟であることが語られていました。多民族国家である以上、それは半ば必然で、お互いに妥協しながらやっていくしかなく、つまりお互い譲るところは譲ることに躊躇ないことが多い、と。そして、「本音」と「建前」をよく使い分ける、とも。為政者が誰であれ、戦火で荒れ果て世界有数の貧乏国でもあるアフガニスタンには国際社会の援助は不可欠です。交渉次第でアフガニスタンが良い方向性に向かうよう希望が持てるのでは、と期待します。
今はとにかく、荒廃したアフガニスタン社会と国土復興に向けて、全力で国際援助を行うことが何よりの急務でしょう。この9月、国連開発計画(UNDP)は、2022年半ばまでにアフガニスタンの97%が貧困に陥る可能性を警告しました(日本語プレスリリース, 英語報告書全文)。アフガニスタン現地、それもかつてターリバーンに弾圧されたハザラ人の地域からも、身の安全はこの8月15日以降改善したが経済状況の不安が大きいと報道されています(“Afghanistan’s Hazaras fear uncertain future despite improved security (アフガニスタンのハザラ人は安全は改善したものの、不確定な未来を恐れている)” ジェイムズ・エドガー(James EDGAR)による2021年9月10日の記事)。
まずは人々が生きていき食べていけるようにならないことには話になりません。そうしてまずは生きるための安全を確保した上で、その中で人権状況の改善を働きかけていくことも次のステップにできるでしょう。
ゴパルの記事の最後のパラグラフにはわずかに希望を見いだせる気がしました。
前述のように、シャキーラの家族は誰も文字を読めません。しかし、実はある日、シャキーラが襲撃を恐れて家の物置に隠れている時、祖父が使っていた国語の教科書を偶然発見し、それ以来、ひそかに勉強しているそうです。ゴパルの記事はこう結びます。
シャキーラには、口に出すことはまずないが、夢がある。シャキーラは、この数十年の戦禍の中、文字を読むことを自習し続けた。今は、パシュトゥーン語のクルーアンを1節ずつ読んでいるところだ。『すばらしい心の慰めになる』と彼女は言う。今、彼女は末の娘にアルファベットを教えていて、大胆な夢を抱いている。女友達を集めて、皆で、男たちに対して少女のための学校を設立するように要求する、という夢を。
女性への教育の必要性を訴える活動で知られ、2014年に史上最年少でノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイは、(アフガニスタンではなく隣国のパキスタン出身ではありますが)同じパシュトゥーン人女性です。彼女の願いは現地住民の願いであり、また人類の願いでありましょう。パシュトゥーン人女性であるシャキーラの夢がいつの日か、できるならば近い将来、叶うことを願います。
[固有名詞の表記についての注] 本文中の固有名詞の大半は、パシュトゥーン語が原語であると考えられる。パシュトゥーン語には、日本語やアラビア語と異なって母音の長さに意味の違いがないと聞く。そこで、パシュトゥーン語固有名詞は、原則として、原文のアルファベット表記を短母音表記で表して、片仮名表記した。一部、イスラーム世界で一般的な名前については、アラビア語発音を参考にした。
本稿において参照した文献
- アフガニスタンの人口分布: https://worldpopulationreview.com/countries/afghanistan-population
- ケシの作付面積2019年統計: https://www.statista.com/statistics/264744/top-countries-for-oppium-cultivation-based-on-acreage/
- 2000〜2001年のアフガニスタンのケシ輸出量の激減 (2021年 エコノミスト誌): https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/09/01/what-does-taliban-control-mean-for-afghanistans-opium-economy
- ヘルマンド地方のケシ栽培 (2007-08-28 英ガーディアン紙): https://www.theguardian.com/world/2007/aug/28/afghanistan.drugstrade1
- ターリバーンによる1998年のハザラ人大虐殺 (Wikipedia英語): https://en.wikipedia.org/wiki/Battles_of_Mazar-i-Sharif_%281997-1998%29#Recapture_and_massacre_%28August_1998%29
- (故中村哲さんの)ペシャワール会: http://www.peshawar-pms.com/
- 『カブール・ノート——戦争しか知らない子どもたち』 山本芳幸著(2001年当時の国連難民高等弁務官カブール事務所長), 幻冬舎 (2001年11月) : https://www.gentosha.co.jp/book/b563.html
- 『アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない、恥辱のあまり崩れ落ちたのだ』 モフセン・マフマルバフ著, 現代企画室 (2001年11月) http://www.jca.apc.org/gendai/onebook.php?ISBN=978-4-7738-0112-5
- 『「新しい戦争」とメディア』 内藤正典編著, 明石書店 (2003年4月): https://www.akashi.co.jp/book/b64700.html (2021年重版)
- 国連安保理によるアフガニスタンへの制裁強化決議 S/RES/1333 (2000): https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1333-%282000%29
- ターリバーンの中枢の穏健派が政権の隅に追いやられている様子の報道(“Taliban Shootout in Palace Sidelines Leader Who Dealt With U.S.” by Eltaf Najafizada in Bloomberg): https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-17/taliban-shootout-in-palace-sidelines-leader-who-dealt-with-u-s
- 国連開発計画(UNDP)が2022年半ばまでにアフガニスタンの97%が貧困に陥る可能性を警告(日本語プレスリリース): https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000075432.html
- “Economic Instability and Uncertainty in Afghanistan after August 15”, released on 2021-09-09, by UNDP: https://www.undp.org/publications/economic-instability-and-uncertainty-afghanistan-after-august-15
- “Afghanistan’s Hazaras fear uncertain future despite improved security” by James EDGAR, 2021-09-10: https://news.yahoo.com/afghanistans-hazaras-fear-uncertain-future-165340958.html
元記事:
- Title: The Other Afghan Women —— In the countryside, the endless killing of civilians turned women against the occupiers who claimed to be helping them
- Author: Anand Gopal
- Date: September 6, 2021
- Publisher: The New Yorker
- URI: https://www.newyorker.com/magazine/2021/09/13/the-other-afghan-women
- c.f., interview (short movie) by PBS: https://www.pbs.org/wnet/amanpour-and-company/video/the-other-afghan-women-z5gepv/