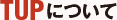FROM: Schu Sugawara
DATE: 2003年7月31日(木) 午前4時09分
昨年のピューリッツァー受賞作『敗北を抱きしめて』で日本でも大反響を呼んだ知日歴史家ジョン・ダワーが、満州を占領し、大東亜共栄圏の夢を追った帝国日本の運命を鑑(かがみ)として、イラク占領に見る超大国アメリカの覇権主義に警鐘を鳴らす。
『イラク‘復興支援'法』が成立し、自衛隊が他国占領連合軍に参画しようとしている今、今年も巡りくる‘敗戦'記念日を前に、わたしたちの一人一人が過去の教訓を改めて噛み締めたい。
「ダワーは、わたしたちがなすべき仕事をなしました。この国は、父祖の時代からの忠告を伝えるのではなく、アメリカの軍靴の踏み跡を辿ろうとしているのです」(訳者よりエンゲルハートへ)
TUP 井上 利男
「ジョン・ダワー:
1931年の満州占領を語り
2003年のイラク占領を展望する」
トム・ディスパッチ 2003年6月20日
—————————————————————-
☆目次☆
編集者トム・エンゲルハートによる序文
『歴史に見る占領――日本の傀儡・満州国』
――占領者たちに共鳴する通底音
――進軍ラッパは鳴り響く
――挙国一致のスローガンに煽られて
――軍部、財閥、官僚の三位一体
(小見出し作成: 訳者)
—————————————————————-
[編集者トム・エンゲルハートによる序文]
ジョン・ダワーは、第2次世界大戦から立ち直った日本の歴史にかけて屈指の
歴史家である。彼の著書2作――太平洋戦争で大量殺戮と残虐行為が病的熱狂
に達するにつれ、日米両国を煽り立てた人種的な憎悪と偏見を論じた『容赦な
き戦争』(平凡社ライブラリー/1986年初版)、および日本の戦後占領期
を描いてピューリッツァー賞を受賞した歴史書『敗北を抱きしめて/上・下巻』
(岩波書店)は、合本セットで読まれるべき名作だ。
今回の戦争の準備段階で、ブッシュ政権内の一部がダワーによる日本占領史の
著作を読み、対イラク政策に日本での経験を生かす方策を熱心に研究している
との世評があった。当時それを聞いて、なんともくすぐったい思いがしたもの
だ。占領統治を想定する米政府官僚たちには、二つの事例が格好の比較対象に
見えたのだろう。フセインのイラクも、旧日本帝国と同じく非人間的な国家で
あり、国民は残虐で堕落した体制から解放されて、民主主義の栄光に浴するべ
きだと――。だが、いまではそれも遠い昔のことに感じられる。
思慮深く細心な歴史家として、また比較占領史の第一人者として、ダワーは下
記の論考でまったく別な比較のしかたを提示する。つまり、戦後日本と戦後イ
ラクではなく、戦前の拡張主義的な帝国日本とアメリカの現政権との比較であ
る。1945年8月と2003年5月との本当の隔たりは、敗戦国日本と敗戦
国イラクとの違いではなく、当時の戦勝国アメリカと現在の戦勝国アメリカと
の違いなのだ。
現代世界におけるアメリカの位置を測るうえで、これほど刺激と洞察に満ちた
論考を他に知らない。本稿はネーション誌(トムディスパッチ・サイトのスポ
ンサー)にも同時掲載されている。(署名)トム
================================================================
「歴史に見る占領――日本の傀儡・満州国」
――ジョン・W・ダワー
—————————————————————-
[占領者たちに共鳴する通底音]
国際的にも国内的にも激変著(いちじる)しい世界へ足を踏み入れつつあるわ
たしたちが、歴史を振り返って、現在位置を知る手がかりや、比較参照すべき
目印、かすかに見覚えのある風光といったものを探し求めるのは、ごく自然な
ことである。そんないま、過去を未来の予測に役立てようとすると、恐怖と希
望の両方をたずさえた、ささやかな比喩イメージとして「日本」が浮かんでく
る。だからこそ、9月11日テロは現代の真珠湾になぞらえられたし(全米の
新聞編集者たちが、ほとんど直感的に真珠湾奇襲を報じたのと同じ「屈辱の日
!」という見出しを使った)、アメリカの現下の敵は第二次大戦の枢軸国をも
じって「悪の枢軸」と名指しされた(北朝鮮は1930年代の日本に相当するの
だろう) 。そしてこんどは、戦後イラクのモデルとして、第2次世界大戦後の
“占領下日本”における民主化という楽天的なシナリオが取り沙汰されている。
しかし、このような類推のどれひとつとして、まともな吟味には耐えられない。
占領下の日本を振り返れば、イラクが1945年の日本とは根本的に異なるこ
と、またアメリカ自体も、半世紀前に抱いていた理想からはるかに遠ざかってし
まったことを思い知らされるはずである。自由主義、国際主義、人権への真摯な
関与、国が重要な役割を担う経済民主化構想――1945年当時、日本の占領
統治に取り組んだアメリカ人たちは、こうした理念を合言葉として政策を練っ
た。ところがブッシュ政権にとって、これらの理念は嘲(あざけ)りの対象にす
ぎない。
いずれにせよ、前世紀なかばのアジアには他にもいくつかの占領事例があり、
現在のアメリカの政策を評価するさい、いずれもじっくり分析する価値がある
だろう。そのうちの2例――沖縄と韓国の占領――は、日本本土の占領政策を
統括したのと同じアメリカの「連合国最高司令官」(ダグラス・マッカーサー)の
指揮のもとで実施された。しかし、もっとも示唆と刺激に富む第3の例は、19
31年に満州で始まり、まもなく中国の万里の長城以南へ、やがて東南アジアへ
と拡大した旧日本の占領政策にほかならない。
日本本土に関しては占領当初から真摯な“民主化”政策を実施したアメリカも、
安全保障問題が当面の最優先課題となれば、民主主義に背を向けてしまうこと
を教えてくれる点で、沖縄と韓国の占領事例は示唆に富む。日本最南端の沖縄
は、軍事戦略家たちがアジア大陸の沖合いに浮かぶ浮沈空母を望んだため、た
だちに巨大な米軍基地に改変された。日本占領は1952年4月に公式に終結
したが、沖縄では1970年代初期に施政権が日本に返還されるまで、アメリ
カによる植民地統治が継続した。その後も、広大でグロテスクな米軍基地群が
存続している。
韓国は、1945年に日本のいわゆる植民地支配からは解放されたものの、国
土が悲劇的に分断され、半島の北半分と同じく専制支配体制が続いた。占領期
間中も占領終了後も、「安定と反共」こそがアメリカの対韓政策の根幹に据え
られていた。韓国国民がアメリカの傀儡(かいらい)政権を自力で倒し、より
民主的な社会を築くには、さらに数十年の歳月がかかった。
満州から中国に拡大した旧日本の占領は、世界史においてほとんど忘れ去られ
た幕間劇の趣(おもむき)だが、現代アメリカの帝国主義的覇権の出現に比較
しうる、もっとも興味ぶかい先例である。もちろん、これら2つの事例のあい
だには大きな違いがある。急速な領土拡大をめざす軍事行動の端緒を開いた1
931年当時、帝国日本は超大国ではなかった。日本の宣伝機関は、民主化・
民営化・自由市場など、今日のアメリカが掲げるような美辞麗句を標榜しはし
なかった。大統領制の衣を着たアメリカの帝政とは異なり、日本の国内政治は
現実の天皇の統帥権によって束ねられていた。
それでも、頓挫した日本帝国と躍進するアメリカ帝国とのあいだには、明らか
な共通項がある。どちらの事例でも目につくのは、極右主義政策の一環として
の帝国建設である。さらに両者に共通するのは、強硬で基本的に単独行動主義
的な対外政策が、国内政治における優先順位や手法の大転換と結びついている
ことだ。
学者たちは、帝国日本の戦時総動員体制と急速な対外膨張政策が、いかにおぞ
ましいほど“近代的”だったかを、ようやく理解し始めたにすぎない。愛国革
新を自称する一派は、対外的には「新秩序」を標榜し、国内向けには「新体制」
を掲げて主導権を握ったばかりか、これら2つの目標が表裏一体であると断言
した。かれらの主張は大胆かつ明解で、目的達成のためには虚言、脅迫、既成
事実化といった手口を弄してはばからなかった。かれらは、空前の軍備増強を
図りつつ、産業界、官僚機構、政治団体を結集する強大な利益共同体を構築し
た。また、新興マスメディアを巧みに操って、国内の大衆を翼賛体制へと動員
した。
過去を振り返るとき、わたしたちはこうした過激な人びとの傲慢と狂気に目を
奪われがちである。かれらの短命な帝国は、日本語の表現を借りれば「夢のま
た夢」同然のものと斬り捨てられているが、ことはそう簡単ではない。帝国日
本のうたかたの大勝利の時期に、かれら極右勢力はアジアに未曾有の激変をも
たらしただけでなく、日本自体にも恒久的な変化を生み出したのだ。そして、
帝国日本の壮大な関心と野心と成果は、わたしたちが今日まのあたりにするア
メリカの政策の多くと不気味に響き合う。体制転換、国家建設、属国づくり、
戦略資源の支配、国際社会からの批判の公然たる無視、「総力戦」のための動
員、文明の衝突というレトリック、人心掌握、国内外におけるテロとの戦い―
―これらすべてが、「大東亜共栄圏」を僭称する新秩序の創造に向けた日本の
不遜な企ての核心だったのである。
—————————————————————
[進軍ラッパは鳴り響く]
アカデミー賞9部門獲得という瞠目すべき栄光に輝くベルトリッチ監督の大作
『ラストエンペラー』(1987年)が、アジア大陸における日本の覇権追求
を世人の記憶に蘇らせることなく、映画ファンを魅了しえたのは、銀幕の不思
議な力を裏づけている。1931年、すでに長期にわたり、地方軍閥と手を結
んで満州に新植民地主義的支配を広げていた日本が、偽りの口実(関東軍の一
部が日本資本の鉄道を奉天近郊で自ら爆破し、それを地元軍閥の謀略だと主張)
を設けて戦端を開き、満州地方を奪取したことで、アジアに新しい帝国の時代
が幕開けした。翌年には、1643年から1912年まで中国全土に君臨して
いた清朝の“最後の皇帝”溥儀(ふぎ)を執政に据え、傀儡国家「満州国」が
建国された。1933年、国際連盟でその挑発的な単独行動主義が糾弾される
と、日本は対抗措置として連盟脱退の道を選ぶ。
いま、わたしたちが婉曲に体制転換と呼ぶこの策動は、のちに万里の長城以南
の中国全土に拡大し、1937年には全面戦争が勃発して、日本は東シナ海沿
岸全域と約2億の中国人を支配下に置くことになった。帝国の軍国主義体制は、
1941年に入ると中国で泥沼にはまり、さらなる戦略資源を求めて東南アジ
ア植民地(フランス領インドシナ、オランダ領東インド諸島、アメリカ領フィ
リピン、イギリス領の香港・マラヤ・ビルマ)に矛先を向けた。真珠湾奇襲は、
この自称アジア解放に対抗するアメリカの軍事介入を遅らせることを目論んだ
もので、今日の米国政府が言うところの先制攻撃に他ならなかった。
軍閥、ゲリラ、“匪賊”からの解放、そして満州を、さらには中国全土を覆う
混乱からの解放、大恐慌後の経済不振にあえぐ世界資本主義体制の不確実性と
略奪からの解放、ソビエトが主導する国際共産主義の“赤禍”からの解放、欧
米植民地主義の“白禍”からの解放――「解放」は一貫して、日本による進出
の決まり文句だった。日本の政治宣伝機関は、「東洋」と「西洋」の決定的衝
突というきわめて事大主義的なメージを煽りたてた。当時もいまも変わらぬ、
魔力に満ちたマニ教的二元論のたわごとである。
—————————————————————-
[挙国一致のスローガンに煽られて]
満州の強奪は、当初こそ日本国内で深い懸念を招いたが、まもなくそれも挙国
一致の大合唱に呑み込まれてしまった。(当時のスローガン「一億一心同体」
は、今日のアメリカの「われら、団結して立つ」と似通っている。) 政治宣伝
機関は、欧米の拡張論者たちを活気づけたのと同じ、使命と(領土拡張)運命
論という美辞麗句を振りまいた。かれらは、アメリカのモンロー主義の文言さ
えも流用し、満州奪取は「アジアのモンロー主義圏」建設の一環であるとして
正当化した。 満州を管理下に置けば、たしかに戦略資源(特に鉄と石炭)は確
保できるが、大義はもちろん平和と繁栄というわけだ。満州国の建国によって、
歴史上に例を見ない「五族共和」(日本人、中国人、満州人、蒙古人、朝鮮人)
が達成されるだろうと宣言された。さらに、これよりはるかに重要なのは、満
州国が、極右勢力の標榜するもっとも基本的な理想像を具現した政治経済体制
確立のためのパイロット事業として構想されていたことである。
(訳注: ここで言う「アジアのモンロー主義圏」は「大東亜共栄圏」を指すと
思われる)
陶然たる当時の雰囲気の中で、人びとの感情に訴えた標語は「理念としての満
州」だった。表面上、このようなイデオロギーは、今日の新アメリカ帝国の熱
烈な信奉者たちが喧伝する主義主張とはかけ離れているように見える。大恐慌
の大波を受け、世界の他の国々と同じように打ちのめされていた日本では、
「自由市場」だの放任資本主義だのといった概念そのものが、控えめに言って
も受け入れがたいものだった。そんな空気の中で、満州国は「国家資本主義」
ないし「国家社会主義」の新しいモデルを導入する絶好の機会として捉えられ
た。
(訳注:「理念としての満州」は原文直訳のママ――「王道楽土」「満蒙義勇開
拓団」「日本の生命線」など、満州にまつわるスローガン的言辞は多い)
こうした大きな違いがあるにせよ、日本の事例とアメリカのそれとのあいだに
見られる数多くの共通項が消えるわけではない。いつもながら悪魔は細部に宿
るのであり、ここでもっとも興味深い細部とは、対外積極政策の採用が、国内
における政治経済秩序の徹底的な転換をともなう点だ。帝国日本の支配層は、
今日のアメリカと同じく、党派分立に悩まされていた。内部抗争の結果、当時
の陸軍大将で、のちに首相になる東条英機とつながる「統制派」に率いられ、
軍部と提携した勢力が主導権を握った。
統制派という呼び名には二通りの意味が込められていた。ひとつには、もっと
過激な右翼も含め、他の党派を統制するという意味である。もうひとつ、より
重要な意味は、挙国一致の「総力戦」を戦う究極目的のために、経済と社会全
体を掌握する決意を指していた。「総力戦」は、第一次世界大戦以降、戦略家
たちの心を捉えていた戦争概念だった。1931年の満州事変勃発は、国家総
動員体制を実現する好機となった。
総力戦に向けた動員計画遂行のためには、対外政策でも国内政策においても、
軍部独裁が貫徹されることになる。アメリカの国務省に相当する日本の外務省
は脇役に追いやられ、経済関連省庁は軍部の要求に従う侍女となった。ほぼア
メリカの司法省と本土安全保障省を合わせた役割をもつ内務省は、国内治安警
察と“危険思想”弾圧の機能を強化した。(日本の1930年代は、複数の著
名人暗殺事件が起こった国内テロの時代でもあり、1936年には大規模なクー
デター未遂<2・26>事件も発生した。)選挙にもとづく国会は、メクラ判的
な承認機関に成り下がった。共産主義者と左翼は大挙して、帝政批判勢力から
の転向を公に表明し、天皇の「錦の御旗の下での革命」成就のために献身する
と宣言した。マスメディアは検閲制度に縛られ、自らも自主検閲で縛った。ひ
とたび軍国主義機構が動き出し、戦死者に対する「血の債務(恩義)」が人び
との心にしっかり根づくと、皇軍を支持しないことなど言語道断になってしまっ
た。
—————————————————————-
[軍部、財閥、官僚の三位一体]
戦時総動員経済は、その近代性において特筆に価する。これは、日本をアジア
支配に駆り立てたのは後進性や「封建的遺制」だったという、かつてもてはや
された論議を覆す考え方である。国家予算は軍事関連支出に圧倒的に傾斜配分
された。満州奪取に続く10年間は、日本の重化学工業が飛躍的に発展した
「第2次産業革命期」だったと、今日の歴史学者は記している。企業合併の大
波が、産業・金融部門のみならずマスメディアも呑み込んでいった。
1930年代以前から、近代日本の経済は(三井、三菱、住友、安田の)4大財
閥、すなわち巨大な複合企業系列グループに寡占支配されていた。しかも満州
奪取を好機として、これら「4大財閥」は、軍需部門の主要生産者、被占領地
における開発事業の大口利権者、萌芽期の労働組合運動に対する弾圧の主役、
そして、富と力の格差拡大を特徴とする国内「二重構造」の整理統合の推進主
体となった。
1930年代は同時に、「新興財閥」として知られる技術革新企業の勃興期で
もあった。これらは主に軍需契約企業であり、帝国建設の請け負い業者である。
4大財閥同様――また、いま「対テロ戦争」のあぶく銭をつかもうと騒ぎたて
ているアメリカの最先端企業と同じく――新興財閥も軍部と癒着して事業を推
進し、今日で言う縁故資本主義を育てた。戦争が終わる頃には、(浅野、古河、
日産、大倉、野村、中島の)6大新興財閥は、鉱業および重化学工業における
払込資本金の16パーセントを占め、他方4大財閥のシェアも膨れ上がって、
32パーセントを超えるまでになった。とどのつまり、「国家社会主義」にとっ
て強引な民営化は大歓迎なのだ。
文民官庁内部では、軍部タカ派と革新的な新興財閥に呼応して、「新官僚」あ
るいは「革新官僚」の名で知られる熟練テクノクラートがゆるやかに連携し、
国外の新秩序を国内の新体制に結びつける役割を担った。体制批判者や野党は、
このような連中を悪徳官僚――財界なら悪徳資本家、軍人なら悪徳軍部――と
糾弾したかもしれないが、いかんせん悪党たちが権力を握っていたのである。
ここでは1930年代日本の軍部支配を論じているものの、戦時中から戦後に
いたるまで、選挙による政治と一般社会機能の大部分は継続していた。194
4年には、東条英機すら適正な国会手続きを踏んで権力の座からおろされたの
だ。しかし、東条とその仲間の極右勢力が起動させた軍国体制は、戦争が本土
に波及し、広島と長崎でクライマックスを迎えるまで、だれにも止めることが
できなかった。帝国としての日本は短命だったが、あとに残された荒廃は甚大
だった。
占領地と帝国の泥沼化がいよいよ深まっても、日本の指導層とその追随者たち
は、愛国心の炎に煽られ、痛ましい運命論に突き動かされて、「撃ちてし止ま
ん」の精神論でがんばり通した。戦(いくさ)に敗れ、あとの祭りになってよう
や
く、知識人と政治家と一般国民が立ち止まり、こう自問した――なんであれほ
どすっかり騙されたのだろう、と。
この問いに答えるには、いまのわたしたちのほうが有利なはずだ。
————————————————————-
【原文】
The Other Japanese Occupation, by John Dower,
written for Tomdispatch.com, a weblog of the Nation Institute
http://www.nationinstitute.org/tomdispatch/index.mhtml?emx=x&pid=771
Copyright C 2003 John Dower
(著作権者=ジョン・ダワーよりTUP配信許諾済み)
=============================================================
翻訳 井上 利男 / 監修 星川 淳 / TUPスタッフ