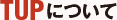1月7日パリで『シャルリ・エブド』テロ事件が発生した当夜、仏公共放送フランス2の夜8時のニュースは「フランス襲われる」という見出しで始まった。オランド大統領が生中継で「共和国とは」の第一に「表現の自由」を挙げて「国民の団結」を呼びかけ、スタジオでは『シャルリ・エブド』を共和国の象徴的存在とする論調が大々的に展開された。まず政界の重鎮R・バダンテールが「風刺画家たちは自由の兵士だったから殺されたのだ」とぶちあげ、別の1人が「彼らは我々の"アイデンティティ"だった」と応じると、モスクの指導者は「テロはフランス共和国に対する宣戦布告である」と、レトリックをさらに競り上げてみせた。コメンテーターの1人は、共和国理念をふりかざしたイスラーム非難の急先鋒としてかつがれている元『シャルリ・エブド』誌女性編集者だった。連日メディアを埋めた「私はシャルリ」のスローガンは、表現の自由を守ることと『シャルリ・エブド』の編集方針を支持することとの区別をぼやけさせ、同誌の編集方針についての議論や疑問は、英語圏メディアと比べるとフランス国内でははるかに少なかった。政界とメディアはこの忌わしいテロを利用して、「共和国対イスラーム」という、これまで繰り返し作ってきた虚構の図式をここぞとばかりに強調した。
このテロで本当に問うべきことは何か。以下に、フランスのアラブ・アフリカ系社会科学者たちによる寄稿を紹介します。
(翻訳:荒井雅子/TUP)
自分が”問題”になるとはどういうものか
2015年1月21日
シャディア・アラブ、アフメド・ブベケル、ナディア・ファディル、ナシラ・ゲニフ=スイラマ、アブデルアリ・ハジャト、マルワン・モハメド、ナシマ・ムジュー、ヌリア・ワリ、マブラ・スマホロ
「自分が”問題”になるというのはどういうものか」と[米国の]黒人社会学者W・E・B・デュボイスは1903年に書いた。フランスやヨーロッパに住む「ムスリム(イスラーム教徒)」(とされる人々)は、その国の国籍であれ外国籍であれ、ここ30年ほど、いやでもこう自問せざるを得なくなっている。アル=カーイダあるいは「IS」のメンバーを自称する三人のフランス人武装襲撃者グループが『シャルリ・エブド』社で大勢の人を惨殺し、ユダヤ人嫌悪の人質殺害事件を起こしたことによって、フランス社会にすでに存在していた政治的社会的緊張は悪化するばかりだ。一部の人々から見れば、こうした殺人は、「ムスリム共同体」を「フランス国民の中の別の民」とみなしてきた作家やジャーナリストによる予言の不吉な成就となる。問題を起こすこうした「共同体」の存在は、「再移民」によってしか解決されないという予言で、「再移民」と言えば聞こえはいいが、「国外追放」のことだ。また、イスラームとテロを一くくりにしないことが重要と認めつつも、こうした暴力の解決には結局のところ、イスラームの神学者や指導者が「イスラームの改革」に(遅まきながら)取り組むしかないと考える人々もいる。
テロに対する、この2つの解釈の枠組みは、1つの重要な社会的事実を誤認している。オリビエ・ロワがいみじくも指摘したとおり、「ムスリム共同体など存在しない」ということだ。イスラームを掲げる宗教的な諸組織は、ムスリムとされる人々を代表するものではない。ムスリムとされる人々は、社会階層、国籍、政治的・イデオロギー的志向などの点でさまざまだ。だがこの多様性は、[テロ実行犯と]「縁切り」しろの大合唱によってすっかりかき消されている。新しく作られたこの言葉では、ムスリムとされる人々が殺人者と密かに連帯していることが前提になっている。言い換えれば、ムスリムとされる人々は、罪があるとみなされているのだ。たとえ、無慈悲に殺害された警察官や、ユダヤ商品スーパーで何人もの命を救った元不法滞在者 [その後フランス国籍を与えられた] が、ムスリムとされる人々の一員だったとしても。ムスリムとされる人々は大変な事態に直面している。ムスリムであるという理由で問題の原因とされ、ムスリムとして公に「縁切り」しろと迫られる……。彼らは二重の怒りを抱いている。一つはテロを非難し、遺族とともに悼むもの、もう一つは「縁切り」せよという、名誉を傷つける要求を拒むものだ。
この2種類の言論がフランスで幅を利かせるのには理由がある。かつては移民と呼ばれていた人々が、今日ではムスリムと呼ばれるようになっているからだ。以前は「移民統合の問題」だったものが、「ムスリム問題」になった。だが問題にされているのは同じことだ。彼らはフランスの領土に住む資格があるか。フランス人失業者の国外追放が「失業問題」の解決になるなどとは誰も考えないのに、「ムスリム問題」となるとそれが公然と議論される。だから、ムスリムとされる人々のアイデンティティを「イスラーム性」だけに帰すとき、口には出せない真実がある。これは今に始まったことではない。そういう人々は紙の上でフランス人であるだけで、たとえフランス国籍をもっていようと追放されても仕方がない、ということだ。
パリを襲った暴力の原因に目をふさぐ風潮を問題視しないわけにはいかない。殺戮が国内にも国際的にも激しい感情を巻き起こしたため、この暴力の生成のメカニズムを解明しようとしてきた社会科学者やジャーナリストたちが軽視されがちになっている(たとえばフランソワ・ビュルガ、オリヴィエ・ロワ、ファラド・コスロカヴァル、ディトマル・ロッシュ、ヴァンサン・ジェイセル、アフメド・ブベケル、サミル・アムガル、モハメド=アリ・アドラウィ、ヴァレリー・アミロー、ロマン・カイエなど)。こうした学者やジャーナリストは「人がよすぎる」とか「”政治的正しさ”ばかり」とか「現実を正面から見据えることができない」などと非難される。歴史的にみると状況は9/11後に似ている。イスラーム主義を掲げる暴力的小集団について長年調査を行ってきたジャーナリストや社会学者、政治学者に向かって、机の前に座ったジャーナリストやテレビ常連の哲学者が、「現場の教訓」を垂れる。あらゆる毛色のイスラーム嫌いたちが、この機に乗じて「文明の衝突」の概念への回帰を押し付けようともくろんでいる今、問われているのは、経験的根拠のある理性的な言論を生み出せるかどうかということそのものだ。
ムスリムとされる人々がつまはじきにされた後、次に槍玉に挙げられるのは、『シャルリ・エブド』のイスラーム嫌悪を批判したとされるジャーナリストや活動家だ。彼らは殺戮に「責任」があると非難され、それを清算しなければならないと言われる。あたかも殺人者がこうしたジャーナリストたちの記事や声明に触発されて行動を起こしたとでもいうかのように。こういうジャーナリストや活動家がメディアで影響力があったことにされているが、実際にはそんなことはなかった。公的な舞台への登場機会には偏りがあり、だれが発言権を得るかに根強い非対称性があることは明らかだ。また、襲撃グループに対する本当のイデオロギー的影響――アル=カーイダという混沌とした集合体の指導者たちの書き物に探るべきもの――が無視されている。こうした非難が暗黙の前提としている論理は詭弁じみている。『シャルリ』誌の編集方針を擁護し、それを批判した人々を攻撃するのは、この編集方針によって殺戮が正当化されうると認めることになる、ということだ。理性よりも感情が先走り、イスラーム嫌悪という現に存在する社会現象を非難する言論は学問であれジャーナリズムであれ運動であれ、片っ端から検閲される危険があるように思われる。そしてこうした一からげの責任のなすりつけは集団懲罰に転化する恐れがある。「シャルリでない」人々が潜在的な敵とみなされるのだ。
こうした不健全な、凝り固まった考え方は、イスラーム嫌悪行為のその後の増加にすでに示されているように、暴力の増幅を煽ることにしかならない。これを避けるには、事実に立ち戻って、政治的暴力の非宗教的な分析を行うことが不可欠だ。暴力に訴えるのはあの襲撃者たちに限ったことではない。他にも、別のイデオロギーの名の下に、あるいは別の紛争の文脈で、暴力に訴える集団が存在する。深層にあるメカニズムを捉えるため、そして政治に携わる者なら暴力を未然に防ぐためには、イスラームを掲げる襲撃者が行った暴力を特別視しないことが絶対に必要だ。問うべきは次のような点である。人はいかにして戦闘員の「道」に入るのか。政治的暴力を可能にする条件は何なのか。襲撃グループのメンバーの経歴から、いくつかのことがわかる。原因の第一は、9/11の前と後に(シリア、イエメン、イラクなどで)欧米が行った軍事介入によって引き起こされた地政学的な泥沼にある。ソ連への敵対勢力として米国の支援を受けた、タリバンや後のアル=カーイダ幹部ら「自由の戦士」は、ベルリンの壁崩壊後、かつての同盟者だった米国に矛先を向けた。彼らはアフガニスタンで、外国勢力の支援を受けて政治的・宗教的秩序を強制し、また、そのイデオロギーを共有して処刑と破壊のテクニックを身につけたがっている世界の襲撃者たちみなに避難所を提供した。アフガニスタンの訓練キャンプで、数世代の襲撃者が養成された。「極悪のけだもの」は欧米による介入の鬼子であり、アルジェリア、チェチェン、ボスニアなどの権力紛争から養分を吸い取った。そして、1995年にパリ、2001年にニューヨーク、2004年にマドリッド、2005年にロンドンと、欧米大国の心臓部を襲撃した。1970年代以降、軍事的資本が蓄積された後に、鍛え上げられた襲撃者たちによるかつてない暴力の波が欧米大国を襲った。こうした暴力的な集団は数カ国に限られていたが、「対テロ戦争」によって、イラク、シリア、リビア、イエメン、マリ、パキスタンなど、以前はこうした暴力集団が存在しなかった国やかかわりの薄かった国で数を増すことになった。「IS」の指導者たちのような新しい世代が、欧米による占領との闘争の中で、軍事的養成を受け、アブグレイブやグアンタナモの収容所の中で、あるいはその実態を目にして過激化し、アフリカからアジアに至る、文字通り国境を超越したネットワークの中を動いている。言い換えれば、イスラームを掲げる政治的暴力の第一の原因は、中東での国家による暴力と、まさに「対テロ戦争」の名の下に行われた戦争の悲惨な結果にある。
こうした国際的な原因を断つことは、言うまでもなく困難を極める仕事だ。フランスは、アラブ世界とアフリカでの権威的な体制との同盟やイスラエルの植民地政策への支持、自国の多国籍企業の権益などを不問に付しながら、いったいどうやって、民族自決の権利に基づき、(本当の)人権尊重に基づく外交政策を行えるというのだろう。
暴力の第二の原因は、フランスの下層階級地区で深刻化する疎外感と関連している。「縁切り」せよというイスラーム嫌悪の合唱が暗に示していることとは逆に、襲撃グループの3人のメンバーは、言ってみれば「自由電子」であり、周囲との個人的、感情的な結びつきが弱く、別離で心に傷を負った生い立ちと社会的な孤立と構造的不平等の産物だった。そのために、非行と暴力的小集団の世界に投げ込まれたのだ。こうした自由電子は、仲間、特に親族や地元モスクの信者とはすでに「縁を切って」いたのであり、教育支援の仕組みによって「すくい上げられる」こともなかった。そして「文明の衝突」が迫っていると確信する宗教指導者――客観的にみればネオコンの指導者と持ちつ持たれつの間柄――の磁場に惹きつけられていった。下層階級のこういう子どもたちは、強度の社会的暴力を取り込んで、生けるロボットと化しており、もはや従来の構造の中で自分たちの存在に意味を見いだせず、力と認知を約束してくれる、死の匂いを帯びた虚無的なイデオロギーの中にそれを見出す。彼らは下層階級地区できわめて少数派にとどまる。
フランスのイスラームには多種多様な傾向が存在している。独立系モスクがあり、出身国(マグレブ諸国やトルコ)と関係の強い大規模な団体があり、ムスリム同胞団などの信徒団体があり、タブリーギー・ジャマアトがあり、政治色がなく敬虔な「サラフィー主義者」がおり、スーフィー(イスラーム神秘主義者)がおり、そのほかにもいろいろあり、そして「タクフィリスト」(訳注†)と言われる暴力的小集団がある。毎日毎日、地元の政治家、活動家、住民は、静かに、新聞の一面を飾ることもなく、こうした暴力的小集団の影響力と闘っている。だからこそ、クアシ兄弟も属していた「ビュット・ショーモン・ネットワーク」のメンバーは、2000年代初め、移民の権利擁護・反ファシズムの活動家たちによって、パレスチナ支持のデモから排除されたのだ。歴史の皮肉は、かつて現場で暴力的小集団と対峙していた人々が、今では、イスラーム嫌悪を糾弾したとして排斥されているということだ。こうした暴力的小集団が存在し維持されているということは、下層階級内部の力関係に直接結びついている。集団が何人かの自由電子に影響力を持つとすれば、それは他の政治勢力、特に1980年代に平等と人種差別反対を訴えた行進の後継者たちが勢いを失って政治的空白が生じたからだ。そこからテロ実行犯となる者たちが生まれてきた。さらに、旧ソ連由来の兵器が意外なほどたやすく買えることや、「タクフィリスト」ネットワークがソーシャルネットワーク上で国境を越えてイデオロギーや軍事的ノウハウを伝達し、組織への勧誘を常に行っていることも、この現象を助長している。
(訳注†) タクフィリスト:信仰を実践しないムスリムを棄教者とみなし、欧米と同様に攻撃の標的にする一派。「タクフィール」はアラビア語で「不信仰者宣告」を意味する。1967年中東戦争敗北後のエジプトで復興し、80年代に先鋭的支持者ザワヒリら将来のアル=カーイダ指導部メンバーがアフガニスタンに集結、さらに米国による侵攻後のイラクでザルカウィらが勢力を伸ばし、2003年以後アル=カーイダの主流となった。
フランス国内の原因を断つことも容易なことではない。それには、経済的・社会的不平等、教育機会格差、政治的排除、はびこる人種差別、住む場所による烙印など、社会的暴力と非行の原因となっている問題に取り組み、社会階層の底辺におかれている人々にとっての真の平等の政策を推進することが必要となるだろう。
2015年1月の政治的暴力を可能にした条件にはさまざまなものがある。政治家は社会科学研究者による分析にもっと耳を傾けるべきだ。ところが、耳障りなことはききたがらない為政者やその顧問、メディアの耳は、「イスラームとテロ」”学”の専門家の方を向いている。事件以前に殺戮者たちを把握し、聴取していながら見逃していた諜報当局の失態は、実行犯を「無力化[射殺]」したという成果によってうやむやにされているようだ。事件に対して真っ先に起こった政治的反応は、最悪の方向へ向かっているように見える。自由を抑圧するテロ法が2カ月前にすでに成立しているにもかかわらず、「フランス版愛国者法」の成立を図る、死刑[フランスでは1981年に廃止]に関する議論を蒸し返す、同化不能とされるムスリムを「内部の敵」として標的にする、など。国籍の出生地主義見直しの声も出て来ると考えられる。つまり、9/11後の政治的教訓は忘れられているように見える。それは政治的暴力は、国家の暴力と社会的暴力から養分を吸い取って肥大するということだ。
シャディア・アラブ 国立科学研究センター研究員
アフメド・ブベケル サンテチエンヌ大学教授
ナディア・ファディル ルヴァンカトリック大学准教授
ナシラ・ゲニフ=スイラマ パリ第8大学教授
アブデルアリ・ハジャト パリ第10大学ナンテール講師
マルワン・モアメド 国立科学研究センター研究員
ナシマ・ムジュー グルノーブル大学講師
ヌリア・ワリ ブリュッセル自由大学准教授
マブラ・スマホロ トゥール大学講師
原文
- 題名
- Qu’est ce que ça fait d’être un problème?
- 日付
- 21 janvier 2015
- 著者
- Chadia Arab, Ahmed Boubeker, Nadia Fadil, Nacira Guénif-Souilamas, Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, Nasima Moujoud, Nouria Ouali, Maboula Soumahoro
- URI
http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/210115/qu-est-ce-que-ca-fait-d-etre-un-probleme