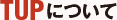FROM: Schu Sugawara
DATE: 2004年3月4日(木) 午前0時36分
お知らせ、2月25日に配信したTUP速報263号「赤旗とキリスト教戦士たち」。おかげさまで大好評でしたが、キリスト教関係の方々からいくつかのご指摘があり、資料としての正確さを期するために【改訂版】として校正いたしました。263号とお差し替えいただきたく、よろしくお願いします。
TUP速報係 菅原 秀
////////////////////////////////////////////////////
1945年、無条件降伏を受けいれた日本に進駐してきた連合国占領軍に続いて、アメリカから大勢の宣教師たちがやってきました。本稿は、日本占領政策のもうひとつの側面、キリスト教を武器とした共産主義に対する闘争の経緯を分析し、キリスト教であれ“自由と民主主義”であれ、“戦勝国”による精神文化の押し付けの愚かしさを浮き彫りにします。だが、これは一方的な断罪の書ではなく、日本にやってきたアメリカ人宣教師たちの善意の行いは公正に伝え、また日本のキリスト者たちと進歩主義者たちを励ますエールにもなっています。(TUP 井上 利男)
====================================================
『赤旗とキリスト教戦士たち』
いつでもアメリカは敵をやっつけ、アメリカ商法を持ちこみ、自由市場に再編し、キリスト教に改宗する。2003年の今、アメリカの宣教師たちが“てぐすねひいて”軍靴の後を追い、文明発祥の地イラクへなだれこんでも、1945年に始まった日本への宣教活動の結末に似た珍妙な結果に終わるだろう。
――ティム・ショーラック
キリング・ザ・ブッダ・コム 2003年
————————————————-
戦艦ミズーリ甲板上で日本の降伏を受けいれてからようやく1ヶ月たった1945年10月のある日、東京中心部にある第一生命ビルに構えた占領軍司令部で、ダグラス・マッカーサー元帥はアメリカ宗教界を代表する牧師たちと向かい合って着席していた。民間人としては戦後日本に初入国したかれら4人は、第2次世界大戦中に途絶えていた日本のキリスト者たちとの対話を再開する目的で来日していた。
生涯を通して聖公会に忠実なキリスト教徒だったマッカーサーは、できるだけ早く1000人の宣教師を派遣してほしいとかれらに依頼した。「日本は精神の空白地帯なのです」とかれは言った。「それをキリスト教で満たさなければ、共産主義が埋めるでしょう」
このようにして、冷戦期のきわめて奇妙なエピソードのひとつ、日本をデモクラシーの反共親米拠点に仕立てる使命に、キリスト教を活用するマッカーサーの計画が動きはじめた。
1946年から50年の間に、キリスト教の主流諸教派の呼びかけに応じ、またアメリカ政府上層部からの祝福を受けて、2000人の教師、福祉関係者、伝道者たちが来日した。かれらに混じって、わたしの両親がいた。シアトル出身の父は、戦時中に日本語を習得した元海軍士官であり、コネチカット州出身の母は、中国に熱い関心を抱く神学生だった。
両親はディサイプル教会に派遣されて、1947年8月に来日し、任期は3年だったが、結局、アジアに22年滞在した。わたしは子供時代を東京の大きなアメリカ人社会で過ごした。その共同体は、1000年以上続いた文化を作り変える遠大な目的を共有する宣教師、外交官、軍人、企業幹部、CIA工作員が集まった幸福な大家族だった。
アメリカの十字軍は、物量だけが頼りだったので、みじめな失敗に終わった。第2次世界大戦後の政治混乱のさなか、数百万規模の国民が日本共産党に入党し、左翼と組んで労働組合を組織化し、またはそれに加盟し、あるいは核兵器の拡散と実験に反対してデモをした。戦後56年たった今、キリスト教徒を自認する国民の数は総人口の1パーセントの半分程度であり、真珠湾攻撃以前のそれと同じ水準である。[訳注: このデータはプロテスタント系のみのものと思われる。カソリックも含めると、総人口の1パーセント弱]
だが人道支援の観点から見れば、1945年以降のアメリカ人宣教師たちの到来には意義があった。宣教師たちは戦争で傷ついた人びとを癒した。敗戦で意気消沈した日本国民が、実業家でも軍人でもない新しいタイプのアメリカ人の姿を目にすることになった。宣教師たちは、日本国民の戦後不安と貧困を共有するためには、快適な住み処をかえりみない心意気も持ちあわせていた。東京に住む篤信のクリスチャンであり、わたしの両親が友人になった最初の日本人のひとり、武田清子は、「あの人たちは若く、理想主義を抱いて、日本に溶け込んでいました」と思い出を語った。「あの人たちは統治国を背負っていませんでした。和解のために来たのです。クリスチャンだけではなくキリスト教でない人たちも、あの人たちの態度を心から賞賛していました」 [訳注:武田清子は元国際基督教大学教授]
実際、第2次世界大戦後の宣教師たちの働きは独特であり、過去100年間のどの宣教師活動に比べても画期的だった。その顕著な特徴は、1945年から52年まで日本を支配した“統治国”政府と宣教師たちとの関係に見られる。連合国軍によって4分割統治されたドイツとは違って、日本はアメリカ占領軍および太平洋連合軍最高司令官(SCAP)の直接統治下に置かれていた。
マッカーサー元帥は、日本を戦争に引きずり込んだ「卑劣で冷酷な野蛮人」(トルーマンの言葉)のイデオロギーの桎梏(しっこく)から日本国民を解放するために必要であれば、どんなことでも実行しなければならないとされていた。かれは、トルーマン大統領の指令により、日本占領の初日から、必要と判断されることはなんでもできる権限を与えられていた。マッカサーにとって、この未曾有の権力は、キリスト教、それもアメリカのキリスト教を日本に導入する絶好の機会を与えた。
ウィリアム・P・ウッダードは戦前の日本での宣教体験があり、かれの著書『天皇と神道―GHQの宗教政策』(サイマル出版会1988年刊)は、マッカーサーの宗教にかかわる政策と態度について英語で書かれた唯一の歴史書である。元帥は「かなりの救世主妄想、すなわち今こそ神に召されているという意識、神はわが側にいますという確信にとりつかれていた」とかれは書いた。
占領司令部・宗教調査班を率いたウッダードによれば、マッカーサーは、日本の伝統宗教は劣っていて、そのいくつかは危険思想集団でさえあると考え、日本がデモクラシーを築き、あらゆる方面から忍び寄る共産主義イデオロギーから自衛するために、日本国民が獲得しなければならない正しい道徳的基礎はキリスト教だけが呈示できると信じていた。
ウッダードの引用によれば、マッカーサーは、ある時の演説で、日本国民に必要なのは、「われわれがなしとげた、ほとんど比類ない科学、芸術、文学の進歩、ならびに過去2000年間をかけて達成した物質的・文化的発展に適応するための精神の再生および人間性の改善である」と宣言した。この簡潔だが仰々しい言葉にトルーマンが心から感動し、この一文をアメリカ人聖職者が日本滞在中に携行する公式契約書に書きこんだ。
戦後日本に来たアメリカ人宣教師たちの物語は、ある意味で占領そのものの歴史であり、華々しい勝利と暗澹たる敗北の両義矛盾に満ちた、2度と繰り返されることのない壮大な社会実験だった。いまだに大戦中の精神構造から完全には抜けきれていない現代日本の状況に照らしあわせると、この実験は特に大きな意味を持つ。例えば、ほんの2年足らず前、当時の森義郎首相が不用意に漏らした「日本は天皇を中心にした神の国」という言葉を見るとよい。あるいは、かれの後を継いだ小泉純一郎は、英霊たちが祭られているウルトラ国粋主義の精神的拠り所であり、A級戦犯たちも合祀された靖国神社に繰りかえし参拝すると頑なに決意しているではないか。
さて、占領下日本を舞台にした政治と宗教の混合は、ジョージ・ブッシュの軍勢がイラクで未知の未来へなだれ込み、またもやアメリカが非キリスト教文化を乗っ取ろうとしている今の状況に、不気味な繋がりを示して木魂(こだま)している。ブッシュの熱狂的な救世主妄想に共鳴する宣教諸団体が、アメリカ対外政策の目標とアメリカ風味のキリスト教熱を混ぜ合わせて、21世紀十字軍の色合いを帯びた人道支援計画をすでに目論んでいる。こうした宗教組織の中には、保守的な南部バプテスト協議会があり、またイスラム教を“邪悪”で“不愉快”な宗教と決めつけた名高い福音説教師ビリー・グラハムの息子、フランクリン・グラハムが率いる原理主義団体が含まれている。
この文脈において、日本でのマッカーサーの政策は、アメリカ政治の精神病理に深く埋め込まれている宣教師妄想を鮮やかに浮き彫りにしている。
―――――――――――
1945年:絶望の日々
―――――――――――
1945年秋、アメリカの牧師たちがマッカーサーに面会していたころの日本では、東京、大阪、横浜、神戸、広島、長崎といった重工業地帯をはじめ、160を超える都市が廃虚になっていた。広島と長崎は人類史上最初の核兵器で汚染されていた。全国どこでも食糧難だった。中国、朝鮮半島、南太平洋から敗残の日本兵たちが徐々に帰還しはじめ、母国に残っていた民衆は飢え、疲れ、米、野菜、肉などの食物を渇望していた。
絶望が日本を調査に来たキリスト者たちの胸を引き裂いた。かれらが日本人牧師および信徒との顔合わせの席で出会った人びとは、途方にくれ、意気消沈し、軍国主義に連座したことを恥じ、500以上の教会を破壊し、数えきれない民間人を殺害した米軍の爆撃に苦しみ、外部からの援助と救済を切に求めていた。日本人牧師が、国民は「ショック状態であり、傷つき、自尊心を失い、惨めである」とかれらに語った。
調査団を率いていたのは、進歩的な世界教会協議会の北米側の委員会を代表するダグラス・ホートン博士、および、戦前の東京で11年間、キリスト教学校の教師を務めていた、北米海外宣教協議会から派遣されたルマー・J・シェーファー博士だった。1946年にまとめられた報告によると、かれらの宣教活動方針は霊的目標と政治的目標の同一化を図るマッカーサーの政策を踏襲していた。「われわれは、日本を自立した政治軌道に乗せる意図を持った国家の市民として来たのであるが、キリストの教会の課題に向かって前進することを、主たる、あるいは事実上唯一の目標とする」とかれらは謳った。
ホートン調査団が日本の教会事情の視察を終えると、かれらはニューヨークへ戻り、宣教師活動の組織化に着手した。各メンバーが所属する教派から、日本での活動歴がある6人の宣教師が選定され、連合軍最高司令官との連絡を統轄することになった。かれらは日本で活動することになる志願者を募りはじめた。働く場として特に重視されたのがキリスト教主義学校であり、1946年に発行された若者向け雑誌の呼びかけによれば、そこでは「毎日の生活で実践されるキリスト教の生き方の浸透が最も肝要であろう」とされた。
新しい宣教師たちの第1波は、主としてプロテスタントのアメリカ最大教派連合である教会協議会に繋がる教会からやってきた。協議会系の教会は、1800年代末期の“社会的福音”運動の時代から、活動内容として、宣教と改宗よりも社会事業と教育を重視してきた。かれらは、100年も前から、社会的関与の一環として、日本、中国、その他アジア各国に宣教師たちを派遣している英国の教会と協力してきた。だが、もはや大英帝国は衰退に向かいはじめ、アメリカが英国を凌駕する世界強国に台頭するようになると、アメリカの教会は急に海外宣教活動の中核を担うようになった。
志願者の大半は、大学、聖書学校、さらには軍隊を出たばかりの若い人びとだった。かれらの動機は、かつての敵との和解、ヒロシマ・ナガサキへの贖罪、日系アメリカ人強制収容への悔恨といった、さまざまな戦後世代の意識に根ざしていた。1948年に来日し、40年たってから宣教師たちの姿勢を調査したある宣教師が、「特筆すべきことに、異教徒を救済するというような、古くて画一的なタイプの宣教師の常套句はいっさい聞かれなかった」と書いた。
1947年5月22日、マッカーサー指揮下の連合国最高司令部(GHQ)が、大勢の日本のカトリックおよびプロテスタントの代表者たちと会合したのに続いて、宣教活動の資格審査を廃止・解禁すると発表した。この方針転換によって、戦後初めて子ども連れの家族でも入国できることになり、本国の教会が新任者向けに大量の食料、衣料、プレハブ住宅、自動車、その他支給品を発送することが公に認められるようになった。
メリーランド州スートランドの米国公文書館に収蔵されている広報によれば、GHQは「この方針の見直しによって、今後3年間に、日本への宣教師たちの流入がいちじるしく増大すると期待される」と謳った。「これは、日本国民が(キリスト教の)基本的な原則を理解し、受容するのを奨励したいというマッカーサー元帥の意向に沿うものである。最高司令官は可能なかぎり多くの有能な宣教師の入国を助けようと努力している」
3ヶ月後、わたしの父母が到着した。
―――――――
神か、政府か?
―――――――
今は退職し、南カリフォルニアの元牧師・宣教師たちの隠退ホームで暮らすわたしの父は、少年のころ、シアトルで優美な日本の貨物船が行き交うピュジェット湾を眺めていて、初めて日本を知った。かれは日本の経済力に賛嘆の念を憶えたが、長年フィリピンで布教していたバプテスト教会宣教師だったかれの祖父が、1938年にアジアへの航海から帰ってきて、日本と戦争になると告げたので、不安が入り混じるようになった。
パールハーバーから数ヵ月後の1942年、父は海軍に入隊した。短期間の駆逐艦勤務の後、父は選別され、コロラドおよびオクラホマ州の海軍語学校で日本語を学ぶことになった。かれは、その後の戦争期間中、日本語を磨けば、通訳、占領当局者、CIA職員、外交官のキャリアを約束された奨学生たちのエリート集団、別名“ボールダー軍団”の一員だった。
わたしの父も出世コースへ進んでもよかった。しかし、かれの語学教師のひとりに日系アメリカ人がいて、その人から違った方向に進むようにと勧められた。「わたしのクラスは小人数だった」と父は述懐する。「あの年輩の日本語教師はきっとクリスチャンだった。ある日のこと、語学校を卒業すれば、どんな仕事をすることになるかについて、かれは話していた。そして、『君たちの少なくともひとりは、政府、海軍、国務省、その他なんであれ宮仕えの道に進まず、日本に行って、キリストにおける兄弟姉妹になり、一介の民間人として紐付きでない道を歩んでほしいものだ』とかれはポツリと言った。そこでわたしは考えた。おもしろそうだ。それに、海軍にはたいして気乗りがしなかった。それでかれの言葉に従うことにした」
とりあえずかれはYMCAに手紙を書いてみたが、すでに日本行きを熱望する応募者が殺到していた。次に自分の教派であるディサイプル教会に申し込んでみた。教会の目にとまり、かれはインディアナポリスの本部に呼ばれた。だがディサイプル教会がかれに申し渡したのは、東京の男子学校の教師になる準備として、コネチカット州ニューヘイブンのイェール大学神学校で神学を修めることだった。父が母に出会ったのも、その神学校だった。
わたしの母はコネチカットの酪農場の生まれであり、17世紀に先祖がニューイングランドに到着したという家系の出身である。母は、子どものころ、隠退した英語教師の話に触発されて、極東への興味を募らせた。中国でキリスト教女学校を創設し、1930年代末期になってコネチカットに帰郷した元教師は、1931年に始まった日本の中国侵略にまつわる心を捉える物語を話してくれた。聞いていた母の心に火がつき、医者になって中国に行きたいと、駆りたてるような大望が燃えあがった。だが、運命、男女差別、経済事情が邪魔になった。その代わり、母は聖職者の道へ進むことにした。ハートフォードのプラット&ホィットニー航空機会社での2年間の勤務をへて、1946年に母はイェール大学神学校に入学した。100人を超えるクラスで、10人の女性のひとりだった。
イェール大学でも、やはりふたりが学んだニューヨーク市のユニオン神学校でも、外国で神に仕えたいというわたしの両親の願いは、強烈に揺さぶられた。そのふたつの学校は、第2次世界大戦後の意気軒昂な時代、アメリカ中に充満した精神と政治の覚醒の中心にあった。ファシズムを相手にした戦争から帰還した若いアメリカ人たちは、周囲を見渡し、未完成の仕事が残っていると結論づけた。今こそ、自由世界の新興指導国家アメリカはニューディール政策が触れずにきた社会的・人種的不公正を正さなければならない――理想が若い人びとを揺さぶり、戦争と圧政で病んだ世界に手を差し伸べ、癒したいと願わせた。
1947年に来日し、以後15年を超えて滞在したメソジスト派の牧師であるチャールズ・ジャーマニーが、「当時の誠実なアメリカ国民の心を捉えていた教えはなにか?」と書いた。「第1に、理想的な社会とは民主主義社会である。第2に、この理想がもっとも具現している国はどこか? アメリカ合衆国である。わが国は全体主義に対する戦争に勝利した。第3に、アメリカにおける民主主義社会の基礎はキリスト教だった。これこそがわたしの呼吸してきた気風に組みこまれていた」
わたしの両親の教師には、進歩的な雑誌『キリスト教と危機(Christianity &Crisis)』を創刊した、デトロイト出身のキリスト教社会主義者ラインホールド・ニーバー、高名な共産主義思想の権威であり、後にニーバーの雑誌の編集者になったジョン・ベネット、ノースカロライナの織物工場主の息子として、黒人と白人が団結した織物工ストライキを研究したことから、人生の転換をなしとげ、後にその研究をまとめた古典的な書物『職工と説教師』を著したリストン・ポープがいた。全米規模の労働不安、南部の人種間緊張、冷戦の最初の兆しといった時代背景の中で、このような出会いがわたしの両親に決定的な影響を与えた。
ふたりは陸軍用船舶を改装した米海兵隊艦アダー号に乗りこみ、赴任地・東京へ出立した。かれらに加えて、船は中国と日本へ向かう宣教師たちを満載していた。両親の船室は別々で、母は女性専用区画、父は甲板を5層下った男部屋だった。数年前、わたしがその船旅についてたずねると、母は微笑み、「わたしたち、時どきキスして、一緒に入り日を眺めたわ」と述懐した。毎晩、甲板で映画会が開かれたが、新米宣教師たちの多くは娯楽を拒み、代わりに祈祷会に出席していたと母は語った。「わたしたちは映画を観にいったわよ」と言って、母は笑った。「この船旅が、わたしたちが入っていこうとしている宣教師の世界をかいま見せてくれたわ」
―――――――――――
廃虚のワーク・キャンプ
―――――――――――
わたしの両親は横浜のドックで米陸軍従軍牧師の出迎えを受け、ジープに乗せられ、爆撃で焼き払われた街を過ぎ、東京北東部にある聖学院中学校に連れていかれた。以後3年間、ここがかれらの住み処になった。日本に到着して2日目、かれらは電車で東京を一周した。混雑した鉄道ターミナル・新宿駅から西側の市街地の大半は、1945年春の大空襲でアメリカの焼夷(しょうい)弾に焼き尽くされ、荒れ地になっていた。さすがに道路は片づいていたが、車線間と道路沿いには、いまだに爆撃時の瓦礫がビッシリと積み上げらたままだった。銀行、保険会社、百貨店など少数の鉄筋コンクリート建てビルは焼夷弾に耐えたが、それを除くと東京の建物といえば掘っ建て小屋だけだった。子どもたちが道路脇から物乞いし、片言の英語で「チョコレート、チョコレート」と哀願し、GI(米兵)ならだれもがポケットに持っているハーシー・チョコをせがんだ。市街地を外れた日本人の教会で行われた両親の最初の歓迎会で、お茶とサツマイモのおふかしがふるまわれた。サツマイモは、いまだに国土の大半をおおっていた貧困の代名詞だった。
1948年、わたしの父は、日本と韓国に国際ワーク(奉仕)キャンプのネットワークを構築するようにと世界教会協議会および会衆派教会奉仕委員会から依頼された。北米とアジアの学生たちを一堂に集めたそのキャンプの体験は、両親の日本滞在初期のハイライトであり、2001年8月、わたしの母が早すぎる死を迎えるまで、宣教生活の想い出を語るのにかれらがもっとも好んだ話題でありつづけた。一夏中、両親の世話のもと、若者たちが働いて、北海道に戦地から復員してきた日本兵の子どもたちのための保育園を造り、東京に青少年センターを建てた。長崎では、1945年8月9日に落とされた原爆で破壊された建物に替わる小学校を建てた。
わたしの家族の一生の友人であり、連合軍最高司令官と協力するように選定された6人の戦前日本での宣教体験者のひとり、レイ・ダウンズは、かれのワーク・キャンプ体験の思い出話が好きだった。ボランティア仲間たちを評して、「かれらは常軌を超えて働く質(たち)であり、楽天的で活気のある人たちだった」とかれは語った。
1950年1月にホートン調査団のラマン・シェーファーが執筆した『日本の宗教事業に関する報告書』を米国公文書館でわたしが見つけ、2年前に父に見せると、かれは目に見えて誇らしげだった。シェーファーは、4ヶ月の日本滞在の後、「ハル・ショーラックの指導のもと、重要なプロジェクトが数多く実行に移されている」と書いた。東京の基督教大学を除けば、「他のなによりも昨年の青年キャンプがキリスト教運動の注目を惹きつけた」
それにしても、若者たちの重労働と規律は戦前からの宣教師たちを驚嘆させた。そのかれらといえば、うだるように暑い日本の夏の間、長野県山中の眠気を誘う高原避暑地・軽井沢で過ごしていた。わたしの父は、「夏中、働く宣教師なんて、それまでだれも聞いたこともなかったよ」と言って、笑った。「昔ながらの宣教師にしてみれば、まあショックだったね」
1950年、わたしの父がイェール大学の学位課程を終了するために、両親は2年間の一時帰休を取得してアメリカに帰った。51年5月5日、わたしがニューへイブンで生まれた。1年後、両親はわたしの姉とわたしを連れて再来日し、続く18年間の大半を日本で過ごした。50年代の残りの期間、母は子育てにかかりきり、父は、米国教会協議会の救援部門であるチャーチ・ワールド・サービスの日本での救済活動の責任を負っていた。それは大した仕事だった。1955年までに、アメリカの教会は、米政府放出の農産物900トンあまり、衣料品3000梱包、食料品4500キログラムを200万人の日本人に配給した。仕事のおかげで、わたしの父は日本中を旅する機会を得て、後にその範囲は韓国とその他アジア各国に広がった。
わたしの日本の記憶で最初のひとつは、アメリカの教会から日本の農民たちに贈与された乳牛を積んだ貨物船の出迎えに、父に連れられ横浜の港へ行ったことである。わたしたちは明け方に起床して、我が家のちっちゃな車、(不思議なことにイギリスから輸入した)フォード・カウンセルに乗り込み、港までドライブした。港で小さな通船に乗り込み、本船に着くと、白黒のジャージー種と茶色のガーンジー種の乳牛が干し草と厩肥の香りが匂う牛囲いに詰め込まれていた。日本人の沖仲士たちが、はるか北の北海道の酪農場へ旅立つ牛たちを船降ろしする機械を操作する合間に、わたしを肩車してくれた。ある日、南の島・九州が大洪水に襲われた時、東京西部・立川の懐かしい米空軍基地へ、わたしは父に連れられて行った。被災者たちが災害から立ち直る一助として、教会から贈られた山羊の空輸をボランティアで引き受けた軍用輸送機編隊の帰りを出迎えたのである。
――――――
最大級の恩典
――――――
このようなできごとにも表れているが、マッカーサーのキリスト教好きはアメリカ軍と教会の親密な結びつきを強めるのにおおいに役立った。例えば、ホートン調査団はアメリカ陸軍輸送機で東京へ来た。ドクター・ホートンは、「交通手段と宿泊施設の両面で、陸軍から最大級の恩典を賜った」と記している。
マッカーサー配下の従軍チャプレン長であり、滞日中のホートンを補佐したアイバン・ベネット陸軍大佐は、1945年の秋、聖書数千冊の日本向け出荷を手配した。49年には、マッカーサー自らが日本国民に向けて聖書を贈ることを提案し、再び大量に輸送された。マッカーサーは連合軍最高司令官の公式用箋に、聖書は「あらゆる自由の要石であり、公正で誠実な政府の基盤であり、約束をたがえることのない神への真実で生きた信仰の礎(いしずえ)である」と記して、日本国民に布告した。[訳注:チャプレンは軍隊などの公的施設・組織つきの聖職従事者。現在ではあらゆる宗教から派遣される]
宣教師活動は占領統治の実質的な補完任務に位置づけられていたと言っても誇張ではない。この政策によって、おおかたの日本国民の目に教会の威光が喧伝(けんでん)されていた。
アメリカ陸軍は日本に宣教師たちを派遣していた38の教派の郵便物すべてを引き受け、宣教師の一部には銀座の陸軍PX(売店)での買物特権を与えていた。日本国有鉄道で国内を旅する宣教師たちは、MP(憲兵)に案内されて、車体に引かれた白線で容易に見分けられる占領軍専用車両へ直行した。わたしの母は「わたしたちのだれもが、乗車券を買わなければならないという事実を受け入れるのに、ずいぶん時間がかかったわ」と言った。「最初にやらなければならなかったほんとうの厄介事は、いかにして自分自身の意識を占領軍生活から切り替えるかだったのよ」
宣教師活動に対する占領当局の支援を印象づける不朽のシンボルのひとつが国際基督教大学(ICU)であり、現在、この東京にある単科大学・大学院併設校は日本の超一流私学のひとつにランクされている。ICUはアメリカの宣教師たちと日本人クリスチャン教育者たちの夢であり、1948年に計画が具体化して、資金集めとスポンサー募集が始まった。マッカーサーみずからが一肌脱いでICU財団の名誉理事長に就任した。やがて財団は50万ドルの資金を集め、東京西郊・三鷹市の学校敷地を中島航空機研究開発会社から購入した。53年秋にICUは開学した。
わたしの父は、教会救援物資の配給に15年間従事した後の1960年代始め、ICUの財務副部長に指名され、わたしの家族は60年代の大半を西東京の広大なICUキャンパスで暮らすことになった。
わたしたちが最初に引っ越した63年当時、ICUは松と樺(カバノキ)がうっそうと茂った森のオアシスだった。他の教員住宅と同じく、わたしたちの家は丘陵の尾根沿いに建っていて、天気のいい日には、武蔵野平野の上に聳える富士山を眺望することができた。麓(ふもと)には、ICU農場の外れまで広がる木立の間を小川が流れ、わたしたちは蛙とザリガニを捕った。農場は50年代始めに父が日本に取寄せた乳牛を何頭か購入し、飼っていた。
キャンパスは楽しい場所だったが、たった20年前までたけなわだった戦争の名残にも満ちていた。わたしの父の執務室があった長いばかりで冴えない建物は、かつての中島本社中枢であり、そこで日本の航空部隊がアメリカ攻撃が可能な長距離爆撃機を開発しようとしていた。本部の隣りには巨大な格納庫が建っていて、昔はそこに開発段階の爆撃機が並んでいた。わたしの弟たちや教員の子弟など若者たちは、格納庫のコンクリート床を自転車レース場に使い、黒焦げのセメントの塊(かたまり)、錆びた鉄骨梁(はり)、ガラス片を避けながら走りまわった。友だちとわたしはわたしたちの家の下の尾根で洞穴を見つけた。1945年の春から夏にかけて日本を攻撃したアメリカのB29爆撃機が投下した焼夷弾から逃れるために、地元の人たちが丘の中腹に掘ったものである。
ICUは第2次世界大戦が残した瓦礫の中から誕生したとわたしは一貫して考えていたが、何年もたってから、そのほんとうの起源は冷戦時代に燃え盛った反共主義の熱気の中にあるとようやく気がついた。マッカーサーと占領軍官僚たちは、みずからが発案した日本にキリスト教大学を創立する計画のために、アメリカで募金運動を進めていた時、金持ちのアメリカ人篤志家たちの目の前に共産国家日本の幻影をちらつかせていたのである。
「スターリンがドイツと日本を共産主義衛星国家に仕立てあげるようなことになれば、冷戦はかれの勝利に終わります。アメリカはヨーロッパとアジアの真ん中に挟まれていますので、孤立してしまうでしょう」と、米国務省の元役人であり、ICU財団理事だったウィリアム・L・クレイトンが、ICU資金贈与が期待できる聴衆を前に発言した。したがってアメリカは「日本の自由主義勢力に精神的・道徳的意味のある援助の手を差しださなければなりません。…… 日本に国際基督教大学を創設することは、こうした方策を具体化する第一歩になるでしょう」
朝鮮戦争のさなか、アメリカ資金の流れが細くなると、懇願の声はヒステリックな調子を帯びた。「現在、朝鮮で勃発している侵略的な軍事行動はアメリカとわれわれの生き方への直接的な挑戦であります。かれらが成功すれば、アメリカは信望を失い、もっと悪いことに、おそらく日本はもとの状態に逆戻りし、あるいは共産主義の奴隷になるでしょう」と、米海軍のチェスター・ニミッツ提督が1950年の募金要請パンフに書いた。「ICUは日本の針路を正しい方向に保つ頼れる舵棒なのです」
1950年代中頃までに、ICUと占領当局との初期の関係もそうだが、このようなレトリック(誇大言辞)はほとんど忘れられてしまった。だが、アメリカの冷戦政策と宣教活動との強固な繋がりはそのまま続いた。
例えば、戦後の日本にアメリカの教会から贈与された数百万のドルは、冷戦のフォールアウト[原注:付随的結果、時には放射性降下物、すなわち死の灰そのもの]の被害を受けた人びとのセーフティネット(救済資金)に使われ、日本におけるアメリカの政策を支える役に立った。1954年、アメリカがビキニ島で実施した水爆実験で発生したフォールアウトを浴びて放射能症にかかった漁師たちの家庭に、アメリカの教会が衣料品と食料品を配布した。ビキニの核実験は3名の漁師たちの死をもたらし、ビキニ近辺水域漁獲の大量廃棄をよぎなくさせ、核兵器反対を訴える日本の抗議行動に火をつけた。だが、アイゼンハワー政権は賠償金支払いを拒絶した。漁船の母港である村むらを支える悲しい仕事は、結局、アメリカ人宣教師たちの肩に残されることになった。
1950年代始め、日本政府がアメリカの石油資本の圧力を受け、基幹エネルギーを石炭から石油に切り替えた後、炭鉱地帯の戦闘的な労働組合の弾圧におよんだ。こういう事態を受けて、宣教師たちが新たに大規模な救済プロジェクトを立ちあげ、職を失った炭鉱夫20万人に食料品と衣料品を供給した。こうして、アメリカの宣教師たちは、アメリカ対外政策がもたらした人道上の付随的被害を、無意識のうちに繕(つくろ)う役回りを演じていた。
――――
神道指令
――――
多くの日本国民はこうした支援や寄付に感謝していたが、マッカーサーがあからさまに広言していたキリスト教推奨は、占領当局が掲げていた政教分離原則の目指すものに甚だしく相矛盾するものであり、占領政策を批判する日本国民の多くの憤りを買った。
占領軍司令部の民間情報教育局・宗教文化班は、1945年秋の創設以来、全国に散開して、占領軍の宗教規制の遵守を強制していた。45年12月には、占領軍は有名な神道指令を発令して、公的に日本国と神道および国家が唱導した天皇礼拝との結びつきを分断した。その指令は、日本の宗教は「国粋主義と軍国主義の隠れ蓑」として利用されてはならないとも宣言していた。
アメリカの宣教師たちとアメリカ軍の緊密で公的な繋がりを考えれば、これはかなり皮肉な捩(ね)じれである。おまけに日本固有の宗教に対するマッカーサーの蔑視は、国家神道の生きた象徴である天皇を、アメリカの命令を日本国民に伝える道具として利用するために、裕仁の皇位を保証するという、かれの不幸な決定とも矛盾している。
また一方、日本の宗教に対するアメリカの監督はあまりも細部にこだわり、占領当局者が仏教寺院の御家騒動に介入することもあるほどだった。ウッダードが記録した事例では、僧正に敵対した左翼仏教僧たちのストライキを、軍当局者が違法と裁定したが、その僧正はかつて熱心な戦争推進論者だった。
占領軍のキリスト教支援策と日本の他宗教への対応の差が甚だしいので、1946年には、仏教界と神道界からの激しい抗議を招くようになった。マッカーサーはそうした声をことごとく無視した。アメリカの当局者のなかには、いたたまれなくなって、他宗教にも“平等”な方針であたらなければならないという気持ちに駆りたてられる者たちもいた。かれらは占領軍のキリスト教徒支持政策の偏向を正すために、禅宗の学究ルース・ササキが求めた1年間の研究目的の日本留学を認め、ユダヤ教ラビ(律法博士)の入国を許した。
だが、公正を期した涙ぐましい試みがあったとしても、マッカーサー本人が帳消しにしてしまった。47年、総理大臣に選出された片山哲は、社会党委員長でありながら、クリスチャンだった。マッカーサーは選挙結果を捉えて、これは“人間性の進歩”の印であり、キリスト教こそが外国イデオロギーの“浸透”を遮る“不壊(ふえ)の防壁”であることを証明したと声明した。
わたしの両親とかれらの親友である宣教仲間たちは、こういった類の宗教・政治心情とはほとんど無縁だった。かれらがイェール大学とユニオン神学校で学び、わたしをはじめ子どもたちに言って聞かせていた真実とは、他者の宗教と信念体系にも心開いていることだった。原理主義的な宣教師たちはクリスチャンでなければ人にあらずとバカにし、口癖のように「救われていますか?」と連発していたものだが(「何から救われるんだろう?」と父は言っていた)、そういうのを両親たちは軽蔑していた。
こういう姿勢では、他の宣教師たちと常にうまくいくというわけにはいかなかった。1955年、チャーチ・ワールド・サービスが東京都渋谷区にわたしの家族の住宅を建てることを承認してくれた。家の骨組みが完成すると、わたしの両親は、棟梁たちに、遠慮せずに神主を招いて、古来の清めの儀式である上棟式を執りおこなうように勧めた。天辺の棟木に清浄のシンボルである白い幟(のぼり)が立ち、祝詞をあげ、香を炊いて、お神酒が回された。わたしたちが知り合っている宣教師家族のなかには、クリスチャンたる者の家にあるまじきことをわたしの両親が許したとショックを受けた人たちがいた。かれらにとって、こういう儀式は神への冒涜だった。
――――――――――――
共産主義者との主導権争い
――――――――――――
アメリカの宣教師たちと日本の仲間たちは、資金力では圧倒的に有利だったが、日本の左翼に対抗するのは難しいと悟った。戦後日本の瓦礫のなかで、日本共産党が復活し、日本に存在した他の組織が手をこまねいているうちに、政治的・社会的空白を埋めてしまった。(戦前の)日本軍国主義と天皇制の勃興に果敢に抵抗した党の前歴が、日本の労働者たちと学生たちのあいだに共産党員への絶大な人気と信望を呼び起こした。
抵抗で彩られた党の歴史に比べると、日本の宗教団体のほとんどはまったく顔色なかった。キリスト教会団体も例外ではなく、1941年には政府布告に従って、組織を統合したのであり、日本軍国主義にはおざなりの抵抗を示したにすぎない。
皮肉なことに、共産主義者の最大の好機の源はマッカーサーその人からの賜物だった。占領が始まってから最初の数ヵ月、元帥は日本の軍国主義の解体と民主化の速やかな断行のために、政治犯を釈放し、言論出版統制を解除し、労働組合禁止令を廃止した。戦争が終わって陸軍刑務所から解放された共産主義者の大半に労働運動の活動歴があった。1930年代の日本軍国化とともに発展した巨大企業の内部で、たちまちかれらは組合オルグ(組織化)活動に全エネルギーを投入したのである。
戦後の最初の年だけで、労働組合の数はゼロから1万2000に跳ねあがり、擁する組合員の合計は370万人になった。「このような改革の断行が共産主義者に圧倒的な勇気を与え、GHQ(マッカ-サーの最高司令部)が共産主義者を援護しているという印象を国民全体に与えた」と、日本のキリスト教神学教授が1950年の報告に書いた。
わたしが国際基督教大学の文書保管室で見つけた、この匿名の教授が著した注目に値する研究論文によれば、日本の資本家・地主階級を糾弾する共産主義者の甲高い声が、戦争の惨禍で家を失い、貧窮のうちに打ち捨てられた何百万もの日本国民の心をつかんだ。「共産主義は理解しやすく、他のどの思想よりも目下の要求を満たしてくれる」と教授は書いた。「それは国民の心に洪水のように流れこんでいる。…… 共産党の当面の目標のひとつは私有財産制度の廃止であり、まさにこの戦争は国民の大多数を無産階級にしてしまった」(原論文のまま)
また共産主義者は、日本のアジア侵略を主導し、国民をアメリカとの悲惨な戦争に引きずり込んだ国粋主義を拒否する日本国民の深い思いをうまく活用した。クエーカー教徒であり、明仁皇太子(現天皇)の家庭教師を務めたエリザベス・グレー・バイニングは、回顧録『皇太子のための窓』に、このような日本国民の超越性への渇望について記している。かのじょの眼には、日本の共産主義者が多くの支持者を得たのは、日本のみならず世界に通用する理想主義を提示したからであると映った。「かれらによれば、共産主義は人類愛なのだ。ここには身を捧げても構わない類の高貴ななにかがある。人類のためには人は身を捨てても構わない」とバイニング夫人は書いた。同時に、左翼は「占領軍とその失策と不公平さへの反感をも利用した。共産主義者たちだけが国民を救いたいと願っていると人びとに約束した」
共産主義者との主導権争いの困難さが1950年代のキリスト教文献の主題だった。最近、わたしが両親の本棚で見つけた宣教師のためのハンドブック『宣教実務』を読むと、日本の書店に並ぶ社会科学の本の半数はマルクス主義関係のものであると書いてある。「聖書を読みたいという願いは大きい」と筆者たちは報告した。「たしかに聖書はベストセラーである。だが、聖書と共産主義書籍とはきびしい競争関係にある。人びとは両者の利点を天秤にかけている」ひとつの章は、共産党が「学生、道に迷う人、探し求める人、若者たちの集団」を結集した労働者デモについての記述にあてられている。そして――かれら“失われた魂”は教会に従うのだろうか?――それとも「平和と平等の名のもとに武装弾圧の体制を備えた西方の隣人、共産主義者に向かうのだろうか?」と問いかけている。
わたしの父は、民衆が日本の保守主義政権の背後にいるアメリカへの怒りを発散させていた皇居前広場で行われたデモを、近接した銀座オフィスの自室窓から何度も見物していたのを憶えている。共産主義者が労働組合を組織し、若い人びとを大義のもとに結集しているのを眺めていて、クリスチャンと宣教師には、日本の一般国民の状態を改善するようなことはなにもできていないと、父は感じるようになった。今でも父は、「共産主義者は社会のためになにかをしようとしていたが、クリスチャンはそれほど関心を持たなかった」と言っている。ほどなく、このような思いが父を苦境に陥れることになった。
1949年、日本のキリスト教・教育協議会が父に日本の青年層の意識調査を依頼した。日本の21都市の若い人びとと教会指導者たちへの面接調査にもとづくかれの報告は、教会が教育・社会事業を刷新する方向に速やかに進まなければ、これまで以上に共産党へ地歩を譲ることになり、教会は忘却のかなたに消えてしまうだろうと結論づけた。報告はUPI通信社の特派員(後にCBS放送に移籍)ピーター・カリッシャーの目にとまり、父は初めて“束(つか)の間の”時の人になった。
「あるアメリカ人プロテスタント宣教師の意見では、日本の青年層を獲得する競争でキリスト教は共産主義に敗北している」と、カリッシャーは記事の冒頭に書き、それが毎日新聞に転載された。(最近、国立公文書館のアメリカ占領軍部門のキリスト教と共産主義に関する書類ファイルの中で、この記事を発見したし、他にも数点の切り抜き記事に父について書かれているのを見つけた)
「日本の教会は、なんらかの人生の意味を探し、把握しようと努めている若い人たちに呈示する指導指針をまったく用意していない」と、カリッシャーはわたしの父の言葉を伝えた。「クリスチャンのやることは祈りだけであると多くの非キリスト教徒が考えているのは残念なことである」とかれは続けた。教会は「今日、若い人たちに訴えかけていない。どちらかと言えば、そのために若い人たちはキリスト教に背を向け、懐疑論と物質主義の奈落にまっさかさまに落込み、少なくとも指導綱領と大義を備えていて、勝算のありそうな共産主義者の陣営のよぎなく加わることになる」
カリッシャーの記事は日本共産党の機関紙『赤旗』にも掲載され、さらにはアメリカ本国で広く伝えられたので、たちまちインディアナポリスのディサイプル教会理事会の目にとまった。わたしの父は、共産主義がキリスト教に替わるべき有望な存在であると言ったのではなく、キリスト者は精神生活上の対抗者からも学ぶべきものが多くあると述べただけであると辛抱強く説明した。この弁明で理事会はどうやら納得し、物議は終わった。だが、ワシントンのどこかで、きっと父の名は後学のためにブラックリストに記載されているはずだ。
――――――――――――――
心情と世論の獲得競争に敗れて
――――――――――――――
1940年代末ごろには、アジア民衆の心情を惹きつけ、世論の支持を得る競争でアメリカは敗れていると米政府首脳と軍中枢は認識していた。ヨーロッパで両陣営間の緊張が高まり、アジアで毛沢東の軍勢が蒋介石率いる国民党を中国大陸から追い落としかねない状況になって、アメリカは、世界共産主義勢力こそが敵であると名指しして、攻撃姿勢を鮮明にした。ただちに日本は極東におけるアメリカ冷戦政策の戦略拠点に位置づけられた。
占領初期の2年間は解放政策が採用されていたが、1947年になると、占領軍は“方針転換”を図った。政治の民主化改革と軍国主義の解体に代わって、工業の再建が努力目標に据えられた。かつて軍国日本の総動員体制の根幹であった財閥(金融資本と工業生産力を系列化した巨大企業連合)に対する規制が緩和された。
9月には、共産党とその支持勢力が占領政策に抵抗して、全国規模のゼネストを指令したが、マッカーサーはそれを違法として抑えこんだ。翌年にかけて、大掛かりな“レッドパージ(赤狩り)”が猛威を振るい、日本の労働組合幹部たちと共産党員たちが何百人規模で逮捕され、あるいは解雇された。
このような容易ならざる歴史的経緯を経て、戦後日米関係を決定づけた基本的枠組みができあがった。時が移り、冷戦が終結し、日本の金融システムが半ば崩壊し、日本を支配してきた自民党が弱体化した今日になっても、この構造がそのまま続いている。
基本的に、アメリカは日本の財界およびその政治的支持者と組んで、極東とアジアにおける封じ込め戦略の支持基盤を強化するために日本を経済的に支えた。これが、戦に敗れた日本のエリートたちが喜んで同意した役回りだった。だが、日本はアメリカに見苦しいほどに依存することになった。一方のアメリカは、朝鮮半島、ベトナム、その他どこへでも軍隊を送る立場になり、日本の権益を保護し、時には日本が経済進出するための地ならしをすることになった。これは、いつか日米を多大な両国間の紛争に導きかねない状況である。
政治活動を実践するマルクス学派の歴史家である武藤一羊は、わたしが1981年に初めてお目にかかった時、「戦争に負けて無力になった日本帝国主義ですが、もちろん、その一部分子は復活を望みました」と説明した。「しかしかれらは状況が変わってしまったことをじゅうぶん知っていました。これが第1です。第2に、アメリカを相手にもう一度戦うことは不可能であり無益であることも知っていました。そこでかれらは実に明解な戦略を採用しました。日本は帝国主義の経済基盤構造の構築に専念することになります。一方、アメリカは軍事力で実質的にアジアを支配します。この関係のもっとも顕著な特色は、日本が決して戦争しなかったことです。アメリカは戦争しました。日本の兵士は死にませんでした。アメリカの兵士は死にました。アメリカが戦争した事実そのものが日本経済に利益をもたらしました。それをアメリカの右派グループが言いたてるのです。日本はもっぱら“ただ乗り”を続けていると主張するのです。わたしはかれらの言い分はもっともだと思います。事実ですから」
1950年、冷戦が現実の戦闘になって燃え上がった。北朝鮮が親米・李承晩政権からの南の解放を旗印に戦端を開いたのである。夏には、アメリカの大規模な軍事介入が始まって、朝鮮戦争が一気に拡大した。だがこの戦争は日本にとって3年間続くことになる奇蹟の経済成長の始まりの引き金になった。戦争遂行のためにアメリカが発注した巨額の特需を追い風にして、日本の鉄鋼、自動車、軍需産業が復活し、たちまち戦前の生産水準を突破した。軍事需要が60年代の輸出先導型急成長の基盤を築いたのである。45年以来始めて、ついに洗濯機や自動車のような贅沢品に廻せるだけの余裕資金が、日本の消費者の財布に入った。
だが、戦争で経済的に潤ったにしても、多くの日本国民は朝鮮戦争の凄まじい人的犠牲を見て震えあがった。クリスチャンであるなしにかかわらず、日本国民の眼に、在日基地を出撃拠点として、大規模な北鮮爆撃作戦を強行する好戦的なアメリカは、敗北した日本を悲惨な状況から救済するために来た慈悲深いアメリカとはまったく正反対の姿に映った。
朝鮮戦争の勃発直後、アメリカの新聞クリスチャン・サイエンス・モニターが、熱心な反共主義者であり、著名なクリスチャンでもあった湯浅キヨへのインタビューを掲載した。その記事に表されたかのじょの見解が、マッカーサーの政策に対する日本人のアンビヴァレンス(相反する両面感情)を示す代表例になっている。かのじょは「日本国民はキリスト教の指導に喜んで従います。マッカーサーは有能なクリスチャンなので、かれに従ってきました」と言った。だがかのじょの意見では、朝鮮で「反共主義を掲げて武力で戦っている」マッカーサーの軍事作戦は、「同じ反共主義であっても、かれの日本統治方策とはまったく違う部類のものです」
1951年、朝鮮で休戦協定が締結された後に、日本語紙・キリスト新聞が、「朝鮮人たちが被った損害はあまりにも大きい。この戦争が終結した今、世界の国ぐにはこの問題を取りあげ、なんらかの形で遺憾または同情の気持ちを表すべきである」と論評した。アメリカ国民の大半は朝鮮戦争を共産主義との決着をつける闘争として見ていたが、日本のキリスト教徒たちはそれほどはっきりとは考えていなかった。戦端を開いたのが、北朝鮮であったのか、中国共産党だったのか、あるいはヤルタ会談で朝鮮半島を分割したアメリカとソ連の首脳たちだったのか、いずれであっても、「わたしたちは人類を戦争に駆り立てる魔性の力に身震いするばかりである」とその記事は結んでいる。
朝鮮戦争中、日本の知識人や共産主義とキリスト教の指導者たちが団結して、アメリカのアジア政策に抗議し、アメリカが日本領土に軍事基地を確保することを認める、1952年に締結された2国間軍事協定に反対した。日本の満州植民地開発を指導したことで戦犯法廷で有罪判決を受けたにもかかわらず、総理大臣になった岸信介のような保守主義の政治家をアメリカが後押ししたことも、さらなる疑念を募らせた。
アメリカ人の元宣教師ジム・フィリプスが、日本におけるキリスト教の歴史を記した著書『日が昇る国から』に、「理想主義肌の日本人の多くはアメリカが平和に貢献していると思いこんでいたが、朝鮮戦争勃発は衝撃だった」と書いた。アメリカは「日本の平和憲法を率先して起草したにしても、国家として平和原則にそれほど貢献しているわけではなく、極東の共産勢力拡張を防ぐためであれば、あえて戦争に出かける国なのだ」と日本国民は思い知った。こうした理由から、1950年以降「アメリカの基幹宗教であるキリスト教に寄せる日本人の関心は著しく冷めてしまった」
―――――――――
キリストの冷戦闘士
―――――――――
冷戦のもうひとつの側面として、宣教師たちの新しい波が押し寄せ、日本国内の外国人キリスト教社会の構成を変えてしまった。新参者たちの多くは頑なな原理主義的な反共主義者であり、ほどなくリベラル派を4対1に届きそうな割合の数で圧倒するようになった。かれらの多くは中国と朝鮮の共産勢力支配地を追われて、日本に来た。そうでなければ、冷戦の風潮のなかで、メソジスト、ディサイプル、長老派といったリベラル寄りの主流教派に対抗して、1940年代末期から50年代初期にかけて創設されたアメリカの新興諸教派によって送り込まれた人たちだった。かれらが日本に来てみると、キリスト教徒が朝鮮戦争反対運動に参加し、クリスチャンの多くが共産主義とマルクス主義に寛容な態度で接しているのを目にして、ショックを受けた。
ほどなく保守派宣教師たちは、1940年代に来日した社会改革を大切にしてきた者たちと衝突し始めた。わたしは、“宗教右派”という言葉を初めて耳にするよりもずっと以前から、わたしの両親もそうだが、社会変革ならびに他宗教への寛容の重要性を強調する宣教師たちと、聖書を字義通りに解釈することを主張し、救われない魂は地獄行きが宣告されていると信じる団体との間に根深い対立があるとはっきり気づいていた。1950年代のことだが、極東福音十字軍、ナビゲーターズ(航海士たち)、新原住民宣教団といった珍妙な名前の教会から派遣されてきた原理主義派説教師たちが、イエス像とアメリカ国旗の絵で装飾した車で日本の田舎を巡回し、かれらなりの福音伝道に、共産主義の悪魔に対抗する好戦的教義をブレンド(調合)して宣教しているのを、わたしの父がからかって、おおいに楽しんでいたのをわたしは思い出す。
それから10年後には、宣教師社会でベトナム戦争が争点になり、社会改革派と反共福音主義者たちとの衝突が激発した。アメリカの軍事介入に対し、わたしの父などのリベラル派は反対し、原理主義者は支持した。日本のキリスト教団体も、ベトナム戦争およびアメリカの日本支配を争点に、保守派と急進派との軋轢で引き裂かれた。この紛争は、マッカーサーの協力を得て創設され、わたしの父が1960年代の大半を運営に捧げ、教壇にも立った学び舎・ICU(国際基督教大学)でとりわけ激烈をきわめた。
ここでわたしの家族の動向を言えば、4年間、日本を離れていた。先ず韓国に移り、次に父がジュネーブの世界教会協議会に赴任することになって、スイスで暮らしていた。1963年に日本に戻ると、わたしたちのICU生活は相変わらず平和で、ほとんど牧歌的と言ってもよかったが、それも66年までのことだった。その年、大学が採用した統一入学試験は、急進派および反体制派の排除を目的にしていると、急進派の学生たちが反発し、1年間にわたって大学構内を占拠した。だが決定的な動機は南ベトナム戦争反対であり、アメリカへの日本の協力、とりわけ日本国内の米軍基地の出撃拠点化である。この騒動が大学内部を2つのイデオロギー陣営に引き裂いたので、財務運営にかかわる大学幹部職員でありながら、戦争のことでは、学生側に同調していた父の生き方は惨めなものになった。
1969年2月、ふたたび学生たちがキャンパスを占拠した。今回は、67年に退学処分された3名の学生の復学を大学が拒否したことに対する抗議行動である。この騒動はカリフォルニア大学バークレー校やコロンビア大学の紛争とは共通点があまりなく、むしろ中国の文化大革命に近かった。70年になって、大学当局が機動隊の学内導入を強行して、占拠に終止符を打つまで、この紛争は続いた。
わたしの両親をはじめ大学関係者家族にとっては、学内ストライキは悲しかったが、わたしには、大学構内にひるがえる赤旗と毎日の反戦デモは刺激でもあり、楽しみだった。紛争の絶頂期、わたしは大急ぎでハイスクールから帰ったものである。“大衆団交”あるいは“拡大闘争集会”と呼ばれる学生たちの武勇伝の舞台は素晴らしい見物(みもの)だった。ふだんは講義や映画に使われていた講堂で、不人気な教官たちの模擬裁判が演じられていたのである。壇上の一方には、所属左翼セクトを表すヘルメットをかぶったストライキ指導部が陣取り、他方には、表情険しく、不安の隠せない教官たちが座らされていた。学生たちは教官をひとりずつ呼び出して、演壇に立たせ、これこれの罪を犯したと総括せよと問いつめた。返答が気にいらないと、かれらは英語で「ナンセンス、ナンセンス」と叫んだ。終幕に、学生たちは男も女も一緒に、鮮やかな赤い旗の前で、腕を組み合い、声を張り上げて『インターナショナル』を歌った。ある意味で、1950年に引かれた政治路線がほんとうに消えることは決してなかった。
―――――――
教団の戦責告白
―――――――
東京オリンピック開催の年である1964年が、アメリカの宣教活動の頂点だった。この時点で、教団と通称される日本キリスト教団に対する外国代表業務を管理していたインターボード(教派海外宣教部連合委員会)には、1355名の宣教師が登録されていた。その後、日本に滞在する宣教師の数はしだいに減少することになるが、その要因は、主として日本の教会側の事情にあった。53年から92年まで日本で仕えたメソディスト教会の元宣教師デーヴィッド・スウェインによれば、日本のクリスチャンの多くが、情緒と金銭の両面で、自分たちはアメリカの教会への不健康な依存を育んでしまっていると感じ始めていた。
現在、スウェインは隠退し、ノースカロライナ州に住んでいるが、数年前、東京でわたしに会った時、「初めに来た宣教師のだれもが、まったく無力な人びとの庇護者になったのです」と語った。「かれらを庇護者として見る色眼鏡を、日本人は外すことができなかったのです」 その色眼鏡のせいで日本人とアメリカ人キリスト教徒の間に“親・子関係”が成立してしまい、日本人がアメリカの信仰仲間との違いを言葉で表し、あるいは行動で示すことが難しくなったとかれは言った。
だが1950年代末期になると、この状況も変わってきた。そして60年代末期には、これが分裂騒ぎにまで拡大した。日本の教会とアメリカの後援者との露骨な紛争のひとつが69年に持ち上がった。その年、保守的なミズーリ・ルーテル教会から派遣されていた宣教師たちの全員が、日本人教会員たちからの圧力を受けて離日をよぎなくされた。いくつかの話を総合すれば、その理由は、日本人牧師が日本人会衆を引き継ぐのをアメリカ側の教会が拒んだことにかかわっている。
日本のキリスト者が独立を求めて努力するようになる転機をもたらしたものは、日本の教会の戦争責任をめぐる内部の論議だった。かつて教会は総じてファシズムや軍国主義の障害にはならなかった。朝鮮、満州、台湾植民地で、日本の教会が派遣した宣教師たちは日本企業や軍隊と協力して活動することが多かった。1941年に軍事政権の指令を受けて、日本キリスト教団が組織された。戦時中、教団の首脳たちは伊勢神宮に詣でて戦勝祈願をした。その時は、そういう行事に参加しなければ、教団は解散を命じられ、地下に潜るしかなくなっていたと教団幹部たちは(戦後になって)弁明した。(スウェインもわたしに指摘したが、それは本当だった。例えば、ファンダメンタルな傾向を持っていた教団内の旧ホーリネス教会系の牧師の多くが、国家行事の式典への参加を拒んで、投獄されている)
だが、帝国主義体制に組み込まれたことによって、教会は戦争犯罪の連座責任という負の遺産を背負うことにもなった。それは、日本軍に踏みにじられた国ぐにでは忘れられることがないものだった。そこで教会はみずからの罪を認めた。1966年、何ヶ月も内部で論議を重ねた結果、(アメリカの主流教派の合同したものに相当する)日本の教団は『第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白』を公表し、教団が軍部に協力したことを認め、第2次世界大戦の傷でいまだに苦しむ韓国、フィリピン、その他諸国の闘うキリスト者と連帯して働くことにより、過ちを償うと誓約した。告白は「背中にしがみつく猿を振り捨てるようなものです」と、スウェインは言った。「告白は解放の行為なのです」
教団は、同時併行して、海外からの宣教資金を削減し、教団事業をアメリカの教会機構から切り離す10ヶ年計画を開始した。1970年代初期からは、日本に宣教師たちが派遣されるのは、日本側からの個別の要請にもとづくものだけになり、アメリカの教会も、交替要員がいなくても、配下の宣教師が退任するのを認めるようになった。現在、アメリカの主流派教会から派遣されている宣教師の数は100人以下に減っている。
だが空いた場所を塞ぐかのように、原理主義的なセクトの福音派グループが増殖し、それに、白シャツとネクタイのモルモン教の若い男性たちは、ワシントン州のわたしの故郷の町でもそうだが、東京の市街地でユビキタス(偏在=どこにでもあるもの)であるかのように見かけられるになった。
――――
東京再訪
――――
母が亡くなる数年前のことだが、わたしは両親と一緒に東京に2週間滞在し、なつかしい盛り場を歩きまわった。1969年を最後に離日してから、3人揃っての日本旅行はこれが始めてだった。
ある雨の午後、東京にいたころ、長年つきあっていたクリスチャン家族である佐藤さん宅を、わたしたちは訪問した。昔の想い出を語り、2家族一緒の昔の写真を見て笑い、1993年に亡くなった家長へのお悔やみを述べて、一家を慰めた。社会人生活のかなりの期間を、東京都の委託で、外国人男性と結婚した日本女性のカウンセラーとして捧げてきた佐藤さんの未亡人は、夫の葬式について話しながら、クスクス笑った。かのじょが言うには、一家は自宅で葬儀を執り行うことになり、東京南郊の近隣の人びとを多く招いた。ところが後ほど、何人かの隣人たちが、葬儀場が教会でなくてありがたかったと打ち明けた。教会では“肩が凝る”と言ったのである。「そんなことをあの人たちはあけすけに言ったのです。あたりまえでは言えませんわ」と、かのじょは評した。
このエピソードは、日本におけるキリスト教にまつわる自明の理を浮き彫りにしている。年月を重ねると教えが浸透するとしても、キリスト教という宗教はいまだに異国のものだと考えられている。仏教は中国人によって伝えられ、または人によっては朝鮮人が伝えたと言うが、今でも日本人の生活に深く溶け込んでいる。神道もそうであり、第2次世界大戦中に享受していた国家護持の地位を回復しつつある。“アウトサイダー”の地位がキリスト教の影響力の限界を決めている。キリスト教はいまだに人口の1パーセントの半分の信徒しか獲得していなくて、これは1945年の水準と同じである。[訳注:前出と同じ]
これは、アメリカの伝道侵略が失敗だったことを意味するのだろうか? 数だけ見れば、たぶんそうだ。おそらくマッカーサーとかれの宗教顧問は日本人の精神的支えを渇望する心情を読み違えたのだろう。後の世代のアメリカ人ビジネスマンたちも、ほぼ同じように自由市場風味の資本主義に対する日本人の好みを見落とすだろう。
だが、日本社会におけるキリスト者自身の位置づけにも、障害があるかもしれない。無学な労働者の出身であり、第2次世界大戦中は共産主義者として投獄され、後にクリスチャンになった経歴を持つ椎名麟三(りんぞう)は、日本のクリスチャンの大半はインテリまたは上流階級の出身であり、貧しい労働者階級が主体である一般大衆と交流することがまったくできなかったと1959年に書いている。「日本のキリスト教は労働者と大衆に直接語りかける言葉を持ちあわせたことがなかった。…… 言いかえれば、日本におけるキリスト教は少数のインテリ階級の所有物であった。このような不名誉を日本のキリスト教は一掃するつもりが今までなかったと言っても間違いではないだろう。……キリスト教は今日の日本社会の表面に根無し草のように漂っていると言ってもいいだろう」
その反面、教会は日本の国家体制の外部にある組織であって、虐げられた人びとの声として、また、クリスチャンとその他を問わず、政治の主流から外れた反体制派の避難所として、重要な役割を担っている。キリスト者の諸団体は、在日朝鮮・韓国人たちと、増え続けるアジアからの移住者たちの権利を擁護する闘いの最前線に立ってきた。日本のキリスト者は、日本共産党と並んで、右翼と保守政治家が国粋主義の道具として利用してきた天皇制への揺るぎない批判者でありつづけている。キリスト者は、しばしば首相が戦死者の追悼のために参拝する靖国神社のような国家神道の残映を日本政府が露骨に利用することに反対してきた。キリスト者女性グループは、国内の被虐待女性たち、それにフィリピンなどから風俗産業に送りこまれ、やがて強制的に売春させられる出稼ぎ女性たちのためのホットラインを開設してきた。なによりも大勢順応が尊ばれる国にあって、キリスト教共同体は決定的な役割を果たしていると多くの左翼系政治活動家たちがわたしに語っている。
これらすべてが重要な貢献であり、仏教徒の感性、効率性の才能、外界への生得の関心と併せて、日本を、文化、政治、文学の途方もない豊かな水脈に恵まれた、平和でダイナミックな社会に変えるのに役立ってきた。マッカーサーがキリスト教の建設的な特質はアメリカ独自のものであると主張しようとした事実は傲慢と思いあがりを浮き彫りにしていて、それが現在も、アメリカの岸辺から遠く離れた、もうひとつの傷つき敗北した国の、燻(くすぶ)りつづける焦土を哨戒するアメリカ陸軍の姿に反映している。
—————————————————————
[附録] 原文サイト掲載写真のキャプション(URLは掲載ページ)
1頁 http://www.killingthebuddha.com/dogma/red_flags.htm
(上) 1948年、皇居前広場で行われた米従軍牧師主催の復活祭礼拝式。
(右) 1947年8月23日、日本に到着したショーラック夫妻。後ろの木箱には、食料品1トンと全所有物。日本は食糧難だったので、宣教師が入域許可を得るには、1年分の食品を携行することが占領軍当局から求められた。2頁 http://www.killingthebuddha.com/dogma/red_flags2.htm
(上) 1945年8月9日、長崎に投下された原爆で破壊された工場。
(下右) 食べ物を求め、サツマイモを集める母子。3頁 http://www.killingthebuddha.com/dogma/red_flags3.htm
(上) 1948年元日、晴れ着の男の子と女の子。45年春の米軍大空襲で破壊された自宅の跡地に廃材とブリキ板で建てられた家の前で。
(右上) 横浜。アメリカの教会から日本へ寄贈された乳牛を積んだ船の到着を待つ筆者と父。
(右中) 不機嫌そうな筆者。保育園の記念写真。
(右下) 木炭燃料のバス。1947年撮影。戦後初期には、ガソリンが欠乏し、高価だったので、木炭を動力源にする自動車とバスが多かった。
4頁 http://www.killingthebuddha.com/dogma/red_flags4.htm
1947年の東京下町。赤旗を振る共産党員・鉄道労働者たちのストライキ。
5頁 http://www.killingthebuddha.com/dogma/red_flags5.htm
1967-68年の学生ストライキ。国際基督教大学内の教会十字架の上に翻る赤旗。
6頁 http://www.killingthebuddha.com/dogma/red_flags6.htm
(上) 米従軍牧師から日本の信徒会衆に提供された米陸軍兵舎を改装した教会。米軍空襲で破壊された元の教会の残骸が見える。
(右) 筆者、姉、母、弟たち、ショーラック家のメイドだったタイコさん。
————————————————————
[筆者] ティム・ショーラックは米メリーランド州シルバースプリング在住のフリーランス・ジャーナリスト。アジア、グローバル化、アメリカ対外政策について、ネーション誌をはじめ米内外の刊行物に寄稿。現在、ショーラックは、戦後の日本と韓国に滞在した宣教師家族の子どもとして育った体験にもとづく書物を執筆中。同書の日本語版刊行を希望。
[筆者謝辞] 本稿の執筆にあたり、筆者の父ハラム・C・ショーラックは着想を与え、写真を提供してくれた。デーヴィッド・スウェインからは有益な助言をいただいた。筆者はおふたりに感謝の意を表明する。
—————————————————————–
[原文] Red Flags and Christian Soldiers
Tim Shorrock, Killing the Buddha, 2003
http://www.killingthebuddha.com/dogma/red_flags.htm
Copyright C2003 Tim Shorrock [TUP配信許諾済み]
=================================================================
翻訳:井上 利男 監修: 岸本 和世 / TUP