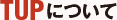━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『世界』7・8月号に掲載された、シーモア・ハーシュによるソンミ村大虐殺記事の邦訳の後半です。前半は以下をご覧ください。
速報988号 シーモア・ハーシュ:犯行現場(上)――ソンミ村大虐殺再訪
https://www.tup-bulletin.org/?p=2894
(前書き・翻訳:荒井雅子/TUP)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
犯行現場(下)――報道記者がソンミ村と隠された過去を訪れる
シーモア・ハーシュ
ベトナム中部ダナンは人口約一〇〇万のビーチリゾート・港湾都市だ。ある朝私はここで、ヴォー・カオ・ロイとコーヒーを飲んだ。ロイは、B中隊によるミケ第四地区襲撃の数少ない生存者の一人だ。当時一五歳だったと、ロイは通訳を通じて言った。ヘリコプターが村に近づく音がしたとき、母親は「いやな予感」がした。一帯では以前も作戦が行われたことがあった。「米兵は数人でふいに姿を現すというようなことはなかった」とロイは言う。「来る前に砲撃したり地域を爆撃することが多く、その後で地上軍を送り込んできた」。米軍と南ベトナム軍の部隊はこの地域を何度も通っており、それまで何事もなかったが、このときは、ロイは襲撃のほんの少し前に母親に追い立てられて村を出た。二人の兄はベトコンとともに戦い、一人が六日前に戦死していた。「私が一人前になりかけていたので、村にいると、殴られたり、南ベトナム軍に無理やり取られるかもしれないと母は心配したのでしょう。私は五〇メートルほど離れた川に向かいました。近い、十分近かった。銃撃と叫び声が聞こえました」。ロイは日が暮れるまでそこに隠れ、それから家に戻って母ら家族を埋葬した。
二日後、ベトコン部隊はロイを西部の山中にある司令部に連れて行った。ロイはまだ戦闘年齢ではなかったが、クアンガイ省全域を行動範囲とするベトコン戦闘部隊の前に連れて行かれ、米軍がミケ地区で何をしたかを話すよう言われた。ゲリラ軍の戦闘意欲をかき立てるためだ。ロイはその後ベトコンに加わり、戦争が終わるまで軍司令部で働いた。米軍の偵察機と部隊は、ロイの部隊を常に捜していた。「米軍の接近を察知するたびに司令部を移動した」とロイは言う。「司令部で働く者はだれでも、絶対の忠誠が必要だった。司令部内には三重の境界線があった。外側は物資提供者用、真ん中は整備と兵站(へいたん)、内側は指揮官。内側には師団指揮官しか入れない。指揮官は、司令部を離れるときは、人にわからないよう一般兵士と同じ服を着た。それで近くの村に入っていく。米軍は、師団幹部を殺したこともあったが、だれだったかを知らなかった」。米軍と同様ベトコン幹部も、殺害した敵戦闘員の数を水増しして兵士を鼓舞することがよくあったと言う。
ミライ地区とミケ地区の惨たらしい大虐殺は、反米戦争への支持を高めたとロイは言った。米軍司令部がなぜこのような戦争犯罪を許したかわかるかと尋ねると、わからないと答えたが、ベトナム中部の米軍指導部のあり方について厳しい見方をした。「米軍将官は兵士の行動の責任をとるべきでした」とロイは言う。「兵士は命令を受けている。彼らは義務を果たしていただけです」
ロイは今も家族を悼み、大虐殺の悪夢を見ると言う。ただ、ファン・ターン・コンと違って、ロイには家族代わりがすぐ見つかった。「ベトコンにかわいがってもらい、面倒を見てもらった。育ててもらいました」。コンがケネス・シールに怒りを隠さなかったことを話すと、ロイは「だれかに酷いことをされても、赦すことはできる。そして未来に向かって進むのです」と言った。戦後、ロイはベトナム正規軍に編入。大佐まで昇進し、三八年間勤務した後、引退した。今はダナンで妻と喫茶店を営む。
ベトナムでは人口の七〇パーセント近くを四〇歳以下が占める。ベトナム戦争は主に上の世代に今もしこりを残しているが、米国人観光客はベトナム経済に恩恵をもたらす存在だ。米軍GIには確かに残虐なことをされたが、まあ、戦争となればフランス軍だって中国軍だって同じことをやってきた。外交上、米国は友邦として、中国に対抗する潜在的同盟国として見られている。ベトナム戦争中に米国人と協力・協働したベトナム人のうち、一〇万人以上が一九七五年に米国に逃れた。共産党支配下のベトナムは汚職がはびこり、政府による厳しい検閲が行われるなど多くの弊害があるにもかかわらず、子ども世代の一部は、親の当惑を押し切ってベトナムに戻っている。
グエン・クイ・ドゥックは五七歳。ハノイで人気のバー・レストランを経営する作家、ジャーナリストだ。一九七五年に一七歳で米国に逃れ、三一年後に戻ってきた。サンフランシスコで、ジャーナリスト、ドキュメンタリー映画作家として賞も取ったが、「ベトナムに戻って暮らしたいとずっと思っていました。一七歳で国を離れ、米国で別の人間として暮らして、やり残したことがある気がしていた。米国で恵まれた機会に本当に感謝していますが、共同体の感覚というものに焦がれていた。ナショナル・パブリック・ラジオの記者として初めてハノイに来て、この街に夢中になりました」
戦争中の米軍の非道について、多くのベトナム人と同様、起きたことは起きたこととして受け止めることを学んだ、とドゥックは私に言った。「米軍兵士は残虐な行為をした。でも戦争ではそういうことが起こるものです」と言う。「そしてベトナム人が戦争中の自らの非道と向き合うことができていないのも事実です。私たちベトナム人には一つの割り切りがあります。必要とする味方を得られるなら、凶悪な敵だったことは忘れておくのがいい、と」
ドゥックの父グエン・ヴァン・ダイは、戦争中、南ベトナムで副知事を務めていた。一九六八年にベトコンに捕えられ、一九八〇年まで獄中にあった。一九八四年ドゥックは、米外交官の後押しもあって、両親のカリフォルニア移住の請願にベトナム政府から許可を得た。父親には一六年間会っていなかった。空港で到着を待っていたとき不安だったと彼は言う。父親は中国国境に近い共産党の収容所で独房に監禁されて大変な苦難を経験していた。手足を動かすことすらできないことも多かった。父は車椅子に乗っているだろうか、精神的に不安定ではないだろうか。父親の渡米は、ちょうど民主党の大統領予備選挙の最中だった。飛行機を降りてきた父は息子に挨拶して言った。「ジェシー・ジャクソンはどうだ?」 父親はソーシャルワーカーの仕事に就き、一六年生き長らえた。
***
ベトナム戦争帰還米兵の中に、再びベトナムに渡って住んでいる人たちがいる。チャック・パラッツォはニューヨーク、ブロンクス区のリトル・イタリーで問題家庭に育ち、高校中退後に海兵隊に志願。一年間の訓練を終えて一九七〇年秋、精鋭偵察部隊に配属された。部隊の任務は諜報を確認し、敵のミサイル発射施設と戦闘部隊に夜襲をかけることだった。部下とともに銃撃戦のただ中にパラシュート降下していくこともあった。「多くの北ベトナム正規軍ともベトコンとも激しい戦闘をたくさんやって、戦友を大勢亡くした」。現在、生活と仕事の場にしているダナンで、杯を傾けながら彼は言った。「でもまだここにいるうちに戦意は失せた。本を読み始め、戦争の政治を理解するようになった。上官の一人は、ベトナムで自分たちのやっていることは間違いであり無意味だと自分も思うと、内輪話では言っていた。上官はこう言った。”気をつけろ、さっさと逃げ出せ”」
一九七〇年、チャーター機で初めてダナンに着陸したとき、飛行場に並べられた棺が目に入った。「そのときになって初めて、戦争の真っただ中にいるんだと実感した」とパラッツォは言う。「一三カ月後、またダナンで今度は帰国便に乗るために並んでいたが、搭乗者名簿に名前がなかった」。押し問答の末、「その日帰国したいなら、C-141貨物機で米国に運ばれる棺の一団の付き添いをするしかないと言われた」。彼はそうした。
海兵隊を除隊後、パラッツォは大学の学位をとり、IT専門家として仕事を始めた。しかし多くの帰還兵同様、彼もPTSDを抱えて「娑婆に戻って」おり、依存症と闘っていた。結婚は破綻した。何度も職を転々とした。二〇〇六年、パラッツォはホーチミン市に戻るという「自分勝手な」決断をした。「PTSDとどう付き合い、自分の亡霊とどう向き合うかということだけだった」と彼は言う。「来てみたら一ぺんでベトナムの人たちに惚れ込んだ」。パラッツォは、オレンジ剤の犠牲者のために力を尽くしたいと考えた。退役軍人省は長年、証拠の不確かさを理由に、オレンジ剤にさらされた人の多くが抱える癌などの病気とオレンジ剤との関連を認めようとしなかった。「戦争中、中隊長は蚊取りスプレーだと言ったが、木や植物が一面枯れているのが見えた」とパラッツォは言う。「米軍帰還兵がいくらかでも援助や賠償を受け取っているなら、ベトナム人も受け取っていいはずだと考えた」。二〇〇七年にダナンに移り住み、現在はITコンサルタントをしながら、米国の反戦NGO「ベテランズ・フォー・ピース(平和をめざす帰還兵の会、VFP)」の地元支部代表を務める。枯葉剤の持続的影響に対処するために国際支援を求める「オレンジ剤アクション・グループ(AOAG)」でも積極的に活動している。
ハノイでは、チャック・サーシーに会った。長身で白髪の七〇歳、南部ジョージア州の出身だ。父親は第二次世界大戦中バルジの戦いでドイツ軍の捕虜になっており、サーシーにはベトナム行きを忌避しようという考えは夢にも浮かばなかった。「ジョンソン大統領と議会は米国がベトナムで何をしているかわかっていると私は思っていた」と言う。一九六六年、大学を辞めて志願。サイゴン空港近くに配備された、軍の分析・報告の処理・評価を行う部隊で諜報分析官となった。
「ジョージアの愛国少年としてもっていた理想は三カ月ですべて粉々になり、米国という国は何なのだろうと疑問に思い始めた」と彼は言う。「私が見ていた諜報は、知性を駆使した大きな嘘だった」。南ベトナムは米軍の渡す諜報を重く見ていなかったらしい。あるとき同僚がサイゴンの市場で魚を買うと、所属部隊の機密報告が包み紙にされていた。「一九六八年六月にベトナムを去るころには、怒りとやり切れなさを抱えていた」
服務をヨーロッパで終え、家に帰ると大変なことになった。「私がベトナム戦争の話をしても父は信じなかった。共産主義にかぶれたか。父は、自分も母も”おまえがだれかわからなくなった。おまえは米国人じゃない”と言った。それから両親に家を出て行くように言われた」。サーシーはジョージア大学に戻って卒業し、ジョージア州アセンズで週刊紙の編集をした。その後、政治・公共政策の仕事に移り、ジョージア州選出民主党下院議員ウィチェ・ファウラーの補佐官も務めた。
一九九二年、サーシーは再びベトナムを訪れ、その後、すでに移り住んでいた数人の帰還兵に加わることを決断した。「一九六八年にベトナムから飛び去るとき、いつか、何かの形で、戻ってくるだろうとわかっていた。願わくば平和なときに。その当時でさえ、ベトナム人をとてつもなく悲劇的な運命の中に置き去りにしていると感じていた。そうなったのは私たち米国人に最大の責任がある。その感覚はいつもどこかに残っていた」。サーシーは不発弾・地雷除去プロジェクトに取り組んでいる。米国は、重量にして、第二次世界大戦中に投下した爆弾の三倍をベトナムに投下した。戦争終結から一九九八年までに、一〇万人以上のベトナム民間人――その四〇パーセントが子どもと推測されている――が不発弾の暴発によって殺傷された。米国は戦後二〇年以上、爆弾やオレンジ剤による被害の補償を拒んでいたが、一九九六年から不発弾・地雷除去にわずかな資金を拠出するようになった。二〇〇一年から二〇一一年にかけて、「ベトナム帰還兵記念基金(VVMF)」もサーシーの不発弾・地雷除去プロジェクトに資金援助を行った。「多くの帰還兵が、自分たちも何らかの責任を引き受けるべきだと感じている」とサーシーは言う。プロジェクトは、ベトナム人、特に農民や子どもに不発弾の危険性を伝える活動を行っており、死傷者は減っている。
早くから戦争の実態に気づいたサーシーだが、戦争終結の少し前にわかってもらえたと言う。父親からコーヒーでもどうかと電話があった。家を出るよう命じられて以来のことだった。「父と母はいろいろ話をしたようだ」と彼は言う。「父は、”お前が正しくて私たちが間違っていたと思う。帰ってきてほしい”と言った」。サーシーはまもなく家に戻り、両親が亡くなるまでずっとそばにいた。二度離婚しており、「もう一度結婚させようとするベトナム人のお節介に抵抗中」と、おどけたメールが来た。
ベトナムで知るべきことはまだあった。一九六九年初め、C中隊隊員の大半は帰国するか、他の戦闘部隊に配属替えされていた。隠蔽は成功していた。ただそのころ、ロナルド・ライデンアワーという勇気ある米軍帰還兵が、「暗く血塗られた」大虐殺について詳細な手紙を書き、三〇人の政府官僚と下院議員に郵送していた。数週間のうちに、手紙はベトナムの米軍司令部に届いた。
今回ハノイを訪問したとき、政府官僚に勧められて、ソンミ村に向かう前に、クアンガイ市にあるクアンガイ省庁を表敬訪問した。そこで、新しく出版された省のガイドブックを見せてもらった。その中に、ベトナム戦争中、クアンガイ市外のトルオン・レ地区で米軍が行ったという、もう一つの大虐殺の詳細な記述があった。報告によれば、索敵掃討作戦を行っていた米軍小隊が一九六九年四月一八日朝七時にトルオン・レに到着した。ソンミ村事件から一年余り後になる。兵士は女性と子どもを家から引きずり出して、村を焼き払った。報告はさらに続く。兵士は三時間後にトルオン・レに戻り、四一人の子どもと二二人の女性を殺害した。生き残ったのはわずか九人だった。
ソンミ村の後も何も変わっていなかったようだ。
***
一九九八年、ソンミ村大虐殺三〇年を迎える数週間前、私は、引退した国防総省官僚W・ドナルド・スチュワートから、一九六七年八月付の未公表の報告書のコピーを渡された。報告は、南ベトナムにいる米軍部隊の大半が、ジュネーブ条約の定める軍の責任を理解していなかったことを示していた。スチュワートは当時、国防総省の査察局調査部のチーフだった。報告書は、ケネディ、ジョンソン両大統領の国防長官だったロバート・マクナマラの要請で準備されたもので、数カ月かけて米国内や南ベトナムに足を運び、数百のインタビューを行ってまとめられた。この報告によれば、インタビューされた兵士の多くは「ジュネーブ条約の明文条項の代わりに、自分自身の判断に基づいてかまわないと感じていた。……[国際法について]説明を受けたばかりにもかかわらず、捕虜を虐待・殺害すると発言したのは主に、若く経験の乏しい部隊だった」。
マクナマラは一九六八年二月に国防総省を去り、報告書はついに日の目を見ることはなかった。スチュワートは、報告がなぜ封印されたかわかると、後に私に話した。「米国民は大事な一八歳の若者たちを送り出していた。その若者たちが耳を切り落としていることを、われわれは国民に知られたくなかった。私は、南ベトナムから戻ってくるとき、事態が手に負えなくなっていると思った。……[ソンミ村大虐殺を指揮した]カリーのことがわかった――本当によく」
実はロバート・マクナマラもわかっていた。一九六九年の終わり近くにミライ地区についての記事を書いていたとき、私はスチュワート報告のことは何も知らなかったが、マクナマラがベトナム中部での血塗られた蛮行について私の報道より二年以上も前に知らされていたことを聞いた。ミライ地区に関する一本目の記事が掲載された後、『ニューヨーカー』誌の若手記者ジョナサン・シェルから電話があった。シェルは一九六八年に、クアンガイ省と隣の省への絶え間ない爆撃について、同誌に圧倒的な記事を書いていた。(シェルは昨年世を去った。)後に『The Military Half (仮訳:軍事側の半面)』という本になったシェルの記事が示していたのは、基本的にはこういうことだ。米軍はベトコンがベトナム中部で基盤を固め、十分な支持を集めていると認めざるを得なくなっており、そのためにミライ地区を含む地域で戦闘員と非戦闘員をほとんど区別していなかった。
一九六七年に南ベトナムから戻ったシェルは、自分が目にしたことに衝撃を受けていた。彼はニューヨークの名家の出であり、ウォールストリートの弁護士で美術愛好家の父親が避暑地マーサズ・ヴィニヤードに持っていた家の隣には、ジョン・F・ケネディ大統領の元科学顧問(科学技術政策局長)ジェローム・ウィズナーがいた。当時マサチューセッツ工科大学の学務担当副総長だったウィズナーは、北ベトナムによるホーチミン・ルート経由の南への軍事物資輸送を妨げることを目的とした”電子防壁”[音響・振動センサーでトラックなどの動きを感知する監視網]構築プロジェクトにも、マクナマラとともに関わっていた。(プロジェクトは頓挫した。)シェルがベトナムで見たことを話すと、やはり強い懸念を抱いたウィズナーは、シェルがマクナマラと話せるようお膳立てした。
まもなくシェルはワシントンでマクナマラに会い、自分が見たことを話した。記事にする前に政府に報告するのは気が進まなかったが、そうする必要を感じたとシェルは言う。マクナマラは会合を内密にしておくことで合意し、シェルの仕事を妨害することは一切ないと言った。マクナマラはまた、シェルが報告を口述できるよう、国防総省内に一室を提供した。口述筆記は二部作成され、マクナマラは、自分の分を使って、シェルが指摘した蛮行について調査を開始すると言った。
シェルの記事は翌年の早い時期に掲載された。マクナマラからその後連絡はなく、政策にも変化の兆しは何も現れなかった。そこへ私のミライ関連記事が出た。シェルは、すでに国防総省を去って世界銀行総裁に就任していたマクナマラに電話をした。そして、ソンミ村地域での米軍の残虐行為について詳しい記述を渡してあるはずだと迫った。このとき、マクナマラとの会合のことを書くべきかもしれないと考えていたと言う。マクナマラは、オフレコにすることで合意ができていたと言い、約束を守るよう念押しした。私はシェルから助言を求められた。もちろん記事を書いてほしかったが、もしシェルが本当にマクナマラとオフレコの約束をしていたなら守るしかないと彼に言った。
シェルは約束を守った。二〇〇九年、『ネーション』誌に書いたマクナマラ追悼記事で、マクナマラを訪ねた様子を明かしたが、異例の合意には触れなかった。追悼記事には、会合の一五年後にニール・シーハンから聞いた話が書かれている。シーハンは、UPI、『ニューヨーク・タイムズ』、『ニューヨーカー』の優秀な戦場記者で、『輝ける嘘』(菊谷匡祐訳、集英社、一九九二年)の著者だ。マクナマラは、シェルのメモを、駐サイゴン米大使エルズウォース・バンカーに送っていたという。マクナマラは知らなかったようだが、大使はシェルの指摘を調査するどころか、その報道の信頼性を貶め、ありとあらゆる手段で記事の掲載を妨害することを目論んだ。
ミライ関連記事が新聞に出た数カ月後、執筆中だった『ソンミ―ミライ第4地区における虐殺とその波紋』(小田実訳、草思社、一九七〇年)の抜粋が『ハーパーズ』誌に掲載された。抜粋では、何が起こったかを克明に描き、特に、大虐殺までの数カ月に、カリー少尉のいたC中隊の兵士たちがどのように人間性を奪われていったかを浮き彫りにした。マクナマラの二〇歳の息子クレイグは戦争に反対しており、電話をくれて、『ハーパーズ』誌を一冊、父親の居間に置いておいたと言った。その後暖炉の横に置いてあるのを見たと言う。マクナマラは公職を退いた後、核兵器廃絶運動を行い、ベトナム戦争で自らが果たした役割に赦しを得ようとした。一九九五年の『マクナマラ回顧録――ベトナムの悲劇と教訓』(仲晃訳、共同通信社、一九九七年)で、ベトナム戦争は「大失敗」(四二九ページ)だったと認めたが、ベトナムの人びとや[ソンミ村大虐殺にかかわった]ポール・ミードロのような米兵に及ぼした害について悔恨を示すことはほとんどなかった。「自分が成し遂げたことを非常に誇りに思っている。物事を達成する過程で過ちを犯したことは非常に残念だ」と、二〇〇三年公開のドキュメンタリー『フォッグ・オブ・ウォー――マクナマラ元米国防長官の告白』で監督のエロル・モリスに語っている。
国防長官時代の文書で機密解除されたものを見ると、マクナマラは、ジョンソン大統領への内部報告では戦争への疑念を繰り返し表明していたことが明らかになっている。しかし、公式には一度も疑問や悲観論を口にしなかった。クレイグ・マクナマラは、父親が死の床で「神に見捨てられたと感じると言った」と話してくれた。その悲劇はマクナマラ一人だけのことではなかった。(了)
原文
The Scene of the Crime
A reporter’s journey to My Lai and the secrets of the past.
By Seymour M. Hersh
The New Yorker, March 30, 2015 Issue
http://www.newyorker.com/magazine/2015/03/30/the-scene-of-the-crime