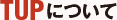「スパナを放り込んで戦争マシンを止めることができる人は限られている。素手よりもわずかに多くを持つなら、君には特別な役割があるはずだ」
反戦の歴史家、故ハワード・ジンは常々「小さな反逆」を人々に説いていた。そして反逆する多くの人々とつながる喜びについても頻繁に語った。そんな時、ジンはいつもいたずらっ子のような笑い顔だった。
素手よりもわずかに多くを持つ反逆者、ダニエル・エルズバーグ、ジュリアン・アサンジ、エドワード・スノウデン。そして無名の内部告発者たちがジンの系譜を踏み、今、新しい歴史を綴っている。
彼ら内部告発者の支援団体「報道の自由基金(https://freedom.press)」の理事の一人であるジョン・キューザックは、ロシアに亡命しているスノウデンをエルズバーグと共に訪れるというアイデアを思いついた時、ふと、もう一人の反逆者を誘うことにした。子供のような好奇心で本質に切り込むアルンダティ・ロイだ。
エルズバーグ、キューザック、ロイ、スノウデン、アサンジ。笑いと涙が交錯するこの反逆者の集いの記録を読みながら、ジンのあの嬉しそうな顔が脳裏をかすめた。
キューザックによる記録を4回のシリーズで配信します。
(前書き:宮前ゆかり、翻訳:荒井雅子・宮前ゆかり/TUP)

考えてみるべきこと:「米国ではISISについては話すことができるが、パレスチナについては話せない
エドワード・スノウデンに会いにいく―3
言えることと言えないこと(続き)
アルンダティ・ロイとジョン・キューザックの対話は続く。
ジョン・キューザック
————————————————————————————————–
次の週にかけて、手続きを計画しなければならなかった。急な話だったし、大騒動という感じだった。ロイは自分で手配したが、気になっていたのは、ソ連の先制攻撃が起きた場合の米国の反撃核攻撃計画者だったというダニエル・エルスバーグの経歴だ。つまり、エルスバーグはソ連を物理的に抹消する計画のために人生の二、三年ほどを過ごしたことがあったのだ。核兵器の秘密、ドミノ理論――彼はそういったことが語られた部屋にいたことがある。それに加え、市民の不服従運動で85回以上もの逮捕歴があり、そのうち一回はロシアで、ソ連の核実験に抗議するグリーンピースの船、シリウスに乗っていたときだった。しかし、ダンのヴィザは届いた。そして僕のも届いた。
その一方で、インドでは、ロイが最も怖れていたことのいくつかが現実になっていた。八カ月前に、ナレンドラ・モディがインドの新しい首相となっていた。(五月に、以下の携帯電話メッセージを受け取った:選挙の結果が出た。ファシストの地滑り的勝利。亡霊たちは実在する。見えたとおり、そのとおり)。
僕はロイとロンドンで会った。彼女はケンブリッジとサウスバンクで、ガンジーとB.R. アンベードカルに関する新しい著書について講演するために二週間滞在していたのだ。インドでは彼女の身代わり人形を火あぶりにしている人たちがいると、ロイはヒースロー空港でいかにもさりげなく僕に言った。「わたしはガンジー主義の人たちを暴力に煽り立てているらしいのよ。でも、わたしはあの身代わり人形の出来栄えにはがっかりしたわ」と彼女は笑った。
僕たちは一緒にストックホルムに飛び、ダンと合流した。ダンはライト・ライブリフッド賞――「もう一つのノーベル賞」とも呼ばれている――の授賞式に来ていた。スノウデンが受賞者の一人だったからだ。そこから皆で一緒にモスクワに飛ぶことになる。
ストックホルムの街並みは本当に清潔で、地面から物を拾って食べることができそうなくらいだった。
第一日目の夜、海事博物館で晩餐会があった。モダンな建築物のど真ん中に、17世紀*に難破した巨大な木造戦艦が一体丸ごと引き揚げられて展示されている。スエーデンの大惨事史上のタイタニックと考えられているワサ号は、海と未来の支配を欲する、権力に飢えた、またもう一人の王の命令によって建造された。この船は武器を積みすぎて上部が重過ぎ、港から出もしないうちに転覆して沈没した。
(*原文では16世紀となっているが、博物館ウェブサイトでは17世紀と記されている。)
それは、典型的な人権団体の夕べだったことは確かだ。グルメの食事と善意、合唱団が歌う美しいクリスマスキャロルの数々。ほとんど病的とも言えるほど祝宴が嫌いなロイが抑えきれないパニックを隠そうとしているのを眺めて楽しんだ。ロイの居場所ではない、ということなのだろう。ダンは忙しく引く手あまたで、人に会ったり、インタビューをしていた。時折、彼を見かけ、そそくさと挨拶を交わすことはできた。
授賞式はスエーデンの議会で行われた。ロイと僕は寛大にも招待を受けていた。僕たちは遅刻した。自分たちの国の議事堂にいるのも苦痛だというような二人がスエーデンの議事堂に座っているなんて一体どういうつもりなのだろう、ということに思い至ったのだ。そういうわけで、僕たちはちんけな犯罪者のように廊下をこそこそ歩き回り、そのうち儀式が見える狭いバルコニーを見つけた。僕たちの空っぽな席がよく見えた。演説は長かった。僕たちはそっと抜け出し大きな議事堂を歩いて通り抜け、祝宴のごちそうが並んでいる空の宴会場を見つけた。これにはなんらかの暗喩があった。僕はまたレコーダーのスイッチを入れた。
JC:政治の道具として慈善事業にはどんな意味があるんだろう?
AR:古い冗談よね?誰かをコントロールしたかったら支援しなさいと。または結婚しなさい。(笑)
JC:援助交際政治……
AR:抵抗運動を迎え入れ、捉え、金を出せ。
JC:飼いならせ……
AR:依存させろ。それを芸術プロジェクトや何らかの製品に変えろ。急進的だと考えていたものが組織化され資金提供される事業になってしまった途端、面倒なことになる。そしてこれは巧妙に行われるのよね。そのどれもが悪いわけでもなくて……正真正銘、良い仕事をしているところもあるのだけど。
JC:ACLU(米国自由人権協会)のようにね。
AR:彼らはフォード財団からお金をもらっているんでしょう? でも素晴らしい仕事をしています。ああいう人たちのやっていることを個々に見ると、責めることはできません。
JC:何か良いこと、役に立つことをやりたいと思っている……
AR:そうね。そしてそういう善意に無理を強いて仕事をさせるのよ。複雑ね。ビーズのネックレスを考えてみて。ビーズ自体はそれぞれきれいだけど、糸を通されると自由に素早く思いのまま動くことができなくなる。ざっと見渡して、どれほど多くのNGOが、例えばゲーツ、ロックフェラーやフォード財団の寄付リストに載ってるかを見ると、何かがおかしいはずじゃない?これらの財団は潜在的な急進主義者を、大盤振る舞いの寄付の受け手に変えてしまう――その後、とてもさりげなく、表向きはそのようには見えないけれど――急進的な政治の境界線の線引きをする。もし言うことをきかなければ首になる……首になったり、資金が打ち切られる。それに、「出資されている者」と「出資されない者」を争わせるゲームがあって、そこでは常に出資者が注目の的になる。もちろん、わたしは資金給付を受けている人たちに苦情があるわけではないんですけどね――だって選択肢がなくなりつつあるのだから――でも、わたしたちは理解していなきゃいけないと思うの――あなたは犬を散歩させているのか、それとも、犬があなたを散歩させているのか?犬は誰で、自分は誰か?
JC:僕は完全に犬だね……そして散歩させられている方だね、きっと。
AR:あらゆるところで――米国だけじゃなくて……そうできる相手なら誰でも弾圧し、叩きのめし、銃撃し、投獄し、それができない相手には金を投げつけてやる――そして少しずつ紙やすりをかけて角を取る。彼らは、インドの表現でパアルツ・シェール、飼いならされた虎という意味なんだけど、そういう存在を作り出す事業をやっているの。抵抗運動の真似事のようなもの……そうやって何も損害を与えることなくガス抜きができるわけね。
JC:最初に世界社会フォーラムで君が話したのは……いつだったっけ?
AR:2002年だったと思う、ポルト・アレグレ……米国によるイラク侵攻の直前。
JC:ムンバイだね。そして翌年、君が行ったら……
AR:完全にNGO化してしまってたの。主要な活動家の多くが旅行代理店の社員になってしまっていて、人々をあっちこっちに飛行機で移動させて、切符やお金の処理に追われるだけになってしまった。フォーラムは突然こう宣言した「非暴力のみ、武装闘争はダメ……」彼らはガンジー主義者になってしまった。
JC:ということは、武装闘争に関与している人々は皆……
AR:皆、排除よ、全面排除。急進的闘争の多くが排除された。なので、わたしはくそくらえ、と思った。わたしの疑問は、例えば、どこから行っても歩いて四日かかるような、森の奥の集落に住んでいる人々がいて、そこに千人もの兵士がやってきて、鉱山会社が欲しがっているからといって人々を住んでいる土地から追い払うために集落を焼き払い、人々を殺し、強姦する、としましょう――権力層の熱烈な支持者たちは一体どんな非暴力ブランドを推奨するのかしら? 非暴力は急進的政治劇場なのです。
JC:聴衆がいる場合にのみ有効……
AR:そのとおり。そして誰が聴衆を引っ張ってくることができるかしら? 資本、スターが必要でしょう?ガンジーはスーパースターでした。森の住人たちにはそのような資本、そのような引力はない。だから聴衆もいない。非暴力は戦術の一つであるべきなのであって――巨大な暴力の被害者に対し外野から説教するイデオロギーであってはならない。わたしにとって、それはこういった出来事を見ることで得られた進化なのです。
JC:君は消化酵素の臭いがしてきたぞ……
AR:(笑)でも、わかるかしら、革命には資金を提供できないの。本当の変化をもたらすのは、信託や基金組織の想像力ではないのです。
JC:じゃあ、僕たちが名前を挙げることのできる大きな策略とは何だろう?
AR:より大きな策略は、自由市場のために世界の安全を維持することです。構造調整政策、私有化、自由市場原理主義――これらすべてが民主制や法治主義になりすましている。企業基金の資金給付を受けているNGOの多くは――すべてではないけれども多くは――「新しい経済」の宣教者になっている。こういった組織は言葉を使ってわたしたちの想像力をあれこれいじくり回す。例えば「人権」という概念とか――時々とてもひっかかる。それ自体のことではなく、人権という概念が正義というはるかに高邁であるべき思想のすり替えになっているから。人権は基本的権利であって、最少限の権利、わたしたちが求める最もぎりぎりの権利です。あまりにも頻繁に、これが目標そのものになってしまっています。最少限度であるべきものが最大限――わたしたちが期待すべきことすべて――になってしまっているわけ。でも、人権だけでは十分ではない。目標は正義であって、常に正義でなければならない。
JC:人権という言葉は、赤ちゃんをなだめるおしゃぶりみたいなものになりうるね――正義が占めるべき政治的な想像力の空間を埋めてしまうのかな?
AR:例えば、イスラエルとパレスチナの紛争を見てご覧なさい。1947年から現在にいたるまでの地図を見ると、イスラエルが不法な入植地を使ってパレスチナの土地のほとんどすべてを丸呑みしてしまっていることが分かります。その闘いにおける正義について語るには、これらの入植地について話す必要がある。でも、単に人権についてだけ話すのであれば、「ハマスは人権を侵害している」「イスラエルは人権を侵害している」ということになる。それ故に、どちらも悪い、となる。
JC:同等であるかのように扱うことができる……
AR:……でもそんなものじゃない。一方で、この人権話はテレビ――素晴らしき残虐行為分析・糾弾産業(笑)――にうってつけね。この残虐行為分析でよい香りを漂わせるのは誰でしょうか?国家は暴力を合法化する権利を得るために自ら労力を費やしてきました――では誰が犯罪化され違法化されるのでしょうか?唯一――ああ、少し言い過ぎね――通常は、抵抗勢力です。
JC:ということは、人権という言葉が正義から酸素を抜いてしまう?
AR:人権は、正義から歴史を抜き取ってしまう。
JC:正義には必ず文脈がある……
AR:わたしはまるで人権を貶しているように聞こえるでしょうが、……そうじゃない。わたしが言わんとしているのは、正義という思想――単に正義を夢見るだけでも――それは革命的だということです。人権の言語は、本質的に不正な現状維持を受け入れる傾向があり、−−その後もっと責任を取らせようとする。でも、もちろん、人権の侵害は新自由主義と世界覇権プロジェクトにとってなくてはならない要素であることが逃れようのないジレンマなわけです。
JC:……暴力以外にはこのような政策を実践する手段はないので。
AR:まったく無理――でも、人権について声だかに話してさえいれば、民主制の実践、正義の実践という印象を与えることができる。米国が民主政権をひっくり返すために戦争を仕掛けた時があったけれど、当時は民主制は自由市場にとって脅威だったのです。各国が資源を国営化し、自国の市場を保護していた……そのため、本物の民主政権は転覆された。イランでも民主政権が転覆され、南米のあらゆる国で民主制が転覆された、チリ……
JC:リストは長すぎる……
AR:そして今、民主制は作業場に持っていって修理し、市場に好ましい形に改造されているという状況にある。今度は米国は民主制を取り付けるために戦争を戦っているわけ。最初は転覆するため、今は取り付けるためね?そして、現代の世界では企業が資金を供給するNGOが急激に増えていること、CSRという考え、企業の社会的責任――これはすべて新しい管理型民主政治の一部。そういう意味では、すべてが同じマシンの一部だというわけ。
JC:おなじイカの触手。
AR:「構造調整政策」が国に対し公共支出――保健、教育、インフラ、飲料水の供給――の節約を国に強いたときに空いた空間に、NGOが押し寄せてきたわけで、教育や医療などに対する人々の権利であったはずのことを、ほんの僅かな人々に開かれた慈善行為に変えてしまった。「平和」事業は時には「戦争」事業と同じくらい問題がある。これは国民の怒りを管理する手段のひとつです。わたしたちは皆管理されていて、それに気がついてさえもいない……最も不透明で秘密主義の組織であるIMFや世界銀行が「不正」と戦い「透明性」を求めるNGOに何百万もの資金をつぎ込んでいる。彼らは法治主義を求めているけれど、――それは彼らが法律を作ることができる場合だけ。世界資本が何の障害もなく流通できるように、IMFや世界銀行は状況を標準化するために透明性を求めている。人々を閉じ込め、金を自由にする。現在、世界中を――遮られることなく――自由に移動が許される唯一のものは、金……資本です。
JC:すべては効率のためでしょう?安定した市場、安定した世界……均一「投資環境」という考え方には強力な暴力がある。
AR:インドでは、それは「虐殺」と同じ意味で使う言葉。安定した市場、不安定な世界。効率。皆が聞く言葉です。いい加減、非効率賛成派で不正賛成派になりたくなるほど。(笑)でも冗談抜きで、南米のこと、そしてCIAの後ろ盾があったスハルト将軍によって百万人近くの人々、主に共産主義者たちが殺されたインドネシア、南アフリカ、米国の市民権運動における――今の米国でも――、フォード財団やロックフェラーの歴史を見るならば、とても憂慮すべきです。彼らは常に米国の国務省に親密に協力してきた。
JC:それでも、今フォード財団はこういった虐殺に関する映画「The Act of Killing」に資金を出している。彼らは殺し屋たちを紹介しているけど、殺し屋たちの主人については描いていない。彼らは金の出所を追求しようとしない。
AR:彼らはものすごくお金があるので、とても悪いことと同じように非常に良いことまで――ドキュメンタリー映画、核兵器計画者、ジェンダー権利、フェミニストのコンファレンス、文学や映画祭、大学教授の職……「市場」や経済の現状維持を揺るがさなければ何でもあらゆることに資金を提供している。フォードの「よい仕事」のひとつは、CIAと密接に協力していたCFR、つまり外交問題評議会に対する資金提供だった。1946年以降、世界銀行の総裁は全員がCFR出身です。フォードは米国軍と密接な関係にあるRAND、ランド研究所にも資金を出していた。
JC:それはダンが仕事をしていたところだね。そこでダンはペンタゴン・ペーパーズを手に入れた。
AR:ペンタゴン・ペーパーズ……読みながら信じられなかった……ダムを爆撃したり、飢饉を計画したりなどの内容……わたしはペンタゴン・ペーパーに関する分析もあるノーム・チョムスキーの著書「国家の理由(仮題)」改訂版に序文を書いたのです。その本に「バックルームボーイズ」という章があって、もしかするとペンタゴンペーパーズの部分ではなかったかもしれない、覚えていないけど……それには、多分現場の兵士から送られてきた手紙かなんらかのメモがあり、それは白りんをナパームに混ぜたことがいかに素晴らしいことかが書かれてあった……「それは糞が毛布にくっつくように、グック(東洋人の蔑称でベトナム戦争中に多用された)にくっついて骨まで奴らを焼く」。焼夷弾を落されたベトナム人が身体の肉が燃えるのを止めようとして水に飛び込んでも白りん弾が燃え続けたことを兵士たちは喜んでいた……
cf. ロイの序文: http://www.countercurrents.org/us-roy240803.htm
JC:君はそれを暗記で覚えているの?
AR:忘れることはできないわ。わたしも骨まで焼かれたの……わたしはケララ州で育ったの、思い出して。共産主義の州よ……
JC:フォード財団がいかにランド研究所と外交問題評議会に資金提供しているか、って話をしてたよね。
AR:(笑)そうだった……お色気笑劇よ……本当はお色気悲劇なんだけど……そういうジャンルある?フォード財団は外交問題評議会とランド研究所に資金を出した。ロバート・マクナマラは、フォード自動車の社長から国防総省に移った。だから、見ればわかるとおり、わたしたちは取り囲まれている。
JC:……それは過去の話だけじゃない。
AR:そうじゃない――未来も。未来はグーグルでしょ?ジュリアン・アサンジは、著書『When Google Met WikiLeaks』――優れた本――の中で、グーグルと米国家安全保障局(NSA)の関係はあまり明るみに出されていないと示唆している。グーグル社長エリック・シュミットと一緒にアサンジをインタビューした三人は、一人目がジャレッド・コーエン、シンクタンクのグーグル・アイデアズ代表で、元米国務省官僚で外交問題評議会の上級何とかで、コンドリーサ・ライスとヒラリー・クリントンの顧問。あとの二人はリサ・シールズとスコット・マルカムソンで、やはり元米国務省・外交問題評議会関係者。これは重大なこと。でもNGOの話をするときには気をつけなくてはいけないことがあって……
JC:どんなこと?
AR:NGO攻撃が正反対の方、極右から来るときには、まったく違う視点からNGOを批判しているわたしたちが酷い人間に見えてくる……リベラル派にとってわたしたちは悪者になる……
JC:またしても「資金提供を受けている者」と「受けていない者」を敵対させるわけだ。
AR:たとえば、インドの新政府――インドを「ヒンドゥー国家」にしたがっている過激なヒンドゥー右派――は偏見の塊。人殺したち。虐殺は彼らの非公式な選挙戦で、地域社会を分極化させ、票を取り込むために画策されている。二〇〇二年のグジャラトでそうだったし、今年、総選挙前に、ムザファルナガルというところでもそうで、虐殺の後、何万ものムスリムが自分の村を逃れてキャンプで暮らさなければならなかった。これらの殺人の罪を問われた人間の中に、今閣僚になっている人びとがいる。彼らの臆面もない威圧的な殺人への支持を見ると、人権話という偽善にすらほど遠いと感じさせられる。でも今、「人権」NGOが騒いだら、あるいはささやき声が大きすぎるだけでも……この政府は活動を停止させるだろう。いともたやすいこと。資金提供者を探し出しさえすればいい……資金提供者はだれであれ、特にインドの巨大「市場」に興味を持っている者なら、屈服するか、ほうほうの体で反対方向へ逃げていく。こういうNGOが姿を消すのは、それがキメラ[二つの異なる動物が一体化した想像上の動物]であって、社会の中で人びとの間に根を張っていないからで、だからすうっと消えていく。本物の抵抗運動の真髄を吸い取った、うわべだけの抵抗運動さえ消え去る。
JC:モディは長くやっていけるの?
AR:どちらとも言いにくい。本当の野党がないの。絶対多数をもっていて、政府を完全にコントロールしていて、モディ自身は――胡散臭い過去をもつ人間はたいてそうだと思うけれど――味方のだれのことも信じていないから、直接人びとと関わらなければならなくなっている。政府は二の次。公的機関に自分の追随者を送り込み、学校と大学のカリキュラムが改訂され、歴史がばかげた形で書き換えられている。こういうことはすべて、ほんとうに危ない。そして若者、学生、IT人、教育のある中流階級の大部分と、もちろん大企業がモディ側についているし――ヒンドゥー右派もついている。モディは公的な発言のハードルを下げている――こんなことを言ったりする。「ヒンドゥーはヴェーダで整形手術を発見したのである。でなければ、どうして象の頭をした神をもつことができただろう」

JC:(笑)そんなこと言ったの?
AR:そう!危ない。一方で、ほんとに面白みがないからどのくらい続くことができるのかわからないけれど。でも今のところ、人びとはモディのお面をつけたり、手を振って答えたりしてる……モディは民主的に選ばれた。そのことから逃げることはできない。だから「国民」とか「一般市民」がすべての倫理の最後の砦のように持ち出されるとき、わたしは思わずたじろぐことが多いわけ。
JC:「奇をてらった厚化粧は死の仮面」と言うしね……。
AR:当たっていそう……でも、議会ではモディに対抗する本当の野党はないけれど、インドというのはとても面白いところで……公式の野党はないけれど、本物の現場の対抗勢力はある。あちこちに行けば――本当にいろいろな人たち、優秀な人たち……ジャーナリスト、活動家、映像作家がいて、カシミール――インド側のね――に行っても、まもなくダムに水没することになっているアディヴァジ村に行っても、わたしたちが話していること――監視、グローバル化、NGO化――のどれについても、理解のレベルがほんとうに高い。抵抗運動はぼろぼろにされ、ずたずたにされ、後がないところまで追い込まれているけれど、運動の知恵は信じられないほど素晴らしい。だから……わたしはそういう人たちを頼みにして、信じ続けている。(笑)
JC:じゃあ、こういうことは君にとっては目新しいことじゃないんだね……監視社会の話は。
AR:もちろん、細かいことは目新しい、技術的なこととか規模とか――でもインドにいて自分のことを「罪のない無邪気な人間」と思っていないわたしたちの多くにとっては、監視というのはだれでもずっと気づいていたこと。軍や警察に即決処刑された人たちのほとんど――わたしたちは「遭遇」とよんでいるのだけど――は、携帯電話で追跡されていた。カシミールでは、長年、すべての電話通話、すべての電子メール、すべてのフェースブックアカウントがモニターされていた――それに加えて、ドアをぶち破り、群衆に向かって銃撃し、大量逮捕し、そしてアブグレイブもかすんでしまうような拷問をする。インドの中心部でも同じこと。
JC:君が『Walking with the Comrades 同志とともに歩む』ために行った森林では?
AR:そう。あそこでは世界でもっとも貧しい人たちが、もっとも金のある鉱山会社のいくつかを食い止めている。最大の皮肉は、辺境に住む、字の読めない、テレビも持っていない人たちが、ある意味で一層自由だということ。現代のマスメディアによる洗脳の届かないところにいるから。そこでは内戦に等しいものが起きているけれど、ほとんどだれもそのことを知らない。ともかく、森に入る前に、わたしは警察の警視にこう言われた。「あの川を越えるものはだれでも、姿を見られたら、わたしの部下に撃たれる危険がある」。警察は川向こうの一帯を「パキスタン」と呼んでいる。それから警視はこう言った。「ですからね、アルンダティさん、わたしは上司に言ったんです、あの一帯にどれほど大勢の警官を送り込んでも、この戦闘に武力で勝利することはできない――勝利する唯一の方法は、部族の人の家一軒一軒にテレビを置くことだけだ、と。ああいう部族民は欲というものがわかっていないからです」。警視が言いたかったのは、テレビを見れば、欲というものについて教わることになる、ということ。
JC:欲……これこそ、この騒々しい道化芝居の中心……だよね?
AR:そう。
***
その夜、授賞式の後で、僕たちはエルスバーグと合流した。翌朝、モスクワ行きの便に乗った。一緒に来るのはライト・ライブリフッド基金のオレ・フォン・ウエクスキュル、澄んだ目と非の打ち所のない立ち居振る舞いの素晴らしい男だ。オレは、ストックホルムへ来られないスノウデンに賞を渡しにいくのだ。これから数日間、旅の道連れになる。83歳のエルスバーグは、機内でロイの新刊エッセイ『The Doctor and the Saint』を猛然と読み、黄色のリーガルパッドにメモをとっていた。僕はいろいろな考えが頭の中が駆け巡り始め、一路モスクワを目指すこの小さな空飛ぶサーカスのことをロイはどう思っているのだろうと思い巡らした。ロイが――不穏な光沢といたずらっぽいきらめきをもつこげ茶色の瞳をして――「”グック”の視点」と呼ぶものから、自分は何を学ぶのだろうか。ロイはどんな時でも、人懐っこく、山師のようにニヤッと笑い、人の気持ちをほぐすことができるけれど、その瞳は、物事を見通し、物事を激しく愛し、時々恐ろしくなるほどだ。
かつて自分が殲滅を計画した国の入国管理を通り抜けながら、エルスバーグはちらっとピースサインをして見せた。まもなくモスクワの凍りつくような道を車で走り抜けていた。リッツカールトン・ホテルは、クレムリンから文字どおり数百ヤードのところに鎮座している。赤の広場はテレビでは、あの軍事パレードというホラーショーの間、いつもはるかに大きく見えていた。生で目の当たりにすると、ずっと小さい。チェックインして、クレムリンがよく見える、ルーフデッキにはアウディ車が一台展示されているVIPラウンジにすばやく案内された。アウディがお届けするリッツ・テラス。資本主義が歴史を終わらせたはずだということを思い出させるものがここにも一つ、レーニンの墓を見下ろしている。
翌日の昼、待っていた電話が部屋にかかってきた。
米国の良心の生けるシンボルである二人の出会いは歴史的だった。それは起こるべくして起こった。スノウデンとエルスバーグが一緒にいて、話を交わし、メモをやり取りするのを目にするのは、心の温まる、そして非常に刺激になることであり、そしてロイと二人の元大統領部下との会話は類を見ないものだった。深み、洞察、機知、寛容さ、そして構成された公式のインタビューでは不可能な軽快さがあった。自分たちよりも大きな力に観られ、監視されていることを意識しながら、僕たちは話をした。そのうち米国家安全保障局が僕たちの会合の議事録をくれる日が来るかもしれない。素晴らしかったのは、部屋の中にどれほどの意見の一致があったかということだった。何が語られたかだけでなく、どのように語られたか、言葉だけでなく、言葉の外にあるもの、温かみと、そして本当に爽快な笑い。でもそれは別の話だ。忘れられない2日間、20時間を共に過ごした後、僕たちはスノウデンに別れを告げた。もう一度会うことがあるだろうかと思い巡らしながら。
スノウデンと過ごした最後の数時間に、エルスバーグは、核軍拡競争の歴史――嘘に次ぐ嘘の歴史――を、背筋の凍るような経験的な細部にわたって物語った。遺体安置所の独白と殺人儀式からなる黙示録的な一巻。
話の途中でエルスバーグは、国防総省で上司だったロバート・マクナマラのことを「穏健派」と言った。この一節を聞いたロイは、目を大きく見開いた。するとエルスバーグは、エドウィン・テラーやカーチス・ルメイといった、国防総省のほかの狂人たちと比べれば、いかにマクナマラが穏健派だったかを説明した。マクナマラの穏健で合理的な論理では、とエルスバーグは言った。米国に必要な核弾頭の数は1000ではなく400だった、と。なぜなら、400以上になると、「ジェノサイド上の運用益が減る」からだ。横ばいになるわけだ。「400発で大半の人が殺される。だから、800発あっても殺される人の数はあまり増えない――400の核弾頭が、当時37億人の総人口の12億人を殺すことになる。それならどうして1000発もつ必要があるだろう」
ロイは口数少なく、この話をずっと聞いていた。1998年のインドの核実験の後に書いたエッセイ『The End of Imagination』でロイは、次のように宣言して、深刻なトラブルに巻き込まれていた。「核兵器に抗議することが反国家的なら、わたしは脱退する。わたしは自分自身を可動性の共和国と宣言する」。核軍拡競争に関する本を執筆中のエルスバーグは、ロイの本を、この問題について自分が読んだ中で最良のものの一つだと僕に言った。「こう言うことでしょう?」とロイは念を押すために、あるいはだれでも耳を傾けるつもりのある人に向かって言った。「核兵器は、”偉大な国家”という概念には不可避で有毒な必然的帰結だと」
スノウデンが去るとすぐ、エルスバーグは、両手を大きく広げて僕のベッドに倒れこんだ――疲労困憊し至福に包まれて――が、その後、奥深いところから激しい思いが突きあがってきた。エルスバーグは動揺し、感情を抑えきれなかった。エドワード・エヴェレット・ヘイルの『The Man Without a Country』、裁判と軍法会議にかけられた米海軍将校をめぐる短い物語から引用をした。ヘイルの判決では将校は艦船を永遠に転々としなければならず、「米国」という名前を二度と耳にすることがあってはならない。この物語で、一人の登場人物がウォルター・スコット卿の詩「愛国主義」を引用する。
魂がかくも死した男がここで息をしている、
彼は自らに一度も告げたことがない、
「ここは我が土地、我が故郷」と。
エルスバーグは泣き出した。ぽろぽろ涙を流しながら彼は言った。「わたしはある意味ではまだこんなにも愛国者なんだ……国家に対してではないけれど……」。彼は自分の息子のことを話し、そして、自分がベトナム戦争中に大きく変わったこと、そして息子は監獄に入るために生まれたのだとよく考えたものだったことを話した。「スノウデンのような、わたしたちの国の最良の人びとができる最良のことは刑務所に行くことだ、と……さもなければ、ロシアで亡命者になることか。わたしの国はこんなことになってしまった……ひどいじゃないか……」。ロイの瞳は共感を湛えていたが、明らかに落ち着かない様子だった。

それはモスクワで過ごした最後の夜だった。僕たちは赤の広場に散歩に行った。クレムリンは電飾で照らされていた。エルスバーグはコサックの毛皮の帽子を買いに行った。僕たちは、滑りやすい氷に覆われた赤の広場にそろそろと足を踏み入れ、どれがプーチンの部屋の窓だろう、プーチンはまだ仕事をしているだろうかと推測した。ロイは、まだ1001号室にいるかのように話し続けた。
AR:ジェノサイド上の運用益が減る……タイトルは何? 数学、それとも経済学?動物学であるべきね。毛沢東は言った。中国が生き残る限り、何百万もの中国人を核戦争で死なせる用意があると……。計算の中に入れられるのは人間だけだなんて、だんだん吐き気がしてくる……地球上の生命を抹殺して、しかし国家を救う……タイトルは何? 愚かさ、それとも狂気?
JC:社会福祉だよ……ああいう狂人たちはバイナリーコードではどう見えると思う?
AR:見栄えがすると思う。偉大な国家を作り上げるために、どれほど多くの暴力、どれほど多くの血、どれほど多くが破壊されたかと考えると、米国、オーストラリア、イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー――インドやパキスタンまでも。
JC:ソ連……
AR:そう。そういう国家を作るためにこれほど多くを破壊した挙句、守るために核兵器を持たなくちゃならない――そして彼らの生活様式を維持するために気候変動が起きて……二又の抹殺計画。
JC:僕たちみんな国旗に対して頭を下げなくちゃならない。
AR:そして――赤の広場にいる今だから言ってもいいでしょう――資本主義に対して。わたしが資本主義という言葉を言うたびに、みんな思う……
JC:ロイはマルクス主義者に違いないって。
AR:わたしの中にはマルクス主義的なところがたくさんある、確かにある……でもロシアと中国では血塗られた革命が起き、共産主義国だった間も、富の生成については同じ考え方をもっていた――地球のはらわたからむしり取れ。そして今、両国とも結局同じ考え方を打ち出している……もちろん、資本主義。でも資本主義もいずれ破綻する。わたしたちには新しい想像力が要る。それまでは、みなただ……
JC:さまよってる……
AR:何千年、何万年もの間、思想的、哲学的、実際的決定が下されてきた。そうした決定が地球の様相を変え、わたしたちの魂の座標を変えてきた。その決定の一つ一つについて、下すことができたかもしれない別の決定、下すべきだった別の決定がきっとある。
JC:下すことができる決定も……
AR:もちろん。だからわたしは壮大な思想はもたない。壮大な思想を持ちたいと思う傲慢な気持ちもない。でも、抵抗する力の物理学は、権力を蓄積する物理学と同じくらい古いと思っている。それが宇宙のバランスを保っているもの……従うのを拒否すること。言いたいことは、国って何だろう、ということ。行政の単位、美化された自治体当局にすぎない。どうして国に深遠な意味をもたせて、核爆弾で守るのか。わたしは自治体当局に頭を下げることなんかできない……知性的なことじゃない。ろくでなしたちは彼らのやるべきことをやり、わたしたちはわたしたちのやるべきことをやる。彼らがわたしたちを抹殺しても、わたしたちは向こう側に下りていく。
僕はロイを見て、インドに戻った彼女をどんなトラブルが待ち受けているだろうと考えた……古いユーゴスラビアのことわざが頭に浮かんだ――「真実を告げて走り去れ」。でも走り去ろうとしない生き物がいる……おそらくそうするべきときでさえも。弱みを見せればろくでなしどもが図に乗るだけだと知っているのだ。
突然ロイが僕のほうに向き直り、エドワード・スノウデンとの出会いを企画してくれてありがとうと、改まって礼を言った。「スノウデンは冷静な体制人の姿を示しているけれど、ああいうこと可能にするのは情熱だけ。彼はただの体制人じゃない。わたしにはそのことを知る必要があった」
僕たちは、遠くで帽子屋と交渉しているエルスバーグから目を離さなかった。氷で足を滑らせないかと心配した。
「では記録に残しておくために、ロイさん」と僕は尋ねた。「”マルクス主義的なところがたくさん”ある人間として、赤の広場で氷の上を歩くのはどうですか」。ロイは澄ました顔でうなづき、トークショー風の僕の質問を真剣に考えている様子を見せた。「赤の広場は民営化されるべきだと考えます……女性受刑者のエンパワーメント、児童労働の廃止、マスメディアと鉱山会社の関係改善のために倦むことなく活動している財団に払い下げるべきです。たぶんビル&メリンダ・ゲイツに」
ロイの笑みは悲しみを含んでいた……思考のハーモニーが美しく響くのがほとんど聞こえたような気がした。凍りついた空気を突然満たす教会の鐘の音のように、荒涼とした冬の夜を切り裂く風の音のように澄んだ音が。
「ほら、聞いて」とロイは言った。「神が赤の広場に戻りたもうた」
=======================================================
原文
http://www.outlookindia.com/article/things-that-can-and-cannot-be-said-contd-/295810
Consider This: “In the United States, we can talk about ISIS, but we can’t talk about Palestine”
exclusive: meeting ed snowden – III
Things That Can And Cannot Be Said (Contd)
The Arundhati Roy — John Cusack conversation continues.
John Cusack