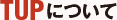FROM: Schu Sugawara
DATE: 2004年3月24日(水) 午後3時12分
◎マコーマック、イラク南部に掲げられた日章旗の意味を語る
トム・ディスパッチ 2004年3月16日
例えば、帝国主義全盛の時代、大英帝国はインドやネパールなどの植民地軍や傭兵たちを両世界大戦のヨーロッパ戦線に投入しました。現代の“自由と民主主義"を守る対テロ世界戦争に、ついに日本も参戦し、イラクに派兵しましたが、これは往時の英領インド軍やグルカ傭兵部隊と、どこがどう違うのでしょうか? ごく当然の疑問が、国政の場で説明されていないし、マスコミや論壇でも、まともな形の議論にはなっていないようです。それでは、東京、国際基督教大学の客員教授の講義に耳を傾けてみましょう。TUP 井上
凡例: (原注) [訳注]
[トム・エンゲルハートによる前書き]
アメリカのマスコミ業界では、だれも考えさえもしなかったようだが、国際社会の目に映るイラク駐留“連合国軍”は、かなり大世帯の英軍部隊は別にして、はなからブラックユーモア以外のなにものでもなかった。占領地に展開する奇妙な帝国軍戦力に加算されているのは、カザフの兵員27名、エストニア46名、フィリピン96名、モンゴル130名、アゼルバイジャン150名、タイ451名、スペイン1300名、ポーランド2500名、イタリア2950名、その他である。これら、象徴的ないしミクロ規模の兵力のほとんどすべてが、当のイラクにまったく無関係、しかも新時代の中東建設によせる貢献としても無意味そのものであり、もっぱら各国の利害関係を背負っているだけだった。
ただ単に帝国から無理強いされ、また賄賂で釣られて、駐留軍に加わった部隊もある。あるいは超大国アメリカのご機嫌をとりたいと切に願い、それにもちろん、ハリバートン社、ベクテル社、その他同類といった帝国本国籍・豪華クルーズ船団が大金の流れに乗るのを目にして、まぎれもないトリクルダウン経済理論[*]を標榜するイラク再建事業(ならびに将来の石油関連契約)のおこぼれで、めでたく海に漕ぎだせるボートも少しはあるかもしれないと哀れな望みにかけて、兵をさしだした“二等”国の二流指導者もいた。
[*政府資金を大企業に注入すれば、景気を刺激して、中小企業・消費者を含めた経済全体を潤すという説]
ここで各国がこうむる流血の犠牲規模には触れないにしても、この“有志連合”のもっとも際だった特徴は、開戦前のさまざまな世論調査結果を見ると、例外なくと言っていいほど全ての参加国で、アメリカの戦争と占領を支持する国民が半数に届いていないという事実にある。開戦直前に数百万の人波が街頭デモを繰りひろげた、あの光景を思いだしてみよう。特にスペイン国民の熱狂と団結は群を抜いていた。世論調査によれば、スペイン人の91パーセントが戦争に反対していた。考えてもみよう。戦争賛成のスペイン人は9パーセントしかいなかったのだ。(この数値には“わからない”層も含まれているはず)
今週(3月14日)、考えられるかぎりで最悪の恐ろしい状況下で挙行された総選挙で、スペイン国民は政府与党の戦争・占領支持政策を拒否する審判をくだした。ブッシュの忠実な同盟者、ホセ・マリア・アスナール首相の政府を退場させた投票に先立つ日々の抗議デモで、人びとが「われらの死、おまえの戦争!」と叫んでいたと伝えられる。なかでももっとも率直な言葉であり、いつの日か、アメリカのあちこちの街の大通りでも聴くに違いないのは、「ウソだ!」という叫びだった。
アメリカで言われているように、スペインの政変はアルカイダがまんまと成功した初めての体制転覆であるという解説にも、一部の理があるだろう。しかしちょっと振り返って、現実に起こったのは何だったのか、じっくり考えてみたい。アスナールの政府は民主的に選ばれたスペインの代表のはずだったが、国民の90パーセントを占める多数派の意志を代弁しないどころか、平然と無視し、裏切る決断を下した。これが最初の“体制転覆”だった。次いで危機の瞬間のさなか、ヨーロッパを直撃した、一生のうちにも滅多にない最悪のテロ行為の背景説明で、政府がウソで通そうとした。これも裏切りだった。
今が決定的瞬間であり、おそらく“危機の絶頂”と言ってもいいだろう。昨年の4月、数百万単位で世界の人びとが大規模なデモに参加したのに、イラク戦争を阻止できず、運動は失敗だったと見なされるしかなかった。だが少なくとも一国では、デモに参加した人たちは、実質的に、解散しなかった。いざという時に、かれらは毅然として立派に行動した。そういうことは別の場所では起こりえないなどと、いささかでも思いこんではいけない。(あのテキサスにおいてさえも、徐々にだが世論が動いていて、地元のスクリップス・ハワード・テキサス調査会社による集計では、60パーセントに迫る数の回答者がイラクの“現状に不満”と評価している)
スペインの審判はイギリスのブレアを直撃し、ポーランド政府をギリギリの崖ぷっちまで追いつめているが、(やはり反戦を願う国民を裏切っている)ベルルスコーニ首相のイタリアを始め、他のヨーロッパ諸国も揺さぶるに違いない。スペイン総選挙の結果は、国民が反対票を投じても不思議ではなく、またそのように予測されていた時に、ウソとゴマカシで押し通そうとした政府与党に、国民が拒絶の形で審判を下したものなのだ。スペイン国民の決断を目のあたりにして、さすがに、わがアメリカの政権部内にも動揺がうまれている。
(こういう状況にたちいたっても、ブッシュ政権はあくまでも真実を語る気がないようである。英紙グラスゴー・サンデー・ヘラルドの信頼できるニール・マッケイが「当初から複数のアメリカ諜報機関はアルカイダがマドリード爆弾事件の背後にいると信じていたが、スペインの総選挙が終わるまで、ETA[バスク祖国と自由]の犯行であるとするスペイン政府の主張に追随していた」と報告している)
ウィリアム・リバース・ピットがオルターネット・サイトに書いた――「2日間だった。真実を語れと自国政府に迫るスペイン国民の堪忍袋の緒が切れるまで、それだけの日数しか持たなかった。真相解明は望めないと分かったとたん、民衆は政府を摘み出した。アメリカでは、政府が9・11事件の真実を明かさないまま1000日に達しようとしているが、米国民はスペインの教訓を深く心に刻まなければならない」
スペインの事態は、ヨーロッパから遠く離れた東アジアでも、韓国はもちろん、日本の政府を揺さぶるはずだ。両国とも、中東とはまったく関係がない理由により、しかも民意に反して、イラクへ派兵している。
イラク駐留“連合国軍”が形成され、派兵が続く経緯と背景については、驚くほど注目されてこなかった。ここで、オーストラリアの学者ガバン・マコーマックを紹介したい。以下に掲載する記事は、日本政府の対イラク政策決定を左右した世界的および地域的要因を、明瞭で絶妙に説明してくれる、まれにみる有益な論文になっている。しかもマコーマックは、(空想にすぎないにしても、トニー・ブレアのイングランドを念頭に置く)アメリカ政府の膨れるいっぽうの願いどおり、日本が“極東における大英帝国”になるための枠組みを分析して見せ、緊密でありながら不安定な日米同盟関係を掘り下げている。さらに、日本が担う縁の下の役割、すなわち、帝国政策の無理が祟って、いよいよ危なっかしくなっているアメリカ財政を下支えする、不可欠な使命に切れ味鋭いメスを入れている。
ところで、つい先日、わたしは第2期ブッシュ政権についての推測記事をものにした。もしもブッシュの続投が現実になるなら、その4年間における対外政策の大変な危機は、闇に包まれた国家の“親愛なる首領”と呼ばれ、核開発計画を持つキム・ジョンイル(金正日)の体制をどうするかという第2期政権の政策をめぐって訪れるはずだと思う。
迫りくる朝鮮半島の危機に備えて、わたしたち皆で用意していなければならない。流血によってであれ、平和裏にであれ、危機が決着するとき(ケリー上院議員がホワイトハウスの主になっているとしても)、これからの何十年にわたり、新時代のアジアと世界の構造が変動することになるだろう。心構えを造る手始めとして、ガバン・マコーマックの新著『標的・北朝鮮』が最適の読み物である。現代世界の情報に遅れないためには、資料が手軽であることも大きな長所になる。この本は分厚くないが、深い良識と分別を備えている。知るべきことが余さず書いてあり、歴史背景もふくめて明瞭かつ複雑多岐にわたる記述である。それでたったの250ページ足らずだ。トム(署名)
==================================================================
BOOTS(軍靴)BILLIONS(資金)BLOOD(血の貢献)
『ブッシュの手の平で踊る小泉の日本』
――ガバン・マコーマック
——————————————————————-
BOOTS(軍靴)
今年2月、国連コフィ・アナン事務総長の来日を1週間先に控えて、小泉純一郎首相は、米国の「信頼できる味方」であることを示すことが、日本にとって決定的に重要であると明言した。最後にかれは、日本が攻撃される事態になれば、助けに来てくれるのは米国であり、国連でも、ほかのどの国でもないと説明した。攻撃してくるのはどの国か、あえて言う必要もなかった。北朝鮮を指して言っていることは、日本人みなに分かっていたからである。2003年3月時点で、米国主導のイラク侵攻を支持すると宣言した時、そして、今年の1月、占領を助けるために日本軍が南部イラクに派遣された時、日本が視野に入れていたものは、イラクのスンニ派でもシーア派でもなく、ここ数年来、国内の恐怖と憎悪が急激に集中されるようになった国、北朝鮮に他ならなかった。
かねてから大陸の近隣諸国に感じる心理的な距離を考えると、小泉の下での日本としては、60年間にわたり庇護を受けて来た米国に擦り寄ること、すなわち、たとえアジア諸国との和解と協調をさらに阻害することになるにしても、米国がより強く抱きしめてくれるように仕向ける立場を示す以外には選択肢が見当たらなかった。2003年11月23日の国会で、小泉は「わたしはブッシュ大統領が正しいと信じているし、かれは善人です」と語った。かれは、ジョージ・ブッシュが個人的な温情を示した数少ない世界の指導者の一人であり、“友情”をちらつかせた要請にからきし弱いようだ。経済規模でみれば、日本はドイツ、フランス、イギリスを合わせたものとほぼ等しい大国であるのに、この首相は主要な問題について、「フランス的な」あるいは「ドイツ的な」立場を取ることで、ワシントンに反抗するような危険を犯そうとはしなかった。世界を見渡して、日本の首相ほどブッシュ政権に忠実な信奉者はいないと言っても間違いないであろう。
9・11攻撃の後、リチャード・アーミテージ国務副長官が、露骨な言い方で、日本は砂に頭を突っ込んでいないで、アフガニスタン戦争では、他人事だと知らぬ顔をせず、日の丸の旗を高く掲げて(ショウ・ザ・フラッグ)同盟国であることをはっきり示せと釘をさし、小泉としても、すぐさまその言葉を重く受けとめた。平和憲法を持つ国であり、また中東の紛争にいっさい関わりをもたないにもかかわらず、日本は、連合軍に対する支援と給油のために、イージス駆逐艦を含め相当な規模の海上自衛隊(日本国海軍の別名)艦隊をインド洋に派遣したのである。
さらに2003年3月、開戦前夜の状況になって、小泉はイラク侵攻に対する“無条件”支持を公約した。かれは、支持の約束を“ブーツ・オン・ザ・グラウンド”すなわち地上部隊の派遣の形で実現するようにとの圧力を受けて、言われたとおりに部隊派遣にも同意した。かくして2004年1月、日本国自衛隊の尖兵部隊が飛びたった。
日本は、従属的であり、しかも公式には“非戦闘的”な役割を果たすにすぎないとしても、敗戦後60年の歴史で始めて、非合法な侵略戦争に荷担することになった。論議されるべき懸案が山積している状況にあるにもかかわらず、最近の国会では、まともな票決すらも稀にしかなされていない。“自衛隊イラク派兵”承認決議案を審議するために、国会が1月末に召集されたが、決議にさいし、憲法違反を主張する野党はこぞってボイコット、さらには政権与党・自由民主党の重鎮たちまで何人かが欠席[または退席]した。
閣僚経験がある保守的な元議員が、政府の行為は憲法違反であるとして裁判に訴えた。また、ある経験の長い[駐レバノン]大使は、小泉の政策に異議を唱えたとして召還され、あげくのはて首を切られた。大量破壊兵器を見つけるために捜索を続けていた米国のイラク調査団の長デイビッド・ケイが、米下院委員会の証人席で、そのような武器の存在は「きわめて疑わしい」と陳述した時でさえも、小泉の姿勢は揺るがなかった。かれにしてみれば、ワシントン向けの“信義”のほうが、日本の憲法、法律、あるいは道義よりも重い値打ちがあったようだ。
戦後、米国の占領下で制定された日本国憲法の第9条が謳う、国による「戦力の保持」および「武力の行使」の制約は、今や西洋世界からは厳しい攻勢にさらされているが、アジア諸国からは、戦後の地域安定に貢献してきた要因のひとつとして評価されている。北朝鮮に対する敵意と恐怖の風潮という国内情勢と、イラク派兵を求める米国からの外圧とが結びついて、小泉の追い風になり、憲法の原則を遵守してきた半世紀の歴史を投げ捨て、自衛隊を正規軍に改変する絶好の機会を提供している。
小泉が自衛隊のイラク派兵を決定したときには、あえて国民世論の根強い反対を押し切る必要があったが、たった数ヵ月のうちに、かれは、みずから訴えた愛国心が奔流になって湧きあがり、それが憲法上の懸念の声を押し流し、まんまと世論の動向を転覆させるのを見ることができた。2003年上半期では、国民世論の7割から8割が、いかなる形であれ自衛隊を派兵することに反対していたが、2004年初めには、賛成意見が(53パーセントになり)過半数を僅差で上回るようになった。目先のことだけを考えれば、小泉は賭けに勝ったのである。小泉は思っていたよりも簡単に任務を達成し、アメリカのマスコミで、またある程度はヨーロッパでも、その仕事ぶりが評価されて、いわく、日本は“現実的”に行動し、“世界的な責任”を担い、着古した“偽善的な道徳主義”の衣を脱ぎすて、米国の“真のパートナー”として振舞っていると報道された。国内外で認められて、小泉はご満悦である。
BILLIONS(資金)
アメリカ経済は、慢性的赤字の重圧に加えて、増えるいっぽうの世界帝国を維持管理する費用負担に耐えかねているので、東京からの資金援助がいよいよ重要になっている。冷戦が終結してからも、日本は国内(とりわけ沖縄)に駐留する米軍の基地を維持するために、700億ドルを超える“思いやり予算”を配分し、さらに加えて、ポスト9・11時代の反テロ連合に寄与する“後方支援費”900億ドルを支出するなど、信じがたい額の援助金を帝国アメリカに貢いでいる。
ワシントンがイラク復興資金の追加分として“数十億ドル規模”を要求すると、さっそく小泉は、他の連合国が請け合った額のどれよりもはるかに多い50億ドルの支出を約束した。ワシントンから強まるいっぽうの圧力が加えられて、日本政府は、イラク政府の巨額債務のうち、下限30億ドルから上限70億ドルまでのいずれかの額、どこで決まっても相当大きくなる部分の償還を繰り延べる用意があると表明した。
世界通貨市場において、ドル安を防ぎ、円高を抑える狙いの、官による大規模な介入も、同じような日本の協調姿勢の明白な表われである。2003年中に、日本銀行は、ドルを下支えするために、これはすなわちアメリカ経済を支えるために、20兆円(1800億ドル)を注入した。2004年になっても、この手法が強化されただけであり、年初2ヶ月だけで、前年総額の半分相当が市場に投入された。米国債、各種公債、米国株に対する外需が弱含みになると、日本銀行は総力をあげて、その安定に努めた。2004年初め、IMF(国際通貨基金)は、アメリカの対外債務がGDP(国内総生産)の40パーセントに迫る勢いであり、その赤字体質が世界経済にとって“重大な危険要因”になっていると指摘したが、アメリカに対して、東京以上に大きな信頼をよせ、あるいは強く支えようとする政府はどこにもない。
日本に財源が余っているというわけではない。1980年代のバブル期に蓄積した過剰流動資産にしても、とっくに消え去っている。日本は、大幅な政府支出抑制と増税の見通し、現行の福祉政策と年金制度の崩壊、待ったなしに進む社会の老齢化に直面している。2004年度予算は、歳入を42兆円、歳出を82兆円と見込んでいる。つまり予算の約半分は国債または借金頼みなのである。教育、福祉、海外援助の予算は削られ、中小企業は放置されることになり、自前の“市場競争力”を頼りに凌(しの)いでいくことになった。バブルの時代が終わってからずっと、山ほどに積もってしまった負債に嘆息し、きわめて臆病な成長マインドを抱えこんでしまった。
ついでに言うなら、日米両国政府がそれぞれ抱えている負債は、どちらも約7兆ドルという途方もない大きさで、ほとんど同額で並んでいる。人口においても、経済分野においても、米国の規模は日本に比べて倍以上なので、それだけ日本の問題はより深刻であるはずだ。日本の債務問題は、たぶん現代史上で最悪だろう。日本システムの病理は、小泉が公言し、宣伝している“行政改革”の大風呂敷に覆われて、手が付けられないままである。
かくして日本国民の貯蓄が、世界帝国として振る舞うアメリカに資金を供給する主な基金になり、また同時に、米国の負債に融資する主な財源になっていて、世界規模の超大国の消費形態、生活様式、軍事構想を支えている。言うなれば、重症の米国経済をなんとか支えるために、末期症状の日本経済が打てるだけの手を打っている図である。こういう米国と日本という債務山脈に連なる双子の峰の上で、世界システムが不安定な均衡を保っている。
BLOOD(血の貢献)
2003年から04年にかけて、日本は一連の歴史的選択を決断した。日本はブッシュ政権に命運を託して、これまで自国の敵もいなかった、また自国がいささかの関わりも持ったことがなかった歴史的紛争の舞台である世界の火薬庫のど真ん中へ、米軍の軍事行動を支援するために、自国軍を派遣したのである。米国務副長官アーミテージは、さまざまに手を変えて発信されるアメリカからの要求に即応して決断をくだす日本の様子を評価して、日本がもはや“観客席に座って”いないで、“競技場の選手”として登場したのであり、米政府は“ワクワクする興奮”を覚えたと述べた。
米国の圧力には、手加減というものがない。ワシントンから東京に代官たちが定期便で飛んできて、新たな指令を伝えてくる。日本は、(2000年10月付け『アーミテージ報告』の言葉を用いれば)憲法を改訂し、正真正銘のNATO式パートナーとして“連合軍”の作戦行動を支援するために防衛線を拡大し、もって“極東における英国”になることを要求されている。日米関係は、ただ単純に、米国が日本を“防衛”するものとして伝統的に語られているが、実際には、ワシントンの視点から見て、力点の置き方がいくらか異なっている。ブッシュ政権にとって、常に基本的であり、不可欠であるのは、日本が「米国の保護に依存し続ける」ことなのだ。いかなる形であれ日本が自立し、また米国の“保護”を中国との友好関係に置き換えようと試みれば、ランド研究所の報告によると、「東アジアにおける米国の政治的・軍事的影響力に致命的な打撃を与える」ことになる。ある日、日本が“自分の足で”歩きはじめ、自分の意志で、極東の英国ではなく、極東の日本になると考えるだけでも、あの9・11攻撃にも劣らない、ワシントン中枢を直撃して、震撼させる悪夢になる。
さしあたり、もし日本が米国主導の試合で本当に“選手”になっているとすれば、誰がチームの主将であり、コーチであるかは見誤りようもなく、またゲームが命がけの深刻なものであることも疑いようがない。2003年2月、イラクとの戦争が迫るなか、日本の立場を問われた自民党政調会長・久間章生(ふみお・当時)は「(日本には)選択の余地がないと思う。なんと言っても、アメリカの州みたいなものなのだ」と言った。小泉とかれの政府は、遅かれ早かれ、関与の代償を払わなければならなくなると理解すべきである。かつて2001年9月、これは日本ではなくオーストラリアについてだが、アーミテージが久間の言葉をきわめて明瞭に裏付けた。かれはオーストラリアの聴衆を前にして、自分が“同盟”と言うとき、その意味は「オーストラリアの息子たちと娘たちが……米国を防衛するために喜んで死ねる」関係を指し、「それでこそ、同盟であると言える」と示唆したのである。この基本的事実の日本版がなにを意味するか、アーミテージは、いや、言うなれば小泉は、まだはっきりとは述べてはいない。しかし、軍靴と資金に続いて、血を流す貢献を見せろという要求があるのは間違いない。
2004年2月、国連のコフィ・アナン事務総長が東京を訪問し、国会で演説した。イラク攻撃によって事務総長としての権威を英米同盟に踏みにじられたアナンにとって、ちょうど来日のころ、イラクで複雑な交渉に力を注ぎ、いくぶんかでも指導力を回復していたとしても、この一年間は試練の連続だった。(国会演説で)アナンは、国連予算の20パーセントを拠出しながら、安保理に席を持たない日本について、世界市民としての役割を果たしていると賞賛した。かれは、小泉の政策について、さすがに批判めいたことは一言も口にしなかったが、それでも小泉の方針には疑義を表明し、世界情勢を踏まえて、これまでよりも自立して、国際人としての役割を果たすようにと、総理大臣の頭越しに、日本国民一般に向けて訴えた。
“北朝鮮問題”が未解決であるうちは、日本は米国に依存しつづけるだろう。逆に言えば、もしも日本と北朝鮮の関係が、また北朝鮮と韓国の関係が正常化に向かい、緊張が緩和するようになれば、日本がアメリカの覇権主義的な計画に包括的に組み込まれているような状態は、とても正当化されるものではない。もしも東アジアに平和が到来するならば、韓国でも、あるいは日本でも、米軍駐留の継続は困難になるだろう。その時、日本がアジア近隣諸国に眼を向けて、米国の“信頼できる同盟国”であることよりも、将来のアジア共同体における信頼に値するメンバーであることを目指して、政策優先順位を組み替えることが可能になるだろう。それまでは、小泉がイラク南部に日本の“自衛”のための生命線を展開する決断をしたために、いつ血の代償を支払うことになるのかと、日本国民はドキドキしながら待つことになる。
——————————————————————
[筆者] ガバン・マコーマックは、キャンベラのオーストラリア国立大学教授
であり、現在、東京、国際基督教大学の客員教授。現代東アジアの歴史、政治
に関する論文、多数。最新刊『標的・北朝鮮:核の破局に北朝鮮を追いつめ
る』(未邦訳・仮題)Target North Korea: Pushing North Korea to the
Brink of Nuclear Catastrophe, Nation Books
——————————————————————-
[原文] Tomgram: Gavan McCormack, Rising Sun over southern Iraq?
Boots, Billions, and Blood; Koizumi’s Japan in Bush’s World
By Gavan McCormack, posted March 16, 2004 at TomDispatch.com.
http://www.nationinstitute.org/tomdispatch/index.mhtml?emx=x&pid=1322
Copyright C2004 Gavan McCormack [TUP配信許諾済み]
===================================================================
翻訳 [前書き]井上 利男 [本文]岸本 和世
監修 星川 淳 + ガバン・マコーマック /協力 TUPチーム