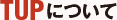FROM: minami hisashi
DATE: 2005年8月27日(土) 午後2時47分
☆海外の目で診た〈ママ〉日本における言論の自由の危機★
TUPは主に海外のニュースやメッセージを読者の皆さまにお伝えしています
が、海外の目で診た日本の姿の紹介もTUPの大事な役割でしょう。今春にメ
ディアをにぎわしたNHKと朝日新聞の対立は、単なる喧嘩として片づけられ
ることが多く、いつのまにかウヤムヤになってしまった観がありますが、海外
の識者たちは日本における言論の自由の危機として厳しい眼で見つめています。
本稿はジャパン・フォーカス・サイトに掲載されたのを受け、TUP速報とし
て配信したいと思いましたが、すでにMEKIKI-net(メディアの危機
を訴える市民ネットワーク)による出版を前提とした翻訳がなされていました。
だが幸いにも、原作者、翻訳者双方のご厚意により、配信が実現しました。テ
ッサ・モーリス=スズキ、岩崎稔両氏に感謝いたします。なお、本稿は書籍原
稿ですので、年号などは漢数字で表されています。井上 /TUP
☆日本のメディアで何が起きているのか★
このエッセーは、テッサ・モリス=鈴木さん自身も下支えしているインターネ
ット上のメディア、Asiarights《*リンク》に、非日本語圏のひと
びとのために、日本のメディアで何が起きているのかを説明するために発表さ
れて話題を呼んだものである。日本語圏の読者には自明であったり、またそう
であるがゆえに不可視になっていたりすることも含まれているかもしれないが、
このように外部の、それもきわめて洞察力豊かな視点から眺めることで、同じ
事態がまた違った奥行きをもって解読可能になるのではないだろうか。なお、
原文には詳細な二十一項の註がついていたが、非日本語圏の読者を想定したも
のでもあったことから、割愛した。また文中には[…]という割注形式で訳注を
付した。岩崎 稔 /MEKIKI-net
* http://rspas.anu.edu.au/asiarightsjournal/
===============================================================
言論の自由、沈黙させられた声――日本のメディアとNHK問題
――テッサ・モーリス=スズキ
ジャパン・フォーカス 2005年8月13日掲載
日本の通勤電車や地下鉄は、週のはじめに、たくさんの多色刷りの広告で飾り
立てられる。これが通勤客に、この国の数ある週刊誌の最新号を買おうという
気持ちにさせるわけである。こうした広告はそれ自体がすでにひとつの芸術表
現形式だ。どれもが同じ様式に則っている。なかにはほとんど判読不能なほど
小さすぎるものまであるが、とにかくテキストをギュッと詰め込んでひとまと
めにして、乗客たちに提供する。この小さな文字列にまじって、黒や赤の巨大
な活字で引き立てられた厳選された数少ない言葉が、今週のニュースはこれだ、
と宣言している。こうした広告の語彙のなかでは、犯罪、死、セックス、それ
にスキャンダルが目立っている。文章のあいだには、雑誌が提供するストー
リーに重要な役どころを務めるひとびとのちいさな写真も混じる。(言うまで
もないが)この写真は、脇のテキストを補うために注意深く選ばれており、晴
れやかに微笑む今週のヒーローというイメージか、それとも政界や芸能界でい
ま話題になっている憎まれ役の、ぼんやりとしたしかめっ面かだ。
これと同じような過程が、一月に一回、今度は主要な月刊誌が新聞スタンドの
店頭に登場するときに繰り返される。月刊誌は、週刊誌よりは長い立ち入った
分析記事を提供しているのだが、週刊誌にすでに一度掲載された話題をとりあ
げることが多く、たとえば発行部数の多い『文藝春秋』(一般にブンシュンと
略称されている)のように、週刊の姉妹誌の白熱したレトリックをそのまま反
復するものもある。
二〇〇五年の一月の最後の週と二月の最初の週にこうした吊り広告のなかから
通勤客の目に飛び込んできた言葉は、「嘘」と「魔女狩り」と「政治的圧力」
だった。そして、いたるところに、もっとも大きく、もっとも影響力のある日
本の二つのメディア、NHKと『朝日新聞』の名が躍っていた。二つの組織は
メディアの倫理と自由の問題をめぐる激しい争いのなかで反目しあい、この二
組織の争いを他のライバルメディアは大いに浮かれながら傍観していたのだっ
た。
いつも週刊誌の見出しになる芸能界のスキャンダルとは違って、この争いは深
い政治的、社会的な意味合いをもっていた。雑誌広告が伝える活気のある自由
な出版といったイメージとは裏腹に、日本のメディアが政治的独立性を維持し、
自由な政治的論争のための場を提供する能力があるのかどうかをめぐって、そ
こでは深刻かつ不穏な問題が生じていたのである。このNHK論争は、長いあ
いだ続いていながら、いまだに解決していない歴史的責任という問題、つまり、
日本が東アジアの隣人とこれからどのような未来を築くのかということに深く
関わる問題も争点としていた。
メディアと女性国際戦犯法廷
論争の起源は、二〇〇〇年の一二月、女性国際戦犯法廷が東京で開催された時
点に遡る。日本と他の六カ国からなるNGOが組織したこの法廷は、証言を集
め、公表し、戦後の東京裁判によっては扱われなかった戦争犯罪について審判
を下そうとしたのだ。その問題とは、植民地や被占領国の女性たちが日本軍に
よって設置されたいわゆる「慰安所」において、制度化された強かんや性的虐
待を強いられたことであった。法廷には公式政府の後ろ盾があったわけではな
く、したがって処罰を遂行する力はもってはいなかったが、その裁判官や法曹
団には、国連やその他の裁判所で豊かな経験を蓄積してきた多くの個人が含ま
れていた。旧ユーゴスラビア戦犯法廷の前所長であったガブリエル・カーク・
マクドナルドもそのひとりである。二〇〇〇年の法廷の主要な目標は、女性た
ちの証言を公共的にヒアリングする機会をつくりだすことであった。戦時中に
「慰安所」で極限的な性的虐待を経験しながら、他の法的な場では承認も補償
も得られなかった彼女たちの多くは、いまどんどん高齢になりつつある。法廷
の判決が、さらに正式な国民的、国際的司法手続きの場を開くための基礎とな
ることが期待されていたのである。
法廷は公開で行われ、連日千人ほどの傍聴者を集めていた。八カ国、六二人の
サバイバーと、二人の旧日本兵が証言に加わっていた。『ワシントンポスト』
『ワールドストリート・ジャーナル』『フランクフルター・アルゲマイネ・ツ
ァイトゥンク』『コリアタイムズ』、それにオーストラリア放送協会といった
国際的メディアによって、その様子は大きく報道された。だが、それとは対照
的に日本国内では、全国的な日刊紙『朝日新聞』だけが法廷のある一部を報道
しただけで、日本のテレビ局にはすっかり無視された。
こうしたメディアの沈黙にとってたったひとつの例外であったのは、二〇〇一
年一月三〇日にNHK教育テレビで放送された『戦時性暴力を問う』というタ
イトルのテレビ・ドキュメンタリーだった。この番組は、戦争責任の問題に関
する四回シリーズの第二回だったが、シリーズの他の回には、アルジェリア独
立戦争や旧ユーゴスラビアの紛争のような問題が取り上げられていた。『戦時
性暴力を問う』は、はっきりと女性国際戦犯法廷に焦点を当て、多くの法廷参
加者の協力のもとに制作されていた。
主題の性格からして、このNHKの番組が論争のテーマとなることはたぶん避
けられなかっただろう。近年、右派の論客たちは、戦争中に行われた女性に対
する制度化された性的虐待に関して、日本国家と日本軍には責任がないと否認
してきていた。およそ否定しがたい証拠は、多くの女性たちが、とくに植民地
から連れてこられた女性たちが、軍によって運営されていたいわゆる「慰安
所」でむごたらしい性的虐待を受けていたということを明らかにしているにも
かかわらず、そうした論客たちは、これらの女性たちが強制的に狩り集められ
たという証言を無視し、そうした女性を集めた責任は日本国家にではなく、そ
の地域の業者にあると主張している。もっとも激しい争点となったのは、女性
国際戦犯法廷がその焦点を権力の頂点にあったひとびとの戦争責任に絞ったこ
とである。そこには、先の天皇、裕仁も含まれていた。法廷の最後日には、裁
判官たちが合議のうえで判決を出した。このときの声明は、「慰安所」システ
ムは人道に対する罪であること、また、裕仁にはその犯罪について共同責任が
あるということを言明していた。この声明は、参加者と傍聴者から大きな拍手
をもって迎え入れられた。天皇に対する批判が厳しいメディアのタブーに取り
囲まれているこの国で、ほとんどの主流派メディアの記者たちがこうした光景
を報道する準備がなかったのも、驚くにはあたらない。
しかしながら、目下の論争のなかで問題になっている論点は、法廷に関するN
HKのドキュメンタリーの内容だけではなく、もっと特定された点であり、つ
まり放送直前の日々に起こった事件についてなのである。この物語は陰鬱であ
り、そこには対立しあう正反対の言い分が渦巻いている。それなのに、確実な
事実の方は論争の対象になっていないのである。
放送に先立つ最後の日々に、NHKの教育テレビの内部では、すでに放送予定
に入っていた番組の内容について深刻な留保を表明する何人かの上層部とのあ
いだで、かなり緊張した関係が生まれていた。二〇〇〇一年一月二七日、ドキ
ュメンタリー番組の放送三日前に、NHKは「大日本愛国党」のような極右集
団と連携した三〇人ぐらいの右翼集団の「訪問」を受けた。この連中は一団の
トラックで到着し、軍服もどきの制服を着て、予定されている番組の放送を中
止せよと要求したのである。政治演説と行進曲を大音響で撒き散らす拡声器を
装備したこの手のトラック部隊は、かれらがその見解を「反日的」とみなす施
設に押しかけては、徹底的に騒ぐのである。
やってきた右翼集団はほんの一握りにすぎないし、かれらの宣伝活動も一般に
はせいぜい騒がしい雑音程度の価値しかないが、その手の「訪問」は、日本の
政治のなかでいまにいたるまで作用しつづけている暴力的な力のことをありあ
りと思い起こさせる効果がある。たとえば、一九八七年、極右集団に属する銃
をもった男が『朝日新聞』阪神支局に入り込み、そこで働いていたひとびとに
向かって発砲し、三十歳の記者小尻知博さんを殺害した。責任者はひとりも逮
捕されていない。一九九〇年には、当時の長崎市長本島等さんが右翼に銃撃さ
れて重症を負ったが、それは、かれが天皇裕仁には戦争責任があると公的に意
見表明を行った直後だった。さらに最近では、二〇〇三年に「国賊征伐隊」と
名乗るグループが、外務省高官の自宅に対して爆弾を仕掛けた。この高官は、
かれらからは、金正日体制との交渉に際してあまりに「軟弱な」姿勢をとって
いるとみなされていた。したがって、「大日本愛国党」のような集団がやって
きたということは、連中の振る舞いが軍服もどきをまとった茶番劇程度の実質
しかないにもかかわらず、かなり深刻に受けとめなくてはならない出来事なの
である。
しかし、さらにもっと重要なことは、右翼が押しかけてから二日後の二九日に
あった松尾武(当時、放送総局長)を含むNHKの上級スタッフと有力な与党
自民党の政治家、安倍晋三との会合であった。安倍は、当時は内閣官房副長官
であった。この点は特筆しておくべきことなのだが、彼は政治支配層の内部で、
その意見がかなり重みをもつ人物であった。元総理大臣岸信介の孫として、ま
た元自民党幹事長安倍晋太郎の息子として、安倍はタカ派的な外交政策を持論
としていることで知られており、最近では現職の小泉首相のもっとも有力な後
継者とひろく目されている。(二人目の勢力のある政治家であり、その後経済
産業大臣となった中川昭一もその場に立ち会っていたと報じた記事があったが、
後述するように中川自身はあとになってこれを否定している)。安倍と松尾、
それに他の参加者たちは、一月二九日の会合で話し合われた主題のひとつが、
放送予定になっていた女性国際戦犯法廷に関するドキュメンタリーの内容であ
ったことを認めている。しかし、目下の争いの核心をなしているのは、かれら
の会話がどのような性質のものであり、どのような帰結をもたらしたのかとい
うことである。放送に先立つ最後段階で、ドキュメンタリーはその内容を決定
的に改ざんされた。新しい材料が付け加えられたのである。それは、「慰安
所」制度に対する日本軍の責任を否定する歴史家であり、法廷に対するもっと
もあつかましい批判者として知られていた秦郁彦のインタヴューであった。そ
れ以前に番組に関与していた法廷の組織者たちには、この秦と議論をしたり、
かれの批判に応答したりする機会は与えられなかった。先の天皇、裕仁に対す
る法廷の有罪判決に言及している箇所について、これをすべて消去するという
決定も行われた。さらに重要なことは、安倍と会ったあとで、そしてそれは番
組放送まで二十四時間もない時点なのだが、NHKの上層部がさらに土壇場の
変更を求めたという点である。放送時間はこれによって四十四分から四十分に
まで切り縮められた。軍による性的虐待に関する中国人犠牲者の証言は削除さ
れ、また「慰安所」制度に対する軍の責任や、そこで働かせるために集められ
た女性たちに加えられた暴力について語った元日本軍兵士の証言も消去された。
結果として、ドキュメンタリーの最終版には法廷の手続きについて一場面も含
まれておらず、それが行った判決についてもまったく言及されないということ
になった。この番組の放送後に、VAWW-NET Japan (Violence
Against Women in War – Network Japan)は、番組制作のために協働すること
を合意したときの条件をNHKが破ったと主張して、放送局と二つの製作会社
を、法廷にダメージを与えるためのドキュメンタリーを作った廉で訴えた。そ
の裁判はいまも続行中である。
いまいちど確認しておこう。最終段階での変更が、番組の内容に関するもので
あったという事実については、争われていないのである。争点となっているの
は、こうした変更が、独立した編集担当者の決断によるものであるのか、それ
とも、NHKの編集過程に対する政治的介入の結果であるのか、ということで
ある。
告発者の物語
過去四年間にわたって、NHKのドキュメンタリー番組をめぐる争いは世論の
関心からは消えていた。この話題は、9・11、イラク戦争、日朝関係の危機、
そして日本の戦後憲法を改訂しようとする加速化する動向などの出来事によっ
て脇に押しやられていた。しかし、二〇〇五年の一月一二日、問題は、政治的
問題に対するリベラルなアプローチをすると一般に見られている全国紙『朝日
新聞』に掲載された二つの記事によって、ふたたび見出し記事の位置にもどっ
てきた。そのきっかけとなった告発者は、あとではそれが二〇〇一年一月の
チーフ・プロデューサー長井暁氏であることが明らかになるのだが、かれはN
HKの内部からカミングアウトして、番組に加えられた変更は、たしかに安倍
晋三元官房副長官や中川昭一現経済産業大臣による圧力の直接的な結果生じた
ものだと明らかにしたのである。これは重大な発言であった。他の国の公共放
送局(たとえば、英国のBBCやオーストラリアのABC)と同様に、NHK
も、法律によって外部の政治的圧力から独立を保つことが求められているから
である。
『朝日新聞』の記事によれば、NHKの幹部は、番組内容を変えるように番組
プロデューサーに命令した際に、とくに、NHKの予算がちょうど国会で審議
中であるという事実を挙げたのである。また、安倍との会見に立ちあったもう
ひとりの幹部(それがあとでは松尾武放送総局長であったことが判明する)は、
『朝日新聞』に対して、政治家による「圧力を感じた」と語り、その発言が引用
されている。その含意は明らかに、もし番組が政治家たちの要求に合致するよ
うに変更されないのであれば、財政的なペナルティがあるかもしれない、とい
うことであった。『朝日新聞』の記者は、自民党の政治家、安倍晋三と中川昭
一にも話を聞いている。安倍はNHKスタッフと会った際に、番組の内容につ
いて話しあったことを認めているが、これが「政治的圧力」を構成しているこ
とは否定した。中川は、その時点では、日本の歴史教育の内容をもっとナショ
ナリスティクにするように求める「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の
会」の代表であり、『朝日新聞』に対してつぎのように述べたと報道されてい
る。「疑似裁判をやるのは勝手だが、それを公共放送がやるのは放送法上公正
ではなく、当然のことを言った」。
この物語の意味は、背後にあるいくつかのファクターによっていっそう大きく
なる。第一のファクターは、安倍晋三の華々しい政治的登場である。安倍はい
まや自民党の幹事長代理という要職についており、日本では世論のうえでもメ
ディアでも多くの人気を集めている。しかし、北朝鮮、軍拡、そして、平和憲
法の改憲といった問題についてのかれのタカ派的なスタンスは、国内外で事態
を監視しているひとびとの懸念を招いている。第二のファクターは、いろいろ
な批判のあった重要人物、NHKの海老沢勝二会長の辞職が差し迫っていたと
いう事情である。かれの辞職は、放送組織の内部での大きな変化の先触れとな
る可能性があった。(事件が起きて以後、海老沢は会長職を辞任したが、組織
内では依然として勢力を維持している)。第三の、もっと大きな背景となる問
題は、(他の地域がそうであるのと同様に)日本のメディアのなかでも進行し
つつある、重要な技術的、組織的な変容である。この変容のなかで生じる問題
のうちでも一番大きなことは、ひょっとするとNHKは将来民営化されること
になるのではないか、という動きであった。そうこうするうちに、メディアの
所有権にかかわる厄介な問題は、新しいメディア企業家、堀江貴文がフジテレ
ビ系列に対しておこなった公然たる敵対的のっとりによって、注目されるよう
になった。
NHKからの応答は、もともとの『朝日新聞』の記事が出てから三日後に現れ、
海老沢会長自身の口から発表された。その声明のなかでNHKは、スタッフが
政治家の圧力を受け入れたという『朝日新聞』の主張をかたくなに否定した。
同時に、自民党の政治家中川が、事件についての自分の記憶はあいまいだった
と説明する声明を発表した。かれはいまや、自分は一月二九日の会見には立ち
合っておらず、NHKのスタッフに対して自分の意見を述べたのは、番組が放
送された後になってからにすぎないと言い出した。それとあわせて、NHKの
幹部松尾武は記者会見場に現れて、『朝日新聞』は、自分がかれらに述べたコ
メントの意味を完全に逆にとっていると主張した。松尾の言い分によると、か
れの『朝日新聞』に対して行った返答は、現実には自分は政治家によって「圧
力を感じなかった」ということを意味していたのだ、という。
しかし、『朝日新聞』が究明するストーリーを記者会見で否定するにあたって、
その主張をもっと洗練するために、NHKの現放送総局長はさらにもうひとつ
の声明を出したのである。これは、問題の根深さについて、あらためてひとび
とに警告ベルをならすような発言であったつまり、この幹部は、あっけにとら
れているひとびとのまえで、番組が放送される前に重要な政治家に特殊な番組
のスケジュールや内容を「説明」するのは、放送局にとっては「通常の業務」
であると公言したのであった。
メディア、自立性、権力
たしかに、公共放送の自立性が危ぶまれている国は日本ばかりではない。東京
における目下の争いは、イラクの「大量破壊兵器」に対する英国政府の動きを
めぐるBBCの報道に関して行われた二〇〇四年のハットン調査委員会や、二
〇〇一年にオーストラリア放送協会会長ジョナサン・シアーが、個人的な友人
であるジョン・ハワード首相の見解に不当に影響されているという訴えを受け
て辞任した事件を思い出させる。
しかし、日本のケースでメディアの自由の実質についてとりわけ深刻な問題を
提示しているのは、まさに報道関係者や政治家たちが、この争いに対してどう
対応しているのかという点である。民主主義においては、報道に対して政治的
圧力が加えられているかどうかという問題は、決定的に重要な論点である。も
ちろんそれは、ジャーナリストにとってだけ重要な争点であるというのではな
く、もっと一般的に、公衆の「知る権利」にとって中心的な意味をもっている。
『朝日新聞』の記事によって提起された問題は、そしてNHKが番組の内容に
ついて、選ばれた政治家たちと放送前に定期的に話し合ってきていたというこ
とは、メディア倫理に反しているだけではなく、法律にも違反している可能性
がある。
ちゃんと機能している民主主義のシステムでは、そうした深刻な告発があった
場合、それが野党政治家やメディアの力によって、議会の、あるいは司法機関
の調査委員会のような独立した機関によって問題を徹底的に調査せよ、という
厳しい要求に転化すると期待できるだろう。ところが、日本ではこのような反
応は起こらなかった。まさにそのことが、この国の現在の政治システムのなん
たるかを語っているのである。一九九〇年代のちょっとした時期を除けば、自
由民主党は(単独でか、あるいは連立の主導的なパートナーとして)過去五十
年間一貫して政権の座にありつづけた。ここ十年間のあいだに、相対的に小さ
いがかなりはっきり声をあげてきた社会民主党(かつての社会党)の議席は激
減してしまい、新しい勢力としての民主党が日本の主要な野党として登場した。
民主党は、雑多な政治家たちの集団が最近になって合同してできたものであり、
そのリーダーシップは、かなりの部分が、与党自民党のかつてのメンバーで、
一九九〇年代にそこから分かれたひとびとによって握られている。他の重要な
社会的、政治的、外交的な論点と同様に、NHK事件についても、民主党は内
部の深刻な不一致によって引き裂かれているために、党の指導者たちは目の前
でおこっている論争に深く関わっても、あまり得策ではないと判断したようで
ある。民主党の執行部は、この事件が「報道の自由にとって重要な問題」であ
ると厳かに宣告したにもかかわらず、この声明に続いて、独立した調査機関の
調査を行うべきだという主張を実効力ある形で押し出すことができなかった。
そうこうしているうちに、日本のメディアの残りの部分は、全体としてこのス
トーリーを取り上げることに決めたのだが、それはただし、ジャーナリズムの
独立と政治的介入をめぐる争いとしてではなく、むしろふたつの競合しあう組
織、NHKと『朝日新聞』とのあいだの喧嘩としてである。それはスポーツの
ような見世物であり、そこで観客にはふたりの出演者が罵りあっているのを眺
めていただこうというわけである。(たとえば月刊誌『文藝春秋』はそのメイ
ンの記事に「NHKvs朝日、メディアの自殺」というタイトルをつけたし、
『Yomiuri Weekly』は、その記事を「泥仕合『NHK』と『朝日』――大嘘つ
きはどっちだ?」と題して掲載した。
この点で、日本の主流メディアの構造についてもう少し述べておく必要がある
だろう。日本には五つの日刊全国紙がある。『朝日新聞』と『毎日新聞』は、
一般的には、政治的スペクトルムの「リベラルな」側に位置していると見られ
ている。ビジネス紙である『日本経済新聞』と『読売新聞』、『産経新聞』は、
そのスペクトルムの「保守的な」側に位置している。NHKと競合する主要な
テレビ局はどれもみな、さまざまな新聞グループのうちのひとつと連携してい
る。
すでに見てきたように、たくさんの日刊誌や月刊誌も存在しており、それらは
主要な日刊全国紙と連携しているものものもあれば、有力な出版社が出してい
るものもある。雑誌は、もっとも部数の多いものでは五十万部を越えている。
週刊誌では、主要な記事は一般に無署名であり、慣習として、全国紙のそれよ
りも、その正確さの程度という点で厳密性を欠いていても許されてしまってい
る。週刊誌は部数競争をする傾向があり、それぞれがいま関心を呼んでいる話
題について、衝撃的なすっぱ抜きのネタを探し出し、他誌を凌ごうとしている。
近年の販売部数の低下傾向が、こうした競争の獰猛さに拍車をかけている。た
しかに積極的な面では、こうした週刊誌は、非常に慎重な全国紙が触れようと
はしない政治的スキャンダルを暴露するという重要な役割を演じることはある。
しかし、否定的な面をみると、そのジャーナリスティックなスタイルは、噂や
あてこすりやヒステリーを煽り立てることで、たまたまこの週の号を飾る残忍
な個人攻撃の標的になった運の悪い人物の人生を破滅させるだけの力を持って
いる。
『朝日新聞』が自分でもっている週刊誌は、論争が起こった週には、その話題
について沈黙を守ることにしていた。(もっとも、グループの月刊誌『論座』
は、あとになって、新聞の立場を支持する一連の分析的な記事を出してはいた
が)。『毎日新聞』系の週刊誌は、この事件について、与党自民党とNHKと
の関係に焦点をはっきりと絞りこんだ記事を掲載した。しかし、そうした声は、
政治的介入からのNHKの独立性という問題について論じるのではなく、むし
ろ事件の端緒となった『朝日新聞』によるすっぱ抜き報道を攻撃することに一
生懸命になっている他の有力誌のかまびすしい野次によって、かなり減殺され
てしまった。
たとえば販売部数の多い『週刊新潮』は、この問題についての報道を「魔女狩
り」(安倍、中川といった政治家たちに対して『朝日新聞』が行った批判を指
している)や「ジャーナリスティックな嘘」(『朝日新聞』の報道を指してい
る)という言葉を使って書きたてた。他の雑誌は、いくぶんかだけもっと微妙
なスタンスをとった。たとえば、『週刊文春』は、読者にむかってNHKと
『朝日新聞』両者の「醜悪な体質」を暴露するという記事をメインに立てた。
一見するとこれは、論争に対するバランスのとれた評価を下しているように見
えかねない。しかし、実際に読んでみれば、その記事の中心的な議論は、きっ
かけになった告発記事を書いた『朝日新聞』に対する激しい攻撃以外の何もの
でもないことがわかる。NHKのスタッフについての多くの辛らつなコメント
も書かれているが、この組織に向けられた主要な批判は、そもそもNHKが無
責任にも女性国際戦犯法廷についてのドキュメンタリーを放送しようなどと試
みたことに絞られていた。『週刊文春』の記事は、そもそもあらゆる問題の諸
悪の根源は、このテレビ番組の「幼稚な本性」に他ならないと結論づけている。
この問題についての、センセーショナルな線をねらった雑誌記事の、とくに不
穏な特徴は、事件に関わっている何人かのジャーナリストに対する非常に個人
的な攻撃であった。とくに顕著であったのは、『朝日新聞』にきっかけとなっ
た記事をすっぱぬいた本田雅和記者に対するものであった。本田記者は、『朝
日新聞』で長いキャリアがあり、環境汚染や対イラク戦争、そして最近では東
南アジアの津波被害などの諸問題について、よく調査した裏づけのある報道を
することで知られていた。『週刊文春』は、(他のこととあわせて)北朝鮮に
対する本田記者の関係について、一連のあてこすり記事を載せることで、かれ
の信頼性を掘り崩そうとしたのである。一九七〇年代、八〇年代における北朝
鮮の機関による日本市民の拉致が暴露され、北朝鮮への敵意が日本でひろがっ
ている時期には、そうした当てこすりは、特別な政治的打撃力をもっていた。
そこに含まれているレトリックはこまかく検討しておく必要がある。というの
も、それはこの週刊誌のジャーナリスティックなスタイルがいかなるものであ
るのかを示す鮮やかな一例であるからである。
女性国際戦犯法廷での国際検事団のなかには、南北コリアから来た十二人のメ
ンバーからなるチームが含まれており、優れた韓国人弁護士に率いられていた。
そのチームのひとりが、黄虎男だった。黄は北朝鮮の公的な立場にあり、日本
についてのアナリストで日本語を流暢に話す。かれは、日本と北朝鮮とのあい
だの公式、非公式の会合にも参加していた。『週刊文春』の記事は、氏名を伏
せた「(日本)政府筋の人物」の発言を引用して、その黄を広義の北朝鮮「工
作員」だと書いたのである。『週刊文春』がいう政府側情報源は匿名になって
いるが、政治家安倍晋三が、これと同じ主張をNHK問題に対して応答する際
に繰り返しているということには留意しておく必要がある。
「北朝鮮の工作員」という言葉は、過去二年間に、日本のメディアで非常に広
く使われてきたものであり、一般に世論のなかでは、七〇年代、八〇年代にひ
そかに入国し、日本の市民を拉致した犯罪に責任のある秘密機関が連想されて
いる。「広義の北朝鮮の工作員」という言葉で暗示されている内実は、ある人
物の推測である。『週刊文春』の記事(と安倍晋三)は、その黄について、か
れが北朝鮮の官吏であり、その能力によって、いくばくかのたいして意味のな
い政治的見解を表明したということ以上には、有罪であるという証拠を提示で
きなかった。しかし、そのフレーズは、何かまがまがしい勢力が働いているの
だという悪意に満ちた不安を掻きたて、それによって望みどおり、ひとびとの
あいだに戦慄を引き起こすことに役立ったのである。
つぎの段階は、こうした不吉な勢力と『朝日新聞』の本田記者とのあいだにつ
ながりをつけることである。ここで『週刊文春』は、非常に薄っぺらな材料か
ら、何かを作り上げなくてはならなかった。女性国際戦犯法廷の直前に、本田
記者が、日本ではよく知られているNGOが運営している学習クルーズ、ピー
スボートに参加していたこと、またその航海の旅程に北朝鮮への寄航が含まれ
ていたということが読者に向かって暴きたてられる。この航海の途上で本田記
者は、北朝鮮からの参加者が法廷への参加に同意したという報告記事も書いて
いた。「その結果として日本に来た人物が、黄虎男であった」と、『週刊文
春』の匿名ジャーナリストは結論づけている。
言うまでもないことだが、本田記者が北朝鮮を訪問し、また北朝鮮のひとたち
が女性国際戦犯法廷に近々参加するつもりであるということを報道したという
事実は、政治的にもジャーナリスティックにもおよそ文句のつけようのないこ
とである。またこの情報は、『週刊文春』が書き立てている話題、つまり、N
HKの編集権に対する政治的介入という問題についてのわたしたちの理解には、
何も付け加えてはくれない。しかしながら、言葉巧みに、『週刊文春』の記事
は、本田記者のジャーナリズムが、脅威となる「広義の北朝鮮工作員」として
公的に特定された人物を日本に送り込むことになんらかの意味で責任があった
かのようにほのめかすことに成功している。現在の日本が持っている世論の風
土のなかでは、これは読者の心のなかに、本田記者とかれの書いたものが、よ
く言って疑わしく二枚舌であると、また悪い場合には、陰謀であり犯罪である
という怪しげな理解を植えつけることに役立った。似たような中傷は、他のい
くつかの雑誌でも繰り返された。そのなかには、右派の月刊誌『諸君』も含ま
れている。『諸君』は、記事全体を、本田記者のキャリアや個人的な信念に対
する長い悪意に満ちた分析に費やしたのである。
『週刊文春』や他の雑誌が『朝日新聞』の貧困な報道水準なるものに投げかけ
る説教じみた御託宣と口汚い個人攻撃のコンビネーションは、ぱっと見にはじ
つに面白い見世物に見える。ところが、繰り返されるこの種の報道には、つぎ
のように読み解かれるべき深刻で笑い事ではすまないようなメッセージが含ま
れているのである。つまり、政治的支配層を決定的に困らせる記事を書くジ
ャーナリストは、その同業者から罰せられるのであり、そしてもし可能ならば
一緒に口を封じられるのだぞ、というメッセージである。
したがって、NHK問題に対してどう応じるのかということは、マスメディア
と民主主義の問題の核心に届くような大切なことがらなのである。これまでの
メディア理論では、自由な報道とは、政治家がその権力の限界を踏み越えると
きに、政府の活動を監視し吠え立てる「民主主義の番犬」(watchdog)として
働くものだと想定されている。しかし、最近のメディア批判は、はたして今日
の寡占化したマスメディアが「番犬」の役割を果たす能力も意志も持ちあわせ
ているのかどうか、疑問視している。たとえば、二〇〇四年のアメリカのドキ
ュメンタリー映画『出し抜いて』(”Outfoxed”)は、マードック・メディア帝
国とジョージ・W・ブッシュ政権とのあいだの緊密な共犯関係に光を当ててい
た。[ “Outfoxed” は二〇〇四年にロバート・グリーンワルドが、マードック
資本のもとで働いていたひとびとの証言とかれらが持ち出した内部文書をもと
に、その政治的な虚偽を告発したドキュメンタリー作品。タイトルのOutfoxed
には、巨大メディア資本マードックが支配する、保守的でブッシュお気に入り
のフォックス・テレビから抜け出すということがかけてある。――訳者]
日本のメディアの実情を観察しているひとびとは、もはやそれが「番犬」
watchdog というよりも、政治的エリートの権益を守るための「飼い犬」guard
dog として機能するようになっているとも考えている。NHK問題は、メディ
アと政治権力とのそうした構造的癒着のいくつかの側面を照らし出している。
NHK経営陣が、問題になりかねない番組の内容をあらかじめ特定の政治家と
話し合うことは「通常の業務」であると公然と言明したことは、明らかに、そ
の組織が行う放送の独立性の全内容を疑わしいものにしたのである。
また、『週刊文春』の記事が示しているように、商業誌がたえずスクープを探
しているという姿勢は、政府に近い「ひとびと」からの、つまり、親しいメデ
ィア関係者にオフレコで話をしたいと思っている高級官僚や政治家からの、権
限のないコメントに深く依拠するという事態を生みだしてしまう。実際に、N
HK事件によって明らかになった枢要な問題とは、(新聞であれ、テレビであ
れ、週刊誌であれ)個々のジャーナリストと有力な政治家とのあいだにできる
非常に親密な個人的関係であった。日本のジャーナリストは、たえず特定の政
治家を追っかけ、かれらの正式な公的活動だけでなく、非公式の発言や社会的
活動にも立ち会うようにと命じられている。そのうちに、こうした指示は親密
な個人的関係に転化してしまうことが多い。そこでは、ジャーナリストはやす
やすと、その政治家が撒き散らしたいと望む情報を広めるための格好のチャン
ネルとなることだろう。もちろん、その見返りは、そのジャーナリストがその
関係からときたま「スクープ」を手にいれられるという期待である。だからそ
うしたチャンネルを維持することは、新聞や雑誌が商業的に成功を収めるため
にはどうしてもなくてはならないことであると見なされている。
主流派の雑誌は、体制のなかで敵意や嫉妬を買う個々の政治家については、か
れらを相対的に安全なターゲットにするために、すすんで暴露をすることはあ
る。しかし、体制全体を困惑されるような構造的な問題と取り組むことはけっ
してしない。NHKのケースでは、多くの週刊誌が、あきらかに、批判的な吟
味の矛先を政府とNHKとのあいだの関係から逸らし、『朝日新聞』を攻撃す
ることのほうが自分たちには政治的に得になると決めていた。そうすれば発行
部数を押し上げられるだけでなく、同時に、政治的官僚的エリートのなかにあ
るかれらの頼りとする情報源に対して点数を稼ぐことができるからである。そ
の結果生まれるジャーナリズムは、餌をねだるロットワイラー種の熱心さよろ
しく、忠実な「飼い犬」ぶりを発揮するというわけである。
「公平でバランスのとれた報道」
日本のメディアは、世界の他のいくつかの国々のメディアとは違って、法律や
憲法によって言論の自由が保障されており、明確な政府検閲もない環境で仕事
をしている。しかし、NHK事件はリトマス試験紙のような働きをして、建前
としてのこのメディアの自由が、腐食力をもった力が組み合わさったことでど
れほど空洞化してしまっているのかを明らかにした。こうした力の第一は、日
本には力強い政治的反対派が欠落しているということである。また第二に、メ
ディア組織と与党の政治指導者とのあいだの裏側での隠された連携関係である。
第三に、極右テロリストの存在である。かれらのときどきの暴力的行為や、非
常に頻繁に行われる暴力的な脅しを、日本の警察は抑えることができず、また
抑えるつもりもない。さらに第四には、少しでも他社を出し抜こうという戦略
から、政治的体制にとって敵対的であるとみなされる個人や組織に対して、繰
り返し大げさな表現で攻撃を加えることをいとわない主流派の商業報道の存在
である。こうした四つの力のどれも、ただそれだけでは、言論の自由を深刻に
危険にさらすのには十分であるとは思われない。しかし、それらがいっしょに
働くと、(もっとも根強いタブーである)天皇制から、南京虐殺や「慰安所」
の運営のような戦争犯罪、そして、現在の日朝関係の多くの局面にいたるまで、
広い範囲にわたる重要なトピックスに対して企てられた実のある批判的議論を、
もみ消すような環境を作り出してしまうのである。こうしたタブーは、日本と
そのアジアの近隣国とのあいだで、歴史的記憶と責任の問題に関して、目下対
立関係が浮かび上がっているという事情があるのだから、ますます重要なので
ある。
日本人の多数派は、日本がイラク占領に軍事的に参加することに反対している
という事実があるにもかかわらず、この主題も、公共的な批判にとって危険な
領域をもっている。このことは、二〇〇四年にイラクの反政府勢力によって誘
拐された不運な日本人三人に向けられたメディアの獰猛な攻撃に表れていた。
日本政府がアメリカの対イラク政策を支持していることをあえて問題にしたか
らという理由で、事件の犠牲者とその家族は、解放されて日本に戻る以前から
ですら、国内メディアによって晒し者にされたのである。この事件もまた、い
まや日本のマスメディアにおける自由な論争をさらに押し殺している五番目の
成長しつつある力を(いささか逆説的な仕方でだが)明るみに出している。そ
れは、巨大で影響力をもつインターネット上のチャットグループの出現という
事実である。インターネットは、政治的問題を公共的に討議するためのオルタ
ナティヴな自由なフォーラムとなるだけの潜在的可能性を持っているにもかか
わらず、「2ちゃんねる」のようなグループ(これは世界最大のインターネッ
トチャット集団である)は、これまでのところ、自由どころか、週刊誌の今日
の強迫観念が反復され極大化されるような場所となる傾向をもっており、そこ
では(イラクの誘拐事件のように)たいていは主流派メディアの不安と嫌悪の
最大のターゲットとなる存在に対して、匿名のヘイトメールが雪崩をうって襲
いかかるという状況が生まれている。
皮肉なことにNHK事件は、まさしくメディアの自由を守るために案出された
概念そのものが、いかに公共的な論議をますます抑圧するために使われかねな
いかということを示している。事件に対する与党からの主だった反応は、自民
党幹事長代理である安倍晋三によってもっとも雄弁に主張されているが、それ
は論争の焦点を、NHKに対する政治介入という問題から、『戦時性暴力を問
う』というドキュメンタリーの「公平さとバランス」という問題へとずらして
しまうことだった。
安倍が持ち出し、日本の多くの主流派メディアによって忠実に反復されている
論拠は、つぎのようなものであった。つまり、女性国際戦犯法廷は、特殊な政
治的な議題に関してNGOによって組織されたイベントであった。NHKが法
廷についての番組を作ることは許容できるが、特殊なNGOの観点に緊密に結
びついたり、あるいはその議題を国民に無批判に提示することは、国営放送に
は許されない、というのである。公平でバランスのとれた放送という基本的な
原則が、NHKにドキュメンタリーのなかにNGOに対する批判の声を入れる
ように要求したのである。ドキュメンタリーの放送の前日にNHK上層部に対
する安倍の抗議は、単純に、これらの「公平とバランス」の原理を守ることを、
放送局にちゃんと思い出してもらうようにすることにあっただけだ、というこ
とになる。
こうした「公平でバランスのとれた報道」に対する一見理性的な要求は、しか
しながら、それが適用されたときには大いに問題である。というのも、あらゆ
る番組ないしメディア組織に対してそれが全面的に適用されるのではなく、も
っぱら政治的に批判的な立場をとっているような番組、記事、メディア組織に
とってだけ適用するからである。実例に沿って、NHKとあるNGOとのあい
だの関係を、さらにもう少しこまかく見てみよう。
多くの雑誌が、安倍の「公平でバランスのとれた報道」という言い分をただ反
復していたその週に、NHKの主要なニュース放送は、北朝鮮によって拉致さ
れた犠牲者の家族の会(AFVKN、一般に日本国内では「家族会」という組織と
して知られている)の活動をメインのニュースにしていた。このNGOは、北
朝鮮に対する制裁を求める多くの請願署名を集めてきた。このニュースばかり
が例外的にそうだったのではない。2002年以来、家族会とその姉妹NGO
である北朝鮮に拉致された日本人を救う全国協議会(NARKN、一般には「救う
会」と呼ばれている)が行ったデモ、公的な集会、そして記者会見は、NHK
のニュース放送によって、非常に頻繁かつ詳細に取り上げられてきたのである。
この二つのNGOは、拉致されたかなりの数の日本人市民がいまだに北朝鮮に
囚われているという見解をとっている。そして、かれらの帰国を確実にするた
めに金正日体制に対して、制裁やその他の懲罰的措置をとるように求めている。
「家族会」も「救う会」も、ともに自民党の安倍晋三幹事長代理を含む有力な
政治家との強い関係を作り出すことに成功している。 NHKは非常に頻繁に
この二つのNGOの活動をニュース報道しているが、その際に、かれらの政治
的スタンスを問題視するなんらかの人物のコメントをあわせて報道し、それで
バランスをとるというようなことはけっして行われていない。また、国営放送
が繰り返すこれらのNGOの活動や声明をめぐる報道は、けっして日本の政治
的指導者や主流派メディアから否定的なコメントを引き出すことはなかった。
逆に、VAWW-NETを公然と支持するひとびとは獰猛なマスメディアの批
判の標的であったのに対して、「家族会」や「救う会」の見解に対する公的な
批判は、いまでは日本のメディアタブーの、どんどん拡大しつつあるリストの
なかのひとつに加えられてしまった。
同じように、他のメディア組織が続けてきた『朝日新聞』に対する批判キャン
ペーンの最新の波が、いまや『朝日新聞』と本田雅和記者に向けられたメディ
アの敵意として高まっているのである。攻撃の主要なターゲットは、『朝日新
聞』によるいわゆる「バランスを欠いた」日本政府に対する批判である。『朝
日新聞』の(本田記者を含む)ジャーナリストは、反政府的な課題に取り組む
NGOや社会運動に近いとあまりに頻繁に言われている。この批判キャンペー
ンは、一九八七年の『朝日新聞』の小尻記者の暗殺直後に勢いを得て、新聞の
編集方針に一定の効果をもったようである。『朝日新聞』は、いまでは、相対
的に保守的な学者や公人のコメントで、主要な政治的な記事の批判的、左翼的
な部分に対するバランスを定期的にとっている。こうしたもののすべては、も
しも保守的な『産経新聞』や『読売新聞』による類似のシフトがあり、重要な
批判的左翼的な論客にその紙面がより多く提供されるようになったというので
あれば、まだ賞賛すべきことであるかもしれない。しかし、言うまでもなく、
そうした変化はおきなかった。それにかえて、「公平とバランス」に対する一
方的で選択的な要求が、実際には、日本のメディア報道が抱えているスペクト
ルムの全面的なバランスをずっと右に押しやり、その過程でますます批判的な
声は周縁化され、自分自身や自分の家族の安全と心の平和を、論争的なトピッ
クスについて公共的な発言をするリスクを犯すことで乱されたくないと思うひ
とびとに、沈黙を選択させたのである。
自由な論争を求めて
「でも、脅威を感じていますか。」
「あなたの(またはあなたの家族の)安全について、不安に思うことはありま
せんか。」
日本政府の態度や現代日本社会のある潮流について批判的なメディア評論を書
いている同僚たちに向けられたこうした質問を、わたしはこれまでなんど耳に
したことか。その回数をもう忘れてしまった。問いに対する答えはひとさまざ
まである。しかし、こうした質問が、日本の学者やジャーナリストなどのあい
だの、ありふれた夕食時の会話の一部となっているという事実こそが、驚くべ
きことである。脅迫の性格は無定形だが、むしろそのことがその効果をいよい
よリアルにしている。日本のなかの一定のひとびとは、そうした脅迫の影響力
を無視したりそれに抵抗したりする能力をもってはいるが、疑いもなく、この
ような無定形の恐怖の雰囲気に直面して、マスメディアに自分の見解を表明す
ることをやめてしまった研究者やその他の職のひとびとがたくさんいる。かれ
らが直面したのは、ヘイトメールが殺到することへの恐怖感、命が危ないので
はないかという不安、週刊誌の個人攻撃の標的になるのではないかという不安、
メディアによって「極左」とか「反日的」という刻印を押されることに対する
不安、そして世論のなかでタブーになっていることをとりあげたことで自分の
キャリアを台無しにしてしまうのではないかという恐れであった。
NHK問題は、ことがらの入り組んだ細部のひとつひとつを含めて、試金石と
なりうるだろう。NHKに対する政治介入があったという主張を検証するため
の独立した委員会は、そもそもいつの日にか設立されるのだろうか。物語の真
実は法廷で明らかにされるだろうか(というのも、NHKの幹部連中は、『朝
日新聞』に対する名誉毀損の訴えを起こすとぶつぶつ言いだしているからであ
る)。NHKの幹部や政治家たちは、事件に対する外部からの詳細な調査から
うまく逃げおおせ、問題を「未解決のミステリー」として世のひとびとの記憶
から消すことができるだろうか。『朝日新聞』やそのジャーナリストに対して
競合紙によって行われている攻撃は、『朝日新聞』の編集方針のさらなる変化
を促すことになるのだろうか。ジャーナリストたちは、これからも、論争を引
き起こしかねない事件をたためらわずに報道するだろうか。この事件によって、
どの人物のキャリアが底上げされ、だれのキャリアが破壊されるのだろうか。
事件は日本の主流派メディアの構造的な問題を照らしだした。しかし、それは
同時に、政治とメディアのあいだのつながりがもつ息苦しくなるような勢力に
対して、抵抗の基盤として役立つかもしれないような日本社会のいくつかの特
徴にも光をあてることになった。民主党からも主流派の全国メディアからも、
政府とNHKとのあいだの関係を徹底的に調査せよというはっきりした要求が
出てこなかったために、この問題を取り上げるという課題は広く日本の民衆に
ゆだねられている。事件が明らかになった週に(自分たちの主張を広げるため
につねにインターネットを利用している)たくさんの市民社会のネットワーク
が、メディアに対する政治介入を批判して声を挙げた。政治家に放送予定の番
組の内容を説明するのは「通常の業務である」とNHK幹部が表明したことは、
「NHK視聴者のストライキ」を引き起こし、多くの市民は政治的影響力から
の独立性をふたたび確立するまで、受信料の支払いを留保すると宣言した。
こうした運動そのものが、日本のメディアのなかでどのように報道されてきて
いるのかは興味深い。『朝日新聞』『毎日新聞』『日本経済新聞』は、それに
ついて短く報道したが、予想通り、国民的メディアの大半によって黙殺された。
しかし、運動は、日本の多くの地方新聞ではかなり広範に記事になつた。『北
海道新聞』や『高知新聞』は、NHKが政治的な圧力からの自立性を守るよう
に保証する市民の行動を支持する社説を掲載した。当然にも地方メディアは、
その土地の勢力家の家族と財政的にも人脈的にも緊密な結びつきがあることが
多いし、こうした一族はその地域の問題の報道する新聞の姿勢にも影響を与え
かねない。しかし同時に、そうした地方新聞は、(たいてい東京に拠点をお
く)全国メディアよりも、中央政府から距離をとっている。そして、政治家や
政府の役人に人脈的に依存することもずっと少ない。そのため、そうした新聞
はより積極的に、批判的、自立的な仕方で全国ニュースを報道するか、あるい
は主流派の全国メディアが無視する社会問題をとりあげようとすることがある。
たしかにインターネットのチャットグループが、全国的な弱いものいじめの場
として使われてしまうような昨今のケースがあったにしても、インターネット
は、自由な公共的論争のための重要で可能性の豊かな場を作りだしている。あ
らゆる非政府組織が主流派メディアに同じように取り上げられるチャンスを持
っているわけではない。だが、公衆に自分たちの見解を伝達するための手段と
してのインターネットには、だれでも平等にアクセスできる。韓国にひろがっ
ているインターネット新聞のようなメディアは、日本ではなかなか根をおろせ
ないでいるが、オンラインジャーナリズムの実験は、しだいに大きな関心をひ
きつけるようになってきている。これらはインターネットテレビサービス
Videonews.com のようなサイトを含んでおり、NHK事件についても重要な材
料を放送している(そのなかには、告発者長井氏の記者会見のノーカット版や
日本のジャーナリストやメディア研究の専門家グループによる「事件を調査せ
よ」というアピールも含まれていた)。インターネットメディアは、主要紙で
は聴き取られることのない声のための空間を開き、既存の境界をこえたさまざ
まな連携の可能性を創出し、日本でメディアの問題に関わっているひとびとが、
自分たちの意見をひろく共有しあい、他国における類似の問題を抱えるひとび
との経験から学ぶことを可能にしてくれる。
市民社会、地方メディア、そして新しいオンラインネットワークが手をたずさ
えたならば、ひょっとすると、日本の主流派ジャーナリズムをますます包摂し
つつある自己検閲と大勢順応という腐敗した風土に対して、それが対抗力を生
み出す日がいつか訪れるかもしれない。
[原文]
Free Speech – Silenced Voices:
The Japanese Media, the Comfort Women Tribunal, and the NHK Affair
By Tessa Morris-Suzuki
Posted at Japan Focus August 13, 2005.
http://japanfocus.org/article.asp?id=365
Copyright C 2005 Tessa Morris-Suzuki
TUP配信許諾済み。本稿の無断転載を禁じます。
==================================================================
[ゲスト翻訳者]岩崎稔 /MEKIKI-net(Citizens for
Responsible Media メディアの危機を訴える市民ネットワーク):
http://www.jca.apc.org/mekiki/
—
minami hisashi