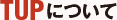■■メールマガジン「PUBLICITY」No.1866 2009/08/28金■■
23歳のロバート・ザバラは、祖母の死後、「安定した生活を得られる場になるだろう」と考え、海兵隊に入隊した。(中略)
「新兵は全員『殺せ』と返答することを求められています」とサンフランシスコのKGOテレビにザバラは語った。
「それで、400人ぐらいの新兵が声を揃えて『殺せ、殺せ、殺せ』と繰り返し唱えていると、しばらくたつうちに、その言葉にはほとんど意味がなくなってきます。
これはどういうことなのか。あまり頻繁に口にしていると、ナイフで喉をかき切る殺人テクニックを練習しながら何度も何度も繰り返す『殺せ』という言葉が何を意味し、何をもたらすのかをまったく考えなくなります」
『冬の兵士』80頁 第2章「人種差別と非人間化」
▼ザバラさんの体験はこう続く。
----------------------------
上申書によると、基礎訓練キャンプの別の教官は「士気高揚を目的とする動画」を新兵たちに見せた。
「やつらをぶち殺せ」という歌詞を含むヘビメタの曲に乗せたその動画には、イラク人の死体、爆発、銃撃戦、ロケット砲などが映し出されていたという。
他の新兵たちがロックのビートにあわせて頭を振っているのに、自分は泣いていたとザバラは語る。
81頁
----------------------------
▼しかし、ザバラさんは訴訟を起こし、海兵隊から去ることができた。その局面では幸いにも「法治」の原則が機能したわけだ。『冬の兵士』のなかで、数少ないホッとする箇所である。しかしニッポンに当て嵌めて考えると、寒気が走る箇所でもある。
■非人間化は人間の宿命なのか
▼こうした殺人訓練の起源は『冬の兵士』でもしっかり説明されているが、米軍の確固たる伝統である。科学的な根拠に基づいた方法であり、たとえばデーヴ・グロスマンの『戦争における「人殺し」の心理学』(ちくま学芸文庫)や『「戦争」の心理学 人間における戦闘のメカニズム』(二見書房)をはじめ、幾つもの本でその実態が明らかにされている。
一言で言えば、敵を非人間化するために、まず自らを非人間化するのである。
そして若者たちは戦場であろうと戦場でなかろうと人間を殺した。戦い、女性を殺し、子どもを殺し、老人を殺し、病人を殺した。イラク人を人間として扱わず、自分自身も人間ではなくなった。
国のために非人間化した生きものが、生き延びて、やがて「人間の世界」に還って来た時、どのような反応を経て、人間に再生するのか。もしくは、再生できないのか。この問いは、「国家」という仕組みのなかで生きざるを得ない人間の宿命になった。
人間が化け物になって久しい時代を、ぼくたちはいま生きている。その事実を自覚する人もいれば、自覚しない人もいる。自分自身が化けものになりうる存在であると知って生きるか。人間のつもりをした化けものとして生きるか。
それは各々の自由だ。
■「個人的な証言」の重要性
▼反戦イラク帰還兵の会/アーロン・グランツが編集した証言集『冬の兵士』は、国家と人間との間で引き裂かれた若者たちの、悲劇的な反応をめぐる記録である。そして本書の重要な特徴は、その内容を要約することができない、というところにある。なぜなら『冬の兵士』は、極私的な物語の集成だからだ。
アメリカの神学者ハーヴィー・コックスは、1973年に出版された『民衆宗教の時代』の中で、人間の社会には「物語」と「信号」という二つの体系があると論じた。
そして現代(つまり1970年代のアメリカ社会)は「信号」が「物語」を圧倒しており、「われわれの社会は今日、信号の致命的な過重によって災いを蒙っている」(21頁)。
そんな窮屈な社会の中で、精神を豊かにして生きるためには、「物語」の重要性をどれほど強調してもしすぎることはない、とコックスは訴える(序論──物語と信号としての宗教)。
「人間は話をする者であり、物語なくしてわれわれは人間となることはできない」(15頁)
▼コックスの言う「物語」とは、「個人的な証言」である。いまここに生きている私は、どのようにして人生の「目」を開いたのか、何によって人生の「目」が開かれたのか。その個人的な、秘められた体験を語る証言こそが、キリスト教の(そしてほとんどすべての宗教の)根幹をなす、というのである。
それは語り手の内部で始まり、そして「これは私に起った出来事である」というものである。最近は無視されているが、証言は宗教的講話の原型として回復される必要がある。
それは独自性のあるもの、風変りなもの、そして具体性に富んだものを祝う一つの類型である。
近年、証言があまり重要視されなくなったのはわれわれの工業社会が、人間的な面においても、機械的な面においても、取り換えのきく部分品を強調し、その結果、特殊なものと不規則なものは危険なものであると感じていることに関係があるのではないかと私は思う。
12頁
▼また、「個人的な証言」とともにコックスが重要視する形式は、彼が「民衆の宗教」と呼んでいる、「集団的物語」「共同の証言」である。これも非常に興味深い内容なのだが、ここら辺で脱線から戻ろう。
▼ぼくは『冬の兵士』を読んで、このコックスの物語論を思い出した。様々な受容、解釈ができうる、個人的な証言が増えれば増えるほど、社会が豊かになる。そうコックスは説いた。ぼくも同感である。
コックスの物語論は「近代」を経たすべての社会にとって重い価値を持つだろう。現在のニッポンにおいてもだし、もちろん、ベトナム戦争から30年以上経って、再び愚劣なイラク戦争を起こしたアメリカにとっても、だ。
ただし、『冬の兵士』の中に神はいない。だからこそ、読む者の「人間観」「世界観」が問われる物語になっている。
■民主主義とマスメディア
▼『冬の兵士』は、20世紀の民主主義というものが、いかに「マスメディア」の影響/操作によって成り立ってきたのかを感じさせる本でもある。
「民主主義」という恐ろしい世の中に生きるぼくたちにとって、戦争の責任を探る努力は辛いものである。なぜなら戦争の責任とは、時の政治家や官僚に押しつけて満足できる類のものでは、絶対にないからだ。
戦争体験の「証言」は、これまで何度も試みられてきたが、難しいものである。今回、戦争した仕掛けた側の内部で、「なぜ今この戦争に反対するのか」について語った個人的な証言を、多角的に、大量に集め、編集し得た、その功績は測り知れない。
再びコックスを引用しよう。「マス・メディアの文化は、一つの宗教であり、そしてわれわれはマス・メディアの寺院からほとんど出ることができない」(19頁)。
だからこそ、『冬の兵士』が内包している、マスメディア報道との厖大で信じがたい「ズレ」が、決定的に重要なのだ。
本書に載っている証言は、そのどれもが、まさに「独自性のあるもの、風変りなもの、そして具体性に富んだもの」である。【取り換えのきかない】「特殊なもの」「不規則なもの」であり、必然的に社会秩序にとって「危険なもの」となるのだ。
『冬の兵士』を通してぼくたちは、「マスメディアの寺院」から出ることができる。
この本を日本語に翻訳した功績もまた大きい。細かい術語の訳し方一つとっても、さぞかし苦労が多かったことだろうと推察する。2000円を切った値段にも、編集の苦労が滲み出ているように感ずる。
読みやすい、読みにくいという意見が様々あるだろうが(たとえば、目次の人名や本文のそれぞれに、内容を説明する短い見出しが付いていたら、もっと読みやすくなっただろう)、「アメリカのいま」に興味関心を持つ人なら、敢えて読まねばならない一冊である。
■マスメディアとマスメディア
▼また、『冬の兵士』は、書籍による民意の立ち上げが、いかに難しいものかを感じさせる本である。この本の存在そのものが、アメリカの民主主義に突きつけられた疑問であるとも言えよう。
戦争を始めるプロパガンダは、マスメディアが担った。しかし【この本もまたマスメディアの一つとなるだろう】。『冬の兵士』は、マスメディアとマスメディアとがぶつかり合う、そのきっかけとなる本だ。ぼくはこの点が重要だと考える。
その時に──つまり、民衆の証言運動が一定の影響力を持った時に──生じる問題がある。それは先に引用したような、現今の「マスメディアの寺院」とは別の、「もう一つのマスメディアの寺院」が出来上がる可能性であり、本気で反戦運動を考えるときには避けて通れない難題である。しかしそれは、たとえ生じるとしても先の話であり、本書の価値とは別の話だ。
「そもそも民主主義は、マスメディアとマスメディアとのぶつかり合いの果てに、その思想的正当性を生み出せるのか」--この本が真に世に問うているのは/真に世が問われているのは、そういうレベルの問題だとぼくは思う。
『冬の兵士』には、アメリカの悲惨と希望が詰まっている。
freespeech21@yahoo.co.jp
http://www.emaga.com/info/